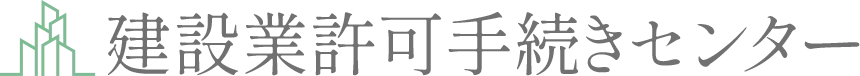【建設業許可の要件】経営業務の管理責任者とは?要件や確認のポイントを解説します。
2025/07/07
建設業許可を取得するには、いくつかの法的要件を満たす必要があります。その中でも特にハードルが高いとされるのが、「経営業務の管理責任者(以下、経管)」の設置です。
「経営業務の管理責任者って社長じゃなきゃいけないの?」
「どれくらいの経験が必要?」
「過去に建設業をやっていたら誰でもなれる?」
こうした疑問をお持ちの方に向けて、この記事では、建設業の経営業務管理責任者の要件や注意点をわかりやすく解説します。
経営業務の管理責任者とは(建設業法第7条関係)
「経営業務の管理責任者」とは、建設業を営むにあたり、会社や事業全体の経営を総合的に管理・統括する立場にある者であり、建設業の許可を取得するために必須の人的要件の一つです。法人であれば常勤役員、個人事業主であれば本人または支配人などに該当します。
建設業法第7条第1号では、以下のように定められています:
「請負契約に関して誠実性を有すること」および「経営業務の管理責任を適正に遂行できる能力を有すること」
この「能力を有すること」とは、実務上、過去の経営経験によって判断されます。
この要件は、経営判断や資金繰り、業務運営など、建設業を適切に運営できる知見を持っている人物がいるかどうかを問うものであり、実質的に会社の中核的なポジションを意味します。
経営業務の管理責任者の要件(要件充足の基本ルート)
経営業務の管理責任者に就任するためには、次のいずれかの経験が必要です。
① 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
次の要件を満たす者が、経営業務の管理責任者として認められます:
-
① 法人の場合(いずれか)
-
・建設業の法人の常勤役員として 5年以上の経営経験がある者
-
・上記法人の役員で、かつ他の建設業許可業者において通算して5年以上の経験がある者
-
② 個人事業主の場合
・本人が建設業の個人事業主として 5年以上の営業経験を有する者
-
・または、個人事業主の事業において 支配人として5年以上経営業務に従事していた者
-
これはあくまで「同一の建設業種」でなくても構いません。「建設業」としての範囲であれば、他業種での経験も通算可能です。
経営経験の内容
ここでいう「経営経験」とは、単に現場での作業経験ではなく、業務を執行する社員、取締役、執行役もしくは法人格のある各種組合の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長当営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、以下のような業務を主体的に行っていた経験を意味します。
-
予算・資金繰りの管理
-
人事労務管理
-
工事受注・契約締結の決定
-
顧客・発注者との交渉
-
許可や法令に基づく届出などの対外的な対応
※ 建設業法上の支店長(令3条の使用人)の場合も役員経験と同様に経管経験として認められます。
② 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務を管理した経験を有する者(執行役員等としての経験)
ここでいう経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者とは取締役会設置会社において、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験を持つ者(執行役員等としての経験)をしめす。
・取締役会設置会社でなければならない。
・建設業に関して具体的な業務執行権が委譲されていなければならない。
・現在の取り扱いでは建設業を所管する執行役員が一人であることを求める許可権者が多い。
③ 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
ここにいう経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者とは上記②に該当しないようなケース(建設部門担当執行役員が複数いる場合、取締役会設置会社以外や個人事業主)にも適用される。内容は令和元年改正までの第7条第1号ロの基準を引き継いだものとされている。
以前の逐条解説には、次のように書かれている。
経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者、たとえば大企業の部長、いわゆる執行役員、個人企業の事業主に次ぐ者等も、ある程度の経営経験があると認められ、また、特に個人企業の場合等は、事業主のみを要件適格者とすると事業主の死亡等により実質的な廃業に追い込まれる結果ともなり得る。そこで、特に許可を受けようとする建設業に限って、経営業務の管理責任者に準ずる地位について年限を加重して経営経験の要件を充足するものとして認めようとするものである。
※なお現在では許可を受けようとする建設業に限られない。
つまりここでいう準ずる地位は廃業を避けるための特例であり、他の手段がない場合の救済措置的立場であるともいえます。
経営業務の管理責任者になれる人の要件(要件未充足の特例ルート)
経営経験が5年に満たない場合でも、以下の特例ルートにより就任が可能な場合があります。
④ 特例①:建設業の役員経験2年以上+他業種の役員経験通算と合わせて5年以上ある者
建設業で2年以上、その他の業種を含めた法人役員としての経験が5年以上ある場合。
④ 特例②:建設業の役員経験2年以上+建設業者で役員直下の地位で財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当した経験と合わせて5年以上ある者
建設業の法人役員として2年以上、建設業者で役員に次ぐ職制上の地位で一定の経験を積んだ者である場合
上記2つの特例は、建設業者で2年以上役員経験はあるが、5年に満たない場合に、補佐人(経理・人事・経営の各部門に5年以上の実務経験がある者)を配置すれば経管になれます。
※ただしこの補佐人制度は、形式的な書類上の「補佐」ではなく、実質的に社内での指導体制が整っていることが求められます。
※④‐②の補佐人となる方の経験は許可を受けようとする建設業者での経験に限られます。
経管の「常勤性」と「専任性」に注意!
経管には「常勤であること」が求められます。つまり、週に数回だけ出社する、他社との兼任役員である、などの場合には認められません。
さらに、原則として他法人との兼職はできません。常勤性が問われる場面では、以下のような書類で確認が行われます
-
・健康保険の資格取得確認通知書
-
・所得税の源泉徴収票
-
・労働契約書
-
・出勤簿など
近年よくある質問として、複数の会社の代表取締役を兼務している場合どうなりますか?といったものがあります。どうしても、対金融機関などの関係もあって、代表取締役を外れることができないなど様々な理由があろうかと思われます。
本来代表取締役は、常勤であるとされていることから、建設業の取り扱いとしては、他法令で常勤性を求められていると考えるとその方は経営業務の管理責任者には就任できません。ただし、現状の多くの窓口の見解としては、複数の会社の代表取締役を兼任していても常勤性は問題としないというところが多いようです。
ですが、いくつかの行政庁では常勤性に問題があるとされることもあるようです。そのような場合には、経管にならない方の会社を二人代取(共同代表制ではありません)として代表権はあるが非常勤もしくは代表権はもう一人の代取りが行使するため、常勤性には問題はありませんといった形でクリアすることも考えられます。
許可後の「経管交代」にも注意!
建設業許可は、経管を「前提」として与えられています。そのため、経管が退職・死亡・辞任した場合には、その時点で許可を失う危険があります。
こうしたリスクを避けるには、
-
・後継者候補を早めに育成しておく
-
・常に要件充足者が複数在籍している状況を作る
-
・執行役員、令3条の使用人などの活用
-
・準ずる地位や補佐人制度を活用する
-
・グループ会社の役員を登用する(ただし常勤性要件に注意)
など、事前の備えが重要です。特に大企業グループの子会社で自社に役員人事権がないような会社の場合は、役員人事発表後大騒ぎになることもあります。そうならないためにもプロパーの要件者の育成など十分な対策が必要です。
行政書士などの専門家の活用も有効!
経管の要件判断は、個々の経歴や職歴により非常に複雑になります。特に特例ルートを使う場合には、書類の整備や経歴の裏付けが重要であり、行政庁によって解釈が異なるケースもあります。
そのため、建設業許可に精通した行政書士に相談することで、無理のない経管選定と確実な申請が可能になります。
まとめ:経営業務の管理責任者の設置は建設業許可の土台!
建設業の世界では、技術力だけでなく、経営の安定性も問われます。経営業務の管理責任者は、その経営面での“証明”とも言える存在です。
-
・経管要件を満たす人材がいないと、許可自体が取得できない
-
・退任すると許可が失効するリスクもある
-
・できれば常時複数の要件者が社内に在籍している体制が理想
-
・特例ルートや補佐人制度を上手く活用すれば道はある
建設業許可の取得、維持のためにも、まずは経管の体制づくりから。これが将来の発展につながる第一歩です。
----------------------------------------------------------------------
建設業許可手続きセンター
住所 : 兵庫県神戸市中央区北長狭通4-3-8 N.Rビル 5階
電話番号 : 078-332-3911
兵庫でガイドラインを守って対応
----------------------------------------------------------------------