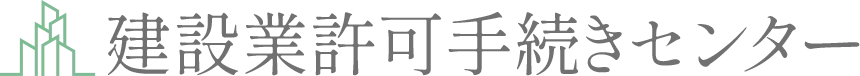地主から相当の地代に基づき地代の値上げを求められた件(私見)
2025/09/27
身内の話ですが、戦前から借りている借地の値上げを地主から言われたとの話を聞きました。
地主の見解では、現在の地代は安すぎる。権利金を払っていない場合は相当の地代(借地人に借地権割合を認めない地代)での支払いが相当とされている。あなたのところは払っていないのだから本来相当の地代を払うべきである。したがって地代の値上げをします。とのことです。
借地人の見解は、値上げは2段階でまずは現状の3倍、その後現状の8倍まで値上げしますとのことで、受け入れられるものではないとのことでした。不動産業者の方に聞くと、最近、土地代の高騰に伴い地代の値上げを求める地主さんが増えており、どちらの立場の方からの相談も増えているんですとのことでした。ただ、値上げの幅がかなり大きいですねとのアドバイスをもらったり、弁護士相談で、今まで通りの地代を支払い、地主が受け取らなければ供託、裁判の流れの中で落としどころを見つけて話し合いとのアドバイスもいただいているようです。
その中で、地主さんから、相当の地代について自身の付き合っている司法書士からアドバイスを受けている
から間違いない、疑問があるならだれか専門家に確認したらいいといわれたとのことで、(専門家ではありませんが)、私のほうに話が来たということです。
調べたところ、確かに権利金支払いが一般的な地域において権利金を支払ないで借地を借りている場合は相当の地代を支払わない限り、その権利金相当額が贈与となるという規定があることがわかりました。
しかし、そのケースが想定されているのは身内の土地に建物を建てている場合や、社長個人の土地に会社が建物を建てている場合であり、今回のように戦前から継続している借地権を想定しているものではないと思われます。
今回のように戦前からの借地権に対する、賃料の値上げの根拠と相当の地代に関して弁護士や税理士、司法書士の方の見解があるページを見つけることができなかったので、自身の備忘録を兼ねて専門家ではない一素人の意見としてブログ掲載させていただきます。(裁判などを経た法的見解ではないことをご理解ください)
相当の地代の位置づけ
「相当の地代」とは、税法上(法人税法・相続税法)でのみ用いられる概念であり、民法や借地借家法上の賃料そのものを意味するものではありません。
税務当局がこの概念を設けた理由は、土地賃貸借契約の際に権利金の授受がない場合、本来支払われるべき権利金相当額が無償で移転したとみなし、贈与課税の対象とするのが原則だからです。
ただし、借地人が「相当の地代」を地主に支払っている場合には、借地権相当の価値が移転していないと捉え、贈与課税を行わない取扱いが採られます。したがって、相当の地代とは税務上の贈与認定回避のための考え方であり、地代算定の一般的根拠とはなりません。
借地権の法律上の成立
旧借家法第1条では、建物の引渡しがあれば登記がなくても借地権は第三者に対抗できる旨が規定されていました。
現行法においても、「借地権者が土地上の建物を所有し登記していれば、借地権は第三者に対抗できる」とされており、権利金の有無は借地権の成立要件ではありません。
すなわち、法律上は建物が建築された時点をもって借地権が成立し、権利金の支払がなかったとしても、借地権の存否には影響しないと整理されます。
税務上の特殊関係取引の取扱い
税法上、権利金のない借地契約は多くの場合、同族会社間や経営者一族間といった特殊関係者間での取引に見られます。
このような場合、借地権に対する権利意識が第三者間に比べて希薄であるため、税務上は贈与認定がなされやすくなります。
しかし、相当の地代を支払っている場合は、借地権の無償移転がなかったものと評価し、贈与課税を行わないという特例的な扱いになります。
国税庁通達(平成17年5月31日 課資2-4)
この通達は、借地権の設定に際し権利金を支払わず「相当の地代」を支払うケースなど、特殊な場合の相続税・贈与税の取扱いを定めたものです。
ただし、通達においても以下が明確に示されています。
- 権利金を支払う慣行のある地域で、通常の地代(その地域で一般的に支払われる賃料水準)が支払われている場合
- 通常の地代が授受されている借地権または貸宅地の相続・遺贈・贈与の場合
これらは本通達の対象外であり、従来の「相続税法基本通達」や「財産評価基本通達」に基づき処理することとされています。
したがって、本件のように通常の地代が授受されている借地権の相続には、当該通達は適用されません。
相当の地代方式の本質
相当の地代方式は、権利金の授受を行わずに借地権を成立させるための税務上の特例的処理です。
この場合、借地権の経済的価値は「ゼロ」と評価され、贈与税や相続税の課税を免れることが可能となります。
言い換えれば、相当の地代を支払うことで課税逃れが許容されるにすぎず、借地権の法律上の効力や地代算定根拠とは直接結びつかないのです。
本件への当てはめ
本案件においては、相続時に自用地としてではなく貸宅地評価を選択して申告が行われているのではないでしょうか?
すなわち、既に借地権割合による評価減という恩恵を受けている以上、借地権が法律上成立していることは明白であり、税務上も「通常の地代が授受されているケース」に該当します。
したがって、国税庁通達(課資2-4)の「相当の地代方式」は本件には適用されず、従来通りの取扱いで足りると結論づけられます。
----------------------------------------------------------------------
建設業許可手続きセンター
住所 : 兵庫県神戸市中央区北長狭通4-3-8 N.Rビル 5階
電話番号 : 078-332-3911
兵庫で様々なご相談を受付
----------------------------------------------------------------------