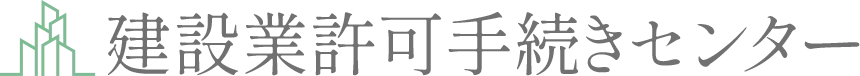監理技術者配置要件の合理化について
2025/07/14
監理技術者の兼任が可能に!特例監理技術者制度で人材の有効活用を
2024年の建設業法改正を受けて、監理技術者の配置要件が大きく変わりました。これまでは、請負金額が4,500万円以上(建築一式工事は9,000万円以上)の工事には、監理技術者を専任で配置することが原則でしたが、改正により「監理技術者補佐」を専任で配置すれば、監理技術者本人は複数の工事を兼任できる「特例監理技術者」としての運用が可能となりました。
◆何が変わった?―制度改正のポイント
旧制度では、工事ごとに監理技術者を現場専任で配置しなければならず、人材が足りない中小建設業者にとっては大きな負担でした。
ところが改正後は、監理技術者補佐をそれぞれの現場に専任配置することで、監理技術者本人は最大2現場を兼任できるようになりました。
つまり、人材に余裕がなくても、
-
現場ごとに監理技術者補佐を専任で立てられれば、
-
上位資格者である監理技術者は、効率的に複数現場を指導・統括できる
という「合理的な人材活用」が可能になるわけです。
◆近畿地方整備局の運用方針とは?
実際にこの制度を運用する際のルールは、工事の種別や発注機関(民間含む)には制限なしとされていますが、近畿地方整備局では、以下のような実務運用を示しています。
<特例監理技術者の配置が認められる要件>
-
発注が分任支出負担行為担当官によるものであること
-
工事の技術的難易度がⅠまたはⅡであること(Ⅲは不可)
-
兼任できる工事は、最大2件まで
-
各工事には専任の監理技術者補佐を置くこと
-
工事の場所が同一または隣接市町村内であること(営繕工事除く)
-
維持工事どうしの兼任は不可(※後述)
-
この「隣接市町村」というルールもポイントで、地図上でA市とB市が隣り合っていれば、2件を兼任することができます。逆に離れた市町村では不可です。
◆分任支出負担行為担当官とは
「支出負担行為担当官」とは、国や地方自治体などの行政機関において、予算に基づいて契約を締結したり、支出を決定したりする権限を持つ職員です。
これに対し、「分任支出負担行為担当官」は、その権限を上位の長(例:庁の長、部長等)から分担して委任された者を指します。
どんな人が該当するのか?
例えば、国土交通省近畿地方整備局のような大規模機関では、
-
局長 → 本省の支出負担行為担当官(トップ)
-
各事務所長(例:大阪国道事務所長、淀川河川事務所長)→ 分任支出負担行為担当官
という形で、現場レベルの事業執行を担う職員に予算執行権限が分任されているのです。
なぜ特例監理技術者制度に関係するの?
近畿地方整備局の「特例監理技術者」の制度運用では、
「分任支出負担行為担当官が発注する工事」であること
が、制度適用の前提条件の一つになっています。
これは、発注の正当性や契約管理の統一性を担保するためです。
要するに「一定の権限を持った者が発注した正式な工事であること」が必要ということです。
わかりやすくまとめると…
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 用語 | 分任支出負担行為担当官 |
| 意味 | 上位官から支出決定権限を分担された職員 |
| 主な役割 | 公共工事の契約・支出の決定 |
| 該当者例 | 地方整備局の各出先事務所の所長など |
| 制度上の関係 | 特例監理技術者制度の適用工事は、原則この者が発注する工事に限る |
◆監理技術者補佐に求められる条件
特例監理技術者制度を使うには、現場に配置される監理技術者補佐が重要な役割を果たします。補佐の要件は以下の通りです:
-
監理技術者と同等の資格を有すること
(例:一級施工管理技士、技術士など/※R3.4.1以降は一級施工管理技士補も可) -
配置される工事に専任で従事すること
-
配置以前に3ヶ月以上の直接的・恒常的な雇用関係があること
(在籍出向や短期契約者ではNG)
つまり、社内の即戦力人材で、しかも国家資格保持者でなければ補佐にはなれません。
専任で従事とは技術者ガイドラインでは次のように記載されています。
専任とは、他の工事現場に係る職務を兼務せず、常時継続的に当該工事現場に係る職務にのみ従事 していること意味するものであり、必ずしも当該工事現場への常駐(現場施工の稼働中、特別の理由 がある場合を除き、常時継続的に当該工事現場に滞在していること)を必要とするものではない。 したがって、専任の主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐は、技術研鑽のための研修、講習、 試験等への参加、休暇の取得、その他の合理的な理由で短期間工事現場を離れることについては、適 切な施工ができる体制を確保する(例えば、必要な資格を有する代理の技術者を配置する、工事の品 質確保等に支障の無い範囲において、連絡を取りうる体制及び必要に応じて現場に戻りうる体制を確 保する等)とともに、その体制について、元請の主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐の場合 は発注者、下請の主任技術者の場合は元請又は下請の了解を得ていることを前提として、差し支えな い。
◆維持工事との兼任に注意
この制度では、「維持工事どうし」の兼任は認められていません。
※維持工事とは
緊急時対応や24時間体制の巡回など、社会機能の維持に不可欠な工事を指します。例えば道路や河川の維持補修、災害対応業務などが該当します。
このような工事は突発対応が多く、現場に専念できないと支障が出るため、制度上でも兼任が制限されています。
◆実際の配置に必要な書類とは?
兼任を希望する場合、受注者は以下の書類を発注者に提出し、判断を仰ぐ必要があります:
-
工事場所が隣接していることを示す資料(地図等)
-
監理技術者補佐の資格証等
-
補佐と事業者の雇用関係を証する資料(社会保険加入証明など)
-
監理技術者と補佐との連絡体制、業務分担表
特例監理技術者制度の利用は、コリンズ(COLLINS)への登録も必須です。
◆特例監理技術者に求められる責務とは?
兼任できるとはいえ、特例監理技術者は従前と同じく以下の業務責任を負います:
-
施工計画の作成
-
工程・品質・安全の技術的管理
-
作業員に対する技術的指導・監督
-
主要な会議・立会・巡回の実施
-
補佐との連絡体制の整備
要するに、現場に“いない”からといって責任を免れるわけではなく、上位技術者としての重責はそのままです。
◆まとめ:人材不足の打開策としての制度活用
建設業界では技術者不足が続く中、今回の特例制度は中小事業者にとって大きな福音といえます。とはいえ、
-
監理技術者補佐の人選
-
工事地域の制約
-
書類提出・体制構築
など、実務面での対応力が求められる制度でもあります。
「人を増やさずに、現場をまわす」ための制度として、しっかり活用していきたいところです。
----------------------------------------------------------------------
建設業許可手続きセンター
住所 : 兵庫県神戸市中央区北長狭通4-3-8 N.Rビル 5階
電話番号 : 078-332-3911
兵庫でガイドラインを守って対応
----------------------------------------------------------------------