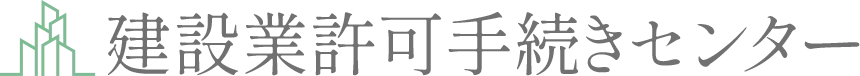兵庫県で2以上の県民局管内の公共工事に参加する裏ワザ
2025/10/11
兵庫県の工事入札の応募条件にその管内に建設業の主たる営業所を構えていること、という条件が付与されていることは少なくありません。そのため、従たる営業所を県内に設けていても、従たる営業所のある地域の工事には参加できないのが原則です。当事務所では兵庫県に対し回答を得ましたので、本記事では、その裏ワザについて記事にしていきます。
目次
建設業と許可の決まり

建設業者は許可を持たないと営業はできない
建設業許可は、建設工事を請け負う事業者にとって不可欠な制度です。許可取得のためには、経営業務の管理責任者や専任技術者の配置、資金要件など、建設業法で定められた要件を満たす必要があります。例えば、500万円以上の工事や特定の業種を行う場合には必ず許可が必要となるため、事前の確認が重要です。
申請の流れとしては、まず要件の確認・証明書類の準備から始め、兵庫県の建設業課へ許可申請書を提出します。その後、行政による審査を経て、問題なければ許可証が交付されます。許可取得後も、定期的な更新や変更手続きが必要となるため、継続的な管理も欠かせません。

許可を持たない営業所での営業はできない
許可を受けた建設業者は、その許可を受けた営業所でしか建設業にかかる営業(見積もり、入札、締結契約の実務的な行為を含む)はできません。、「許可を受けた業種については軽微な建設工事のみを請け負う場合 であっても、届出をしている営業所以外においては当該業種について営業することはできない。」と許可事務ガイドラインにあるように、許可を持たない営業所が500万円未満の軽微な工事であっても契約してはいけない点に注意。

建設業許可申請時に押さえるべき注意点
2か所以上の営業所において営業活動を行う場合は、その営業所が県境をまたいで2以上の府県にある場合には大臣許可を、一つの県内にある場合は知事許可で従たる営業所の登録をする必要があります。
また、直接営業行為をしなくても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う場合は「営業所」に該当するので注意が必要です。
兵庫県における入札案件の状況

県民局制を引いている。
兵庫県においては、県下を神戸、阪神南、阪神北、東播磨、北播磨、中播磨、西播磨、但馬、丹波、淡路の10県民局に分割しています。このうち建設業に関しては中播磨と西播磨は中播磨に集約されています。
一方、発注案件は10の各県民局それぞれでされています。

各県民局の管内に本店があることの要件が多い
そのうえで地域ごとの受注機会の公平性を保つ目的があると思われますが、県民局の発注に付与されている条件を確認すると、「○○県民局の管内に建設業の主たる営業所が存在すること」を応札できる業者に課していることがあります。
例えば東播磨県民局の発注工事には東播磨管内に本店がある業者でないと応札参加の権利がないということになります。
このため、例えば神戸市西区に本社がある会社は、すぐ近くの明石市内の工事には応札できず、1時間近く移動にかかる神戸市東灘区内の工事に参加可能といったようなことがあります。

市町村も地元優先
兵庫県の県民局ごとはもちろん、例えば神戸市と明石市の場合、神戸市に本店がある会社は明石市に入札参加希望を出してもなかなか応札させてもらえません。明石市に本店がある会社が神戸市内の工事に参加しようとしても同じです。市町村の場合は地方税を納めてくれる地元業者を優先するというのは理解できます。ただし、そうであれば、支店でも地元在住の労働者を多く雇ってくれているなら、逆転してもよいと思う部分もありますが、現状はそのようにはならないことが多いです。
同一資本の会社が同一商号を使用することのリスク

類似商号の審査が緩くなった現在
旧商法では、「同一市町村における同一商号の使用禁止」という規定がありましたが、平成18年に施行された会社法には引き継がれませんでした。
これを類似商号の調査が不要になったと言っている専門家がおられますが、間違いです。
現在も不正競争防止法(二条1項1号)と会社法(8条1項)により、他人の営業上の利益を侵害するおそれのある、周知・著名な商号と類似した商号の使用が禁止されています。
旧商法時代の「事前規制」から、作っても良いけれどトラブルになったら自分らで解決してよという「事後救済」に変わっただけなのです。

現在も残る類似商号の禁止
不正競争防止法と類似商号の関係
著名表示冒用行為も禁止:他人の著名な商号と同一・類似の商号を使用する「著名表示冒用行為」も禁止対象となります。
損害賠償・差止請求の可能性:これらの行為により営業上の利益を侵害された場合、侵害者は差止請求や損害賠償請求を行うことができます。
目的は営業上の利益の保護:他人の商号と類似した商号の使用は、自己の営業と混同させる「混同惹起行為」として、不正競争防止法によって禁止されています。
会社法との関係
不正目的の類似商号の使用禁止:会社法第8条は、「不正の目的」をもって、他の会社と誤認されるおそれのある名称・商号を使用することを禁じています。
事後的保護の強化:新会社法施行により、商業登記上は「同一・類似の商号」であっても登記されるようになりましたが、これは商号使用の自由化ではなく、事後的に民事裁判などで商号保護が図られる形に変わりました。

同一商号を使用することにリスクはないのか?
上記に書いたように現在では、類似商号についての規制が緩くなったため、同一商号を複数の会社で使用することは可能となりました。しかし、会社法第8条2項 前項の規定(何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない)に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある会社は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。さらに、不正競争防止法2条では他の商号と同一や類似の商号を使用し「人の商品又は営業と混同を生じさせる行為(1号)」、不正の利益を得る目的で「同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し、若しくは保有し、又はそのドメイン名を使用する行為(19号)」は、不正競争として規制されています。
経営事項審査上の懸念点

悪意を持った業者に利用されないか?
公共工事に参加するには建設業者は経営事項審査の受審をする必要があります。
経営事項審査においては各種の書類を提出しますが、同一商号の場合はその判別が困難になります。
例えば今までは技術者の常勤性の確認資料として健康保険証の提示が求められましたが、同一商号の別会社があるということを審査官がわかってなければ、申請者が勘違いして別会社のものを持参した場合見落とされてしまう可能性があります。
同様に、雇用保険の申告書、領収証、標準報酬決定通知書、領収証、上乗せ労災、建設機械自主検査、車検証なども。

もしも見落とされた場合は発覚しない
建設業に関する届出関連書類は閲覧対象でしたが、近年の個人情報の保護意識の高まりにともない、現在では個人情報関連資料は閲覧対象外となっており、閲覧できる情報はかなり制限されています。
経営事項審査は原則、原本を審査官が確認し、審査を行います。原本なので預かったりコピーを提出することはなく、一日に複数業者の審査をおこなうことが多いです。そのため、スムーズに審査を進めようと、審査官もある程度確認箇所は絞っています。普通は同一資本で同一商号の会社があるとは考えていないので、社名を確認するだけで、住所や、整理記号、登録番号などまで確認している審査官は少ないのが実態です。
そして、見落とされてしまえば、発覚することもないため、悪意を持った申請者が出る可能性は否定できません。
同一商号を使用することに関しての兵庫県の見解

兵庫県は問題なしとの見解
同一商号を使用して複数の会社で許可をとり、経営事項審査の受審をしてそれぞれの本店所在地の県民局に入札参加登録をしていることについての兵庫県の見解を令和7年9月に質問書を提出し、10月2日に回答をいただきましたので、公開いたします。

提出の質問主意書
兵庫県知事許可を受けた建設業者として、以下の二法人が存在する。
兵庫県知事許可第400000号
株式会社○○○○店(法人番号 7140001000000)
代表取締役 ○○ 〇
兵庫県知事許可第100000号
株式会社○○○○店(法人番号 7140001000001)
代表取締役 ○○ 〇
両社は登記上別法人であるにもかかわらず、同一商号「株式会社○○○○店」を用いている。さらに、自社ホームページにおいては「○○本社」「○○本社」と併記し、あたかも単一の法人で複数本店を有するかのような表記を行っている。
この状況は、発注者や他の入札参加業者に対して両社を一体の事業体と誤認させるおそれがあり、公平な競争環境を損なう懸念がある。

質問主意書論点
会社法第8条(不正目的による商号使用の禁止)
不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある商号を使用することは禁じられている。両社の態様は、誤認惹起行為に該当する可能性がある。
不正競争防止法第2条(混同惹起行為の禁止)
他人の営業と混同を生じさせる行為は不正競争にあたり、また同一若しくは類似のドメイン使用による混同惹起行為も規制対象である。本件は混同を助長し、不正競争に該当する余地がある。
公共工事の入札制度と独占禁止法
公正取引委員会の見解によれば、行政機関が条例等で「地元業者優先」や「本店所在地要件」を課すこと自体は独占禁止法上問題とならない。兵庫県も県民局単位で「本店要件」を設けているが、本件二法人はその仕組みを潜脱して複数地域で「本店業者」として応札可能となり、制度趣旨を害している。
建設業法第7条第3項
法人又はその役員が請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがある場合、許可は与えられないとされている。形式上別法人であっても、実質同一主体が許可制度を濫用しているとすれば、同条に抵触する疑いがある。

質問事項
同一代表取締役が率いる二法人が、同一商号「株式会社○○○○店」を用いることは、会社法第8条及び不正競争防止法の趣旨に照らし適切と考えるか。
両法人がそれぞれ入札参加資格を保持し、複数の県民局区域で「本店業者」として応札可能となることは、県が採用している「地元業者優先」の運用基準に反しないか。
実質的に一体と評価され得る二法人に対し、兵庫県として入札制度の公平性確保の観点から調査・指導等を行う考えはあるか。
本件が建設業法第7条第3項に規定する「不正又は不誠実な行為をするおそれがある者」に該当する可能性について、兵庫県はどのように解するか。

兵庫県の回答(兵庫県土木部契約管理課長)
(1)当課は会社法及び不正競争防止法を所管していないため、回答を差し控えます。
(2)それぞれが、建設業許可、有効な経営事項審査の総合評定通知書を有している別法人であり、各法人に対し入札参加資格審査をを行い、不備がなければ入札参加資格者名簿に登載します。
そのうえで、各法人が資格要件を満たす入札に参加することは可能です。
なお、当該二法人は同一代表者であることから、それぞれから資本関係及び人的関係に関する誓約書の提出を受け、関係会社としての取り扱いをしています。
関係会社は、資本関係又は人的関係がある者同士の同一入札への参加を制限する運用基準に基づき、同一入札に参加することはできません。
(3)上記(2)の理由により、調査・指導を行う予定はありません。
(4)同一代表取締役、同一商号のみをもって、建設業法第7条第3項に違反するものと判断することはありません。
兵庫県で違う県民局の入札工事に参加する裏ワザまとめ

地元業者以外は応札できない発注がある
現在は地元業者優先が進み、公募の条件にはよるが、神戸市内の工事は神戸市内の業者を優先するため例えば明石市の業者は応札できない。たとえ明石市の業者が神戸市内に支店を持ったとしても、それは準市内業者として市内業者とは違う扱いとなることが多い。
つまり、建設業法上の主たる営業所がどこにあるかが影響することが多い。

別会社であれば応札できる。
そのため、他地域の工事の入札に参加するためには、支店では弱いため、別会社を作って応札条件を整えるのが一般的です。
しかし、その場合は会社名や代表者も変えることが多いと思われます。その場合は作業服やヘルメット、営業車や、重機に記載する社名なども違うため、全くの別会社として運用されることになります。
そんな中、同一名称で動いている会社があるとの情報がありましたので、その是非を兵庫県に確認したところ、今回問題ないとの回答があったということです。

別会社を同一商号とする注意事項まとめ
兵庫県の建設課長の文章による回答ですので、兵庫県の最終回答としては、「問題ない」との答えです。
現在の入札制度の発注形態からすれば、地元優先により、本店の所在地だけで入札に参加できることが多くなっています。その意味では、支店を作り、その地域の公共工事に参加することは難しいため、別会社にすることでそれぞれの入札に参加が可能になります。さらに、同一商号とすることで、同じ会社がいろんな市町村の入札を落札していると勘違いしてくれます。
ただ、正当なメリットが少なく、リスクと手間が煩雑になるにもかかわらず、同一商号を使うことを選択する会社については、第三者を混同させようとする悪意を感じます。ので、当事務所としてはお勧めはしません。
ちなみに、近畿地方整備局の見解としては、他法令に触れるリスクがあるので、同一商号はやめておくのが無難であるとの回答もいただいておりますので、念のため。