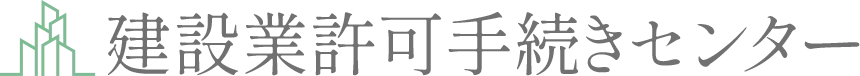兵庫県の建設業者に関する処分基準のポイント
2025/08/02
建設業法には処分や罰則が定められていますが、建設業許可は許可権者が、県知事や、整備局長とされていることから、それぞれの許可権者の権限が独立してあるため、微妙に違いがあります。兵庫県においては建設業者に対する処分基準があるためそちらを参考にポイント解説していきます。
目次
兵庫県の建設業者処分基準を徹底解説 ~不正行為とリスク管理の最前線~

処分基準策定の背景と趣旨
兵庫県が令和4年に示した「建設業者等の不正行為等に対する監督処分基準」は、建設業の健全な発展を図るための重要な指針である。建設業は、公共工事から民間工事まで広く社会基盤整備を担うが、談合や贈賄、虚偽申請、一括下請負、主任技術者の不設置など、さまざまな不正が発覚することも少なくない。こうした事案は県民の信頼を失墜させ、発注者や下請業者に多大な損害を与える可能性があるため、兵庫県は不正行為に対する統一的かつ明確な処分基準を設けた。
この処分基準は、建設業法の理念――すなわち「建設工事の適正な施工確保」「発注者保護」「建設業の健全な発達の促進」――を踏まえ、不正行為への厳正な対応と予防の両立を狙う。対象は許可業者だけでなく、無許可で建設業を営む者(いわゆる無許可業者)も含まれる点に特徴がある。特に公共工事における不正は社会的影響が大きく、重い処分が課される傾向にある。

監督処分の基本理念と範囲
処分基準の総則には、処分の運用にあたり「地域や業種を限定せず」実施することが基本と明記されている。ただし営業停止を行う際、明確に特定工事の部門だけで不正が発生した場合は、その部門に応じた処分を行う例外もある。また請負契約に関連する不正の場合、公共工事と民間工事とで処分の適用範囲を分けることも可能とされる。
監督処分は以下の種類に分類される。
- 指示処分:改善命令に近く、軽微な違反や是正可能な不正行為への対応。
- 営業停止処分:一定期間建設業の営業活動を停止させる厳しい措置。
- 許可取消処分:建設業許可そのものを失わせる最終段階の処分。
さらに基準では、他法令違反に基づく処分もカバーする。たとえば談合事件での刑事判決確定後や独占禁止法の課徴金命令確定後には、刑の確定を待って営業停止処分を行うことが原則だが、社会的影響が大きい場合は逮捕段階で勧告や準備措置を行う余地もある。

不正行為の類型と処分の重さ
兵庫県の基準は、不正行為を大きく類型化し、それぞれに処分の重さを定めている。代表的なものは次の通りである。
- 談合・贈賄等(刑法違反や独占禁止法違反)
代表権ある役員が刑に処せられれば営業停止1年、代表権のない役員や使用人なら120日以上の営業停止と厳格な対応がされる。
- 虚偽申請
完成工事高の水増しによる経営事項審査結果の不正利用では30日以上、さらに監査受審に関わる虚偽があれば45日以上の営業停止。
- 一括下請負違反
建設業法22条違反は15日以上の営業停止が基本。
- 主任技術者・監理技術者の不設置等
建設業法26条違反(技術者未配置や資格不備)は営業停止対象。
処分の重さは、故意・重過失か否か、違反の態様や規模、社会的影響度で増減される。また、複数の不正行為が重なった場合は基準期間を合算し、さらに必要に応じて2/3倍の加重を行うルールも明記されている。

処分の内容と活用の実態
処分基準の特徴的な部分として、不正行為が複合する場合や、過去に処分を受けた業者が再び違反した場合の「加重ルール」がある。
- 複合違反:複数の不正行為が異なる処分事由に該当すれば、それぞれの営業停止期間を合算。さらに、一方の不正が他方の結果として行われた場合は「重い方の処分の2/3倍を加重」。
- 再違反:営業停止処分を受けた業者が3年以内に同種の不正を再び行えば加重処分が課される。
この仕組みは「処分逃れ」や「繰り返し違反」を防ぐ抑止力を持つ。特に主任技術者未配置など、軽視されがちな義務違反も繰り返せば営業停止に発展するため注意が必要だ。

勧告・指示処分と改善義務
基準は営業停止や取消だけでなく、勧告や指示処分といった是正措置も重視する。
例えば、贈賄容疑で役員が逮捕された場合、営業停止まで時間がかかると見込まれるときは、まず社内体制の整備を求める勧告が行われる。また、指示処分後に従わなければ営業停止へと移行する仕組みもある。
これは「即処罰」よりも「改善機会」を与える柔軟な設計だが、従わなければより厳しい処分につながる。

許可取消しに至るケース
処分の最終段階が許可取消だ。兵庫県基準でも「情状が特に重い場合」や「営業停止処分に違反した場合」に許可取消と明記されている。
たとえば、営業停止命令中に入札や契約を行った、重大な贈賄事件を繰り返したなどの場合は、県知事は建設業法29条を根拠に許可を取り消す。
許可取消は業者にとって「営業権の喪失」を意味し、再許可には5年間の欠格期間がある(建設業法8条2号)。したがって、取消は事実上の事業停止を意味する極めて重い処分である。
1章 処分基準策定の背景と趣旨

第1節 建設業の社会的責任と規律の必要性
建設業は公共工事を通じて道路、橋梁、上下水道など社会基盤を形成し、県民生活の安全や利便性を支える不可欠な産業である。しかし、請負契約を基礎とする業態ゆえに、過去から談合や贈賄といった不正行為、あるいは形式的な契約書類の不備、技術者の不適正配置といったコンプライアンス違反が繰り返されてきた歴史もある。こうした行為は公共事業に対する信頼を大きく損ない、発注者や住民の負担増、さらには工事品質や安全性の低下を招くおそれがある。兵庫県は、これらの不正に毅然と対応するため、統一的な監督処分の基準策定が不可欠であると認識し、処分基準を公表している。直近では令和4年に改正をしている。

第2節 処分基準策定の目的
今回の処分基準の最大の目的は、建設業者による不正行為を抑止し、再発を防ぐことにある。基準は「建設業者等の行為が県民の信頼を損なうことのないよう、知事が行う処分の方針を明確化する」ことを掲げ、処分の恣意性を排し、透明性と公平性を確保することを狙いとしている。さらに、業界全体に法令遵守の意識を浸透させ、建設業の健全な発展を促進することも重要な狙いである。単なるペナルティの羅列ではなく、企業に自浄作用を促し、適法・誠実な経営姿勢を根付かせるための「行動規範」として機能させることが意図されている。

第3節 基準が対象とする不正行為と処分の種類
処分基準は、建設業許可を受けた業者(許可業者)だけでなく、無許可で営業する業者(無許可業者)も含めた「建設業者等」を対象としている。対象となる不正行為は、談合・贈賄などの刑法犯、独占禁止法違反、虚偽申請や一括下請負、主任技術者の未配置といった建設業法違反まで多岐にわたる。処分の種類は大きく分けて、①営業停止処分、②指示処分、③許可取消しの3段階であり、行為の内容・影響・情状に応じて選択される。また、勧告や改善命令など、処分に至らない「警告的措置」も柔軟に行われる。

第4節 建設業法との密接な連動性
この処分基準は、建設業法第28条の監督処分条項を基礎としている。同条は、不正行為や違反があった場合に都道府県知事や国土交通大臣が営業停止や許可取消を命じる権限を定めており、兵庫県の基準はその具体的な適用方針を明文化したものだ。これにより、県の判断基準が事業者や関係者にとって明確になり、処分の予見可能性が高まった。さらに、談合事件や重大事故のように刑法・独禁法など他法令違反が絡む場合にも、基準は適用され、建設業者に対する包括的な法令遵守の枠組みを形成している。
第2章 監督処分の基本理念と範囲

第1節 監督処分の位置づけと役割
兵庫県の処分基準における「監督処分」は、建設業法第28条に基づく行政措置であり、建設業者の法令違反や不正行為に対して、業務改善や取引停止を命じるものだ。目的は単なる制裁ではなく、建設業界全体の健全性を守る「予防的・是正的」機能を果たす点にある。不正行為を放置すれば、工事品質の低下や事故、さらには公共事業への信頼失墜につながる。処分基準は、こうした事態を未然に防ぎ、業界に対して強いメッセージを発する重要な役割を担っている。

第2節 処分の種類と適用範囲
監督処分には、大きく分けて営業停止処分・指示処分・許可取消の3種類がある。営業停止は一定期間、請負契約の締結や入札参加を禁止するもので、業務への直接的な影響が大きい。指示処分は比較的軽度な措置で、違反是正の指導や改善命令を中心とする。そして最も重い処分が許可取消で、建設業法上の営業資格を失う。この3段階は、違反の内容・影響・悪質性に応じて使い分けられ、軽微な違反には指導、重大な不正には厳罰という「適正処分の原則」が徹底されている。

第3節 地域・業種の限定と処分の対象範囲
兵庫県の処分基準では、監督処分は基本的に地域を限定せず行うと定められている。つまり、県内外を問わず建設業者の行為が処分対象となりうる。また、業種についても原則は限定しないが、営業停止処分を行う場合に「特定の工種(例:建築一式、土木一式など)だけで違反が発生した」ことが明らかな場合には、その工種に関連する業務に限定する措置も認められている。ただし、細かく分割した処分は行わず、関連する業種は一括処分とする運用が取られる。

第4節 処分発動のタイミングと勧告制度
処分の発動時期は「違反事実の確定」が基本である。他法令違反については、刑の確定や課徴金納付命令が確定した時点で処分が行われるのが原則だが、違反事実が明白な場合には、確定を待たずに処分可能とされている。さらに社会的影響の大きい事件(談合・贈賄による逮捕など)では、いきなり営業停止に入るのではなく、まず「勧告」を発し、社内コンプライアンス体制の整備を求める段階的措置も導入されている。この柔軟性が、兵庫県基準の特色の一つである。
第3章 許可業者に対する監督処分の基準

第1節 許可業者処分の基本的考え方
兵庫県の処分基準では、建設業法第28条に基づき、許可を受けた建設業者(以下「許可業者」)が行った不正行為や違反行為に対する監督処分の基本的な考え方が明記されている。大原則は、「故意または重過失による行為には営業停止処分、その他の事由による場合は指示処分」を行うというものだ。さらに、悪質な事案や営業停止処分違反など、極めて重い事態には許可取消しまで踏み込むことがある。

第2節 営業停止処分の位置づけ
営業停止処分は、請負契約や入札、見積もりなど建設業者の事業活動の中心的な部分を一定期間制限する極めて強い措置である。談合、贈賄、虚偽申請、一括下請負など、建設業法の重大な違反や刑法犯が対象となり、期間は15日~1年以上と幅広い。特に公共工事に絡む違反の場合、県民への影響が大きいため、厳しい判断が下される。

第3節 指示処分の役割と対象行為
指示処分は、営業停止処分より軽い措置であり、違反是正のための具体的な指導・命令を中心とする。建設業法第11条(変更届)、第19条(契約約款関連)、第40条(標識掲示)、40条の3(帳簿の備え付け)違反など、比較的軽度だが放置できない違反行為に適用される。指示処分を受けた業者が命令に従わない場合、再び違反すれば営業停止処分に格上げされることもある。

第4節 許可取消処分への移行基準
営業停止や指示処分を経ても改善が見られない場合、または談合・贈賄のように企業ぐるみの重大不正行為が認定された場合、兵庫県は建設業法第29条に基づき許可取消処分を行う。許可取消は、事業者としての建設業資格を失わせる最も重い処分であり、事実上の業務廃止を意味する。県の処分基準は、取消しに至る判断基準も明文化し、極めて悪質な事案に限定しつつも、毅然と対応する姿勢を示している。
第4章 指示処分の内容と活用の実態

第1節 指示処分の基本的な性格
指示処分は、兵庫県の処分基準において「監督処分の中では比較的軽度の措置」と位置付けられている。営業停止のように業務を直接的に止めるのではなく、違反状態の是正や再発防止を目的に、行政が業者に対して具体的な改善命令や指導を行うものだ。対象となるのは、建設業法や関連法令違反のうち、社会的影響が比較的小さく、ただちに営業を止めるほどではないが、放置すれば重大化するおそれのある事案である。

第2節 指示処分が適用される代表的な違反例
兵庫県基準が示す代表的な指示処分事由には、次のような行為が含まれる。
- 建設業法第11条違反(営業所名称や所在地の変更を届け出ない)
- 第19条違反(契約約款の不備や未使用)
- 第40条・第40条の3違反(標識掲示義務や帳簿備付義務の違反)
- その他、法定の書類整備義務違反や軽度な契約違反
これらの行為は、企業の法令遵守体制の不備を示すシグナルであり、行政はまず指示処分で改善を求め、従わなければより重い営業停止に進む。

第3節 勧告との違いと運用上の位置づけ
指示処分と似た概念に「勧告」があるが、両者は異なる。勧告は法的拘束力のない「要請」であり、指示処分は建設業法第28条に基づく正式な行政処分である。兵庫県は、談合や贈賄事件など重大な事案でも、営業停止や取消処分に至る前にまず勧告を発することがあるが、改善が見られなければ指示処分に移行する。つまり指示処分は、勧告と営業停止の「中間段階」として機能しており、実務上は違反是正のための重要な手段である。

第4節 指示処分を受けた際の義務と影響
指示処分を受けた業者は、行政から示された具体的な改善命令(例:標識を掲示せよ、帳簿を整備せよ、技術者を配置せよ)に従う義務がある。指示内容を放置すれば「不履行」とみなされ、営業停止処分に格上げされる場合がある。営業停止ほどの直接的な経済的打撃はないものの、発注者や取引先への信用失墜、社内の監査強化など、間接的な影響は大きい。事実上、企業のコンプライアンス体制を改善させる「強制力のある教育措置」として作用する。
第5章 許可取消処分の仕組みと実務

第1節 許可取消処分とは何か
許可取消処分は、兵庫県の処分基準において最も重い行政処分であり、建設業者が建設業法に基づく営業許可そのものを失うことを意味する。営業停止や指示処分が「是正」を目的とするのに対し、許可取消は「資格喪失」という究極の措置だ。これは、業務継続が著しく不適切と判断された業者に対して下される、建設業界からの事実上の退場命令でもある。

第2節 取消処分の法的根拠と兵庫県基準
建設業法第29条は、許可取消の根拠条文であり、特定の重大違反行為があった場合、都道府県知事や国土交通大臣は許可を取り消さなければならないと規定する。兵庫県の処分基準もこれを踏まえ、取消処分の判断基準を明確化している。特に、営業停止処分に違反した場合や、企業ぐるみの談合・贈賄、重大な安全事故、暴力団関与など、建設業を営む資格が根底から失われる行為をした業者が対象となる。

第3節 許可取消処分の典型事例
兵庫県基準が示す取消処分の典型例には、次のような行為が含まれる。
- 営業停止命令に従わずに業務を継続
- 野合・贈賄事件で複数回有罪判決を受けた
- 暴力団関与が発覚した法人
- 重大な虚偽申請(架空の完成工事高、偽装経営事項審査など)を繰り返した
これらは「改善命令をしても改善が見られない」「違反が構造的かつ悪質」といった特徴を持ち、建設業法の根幹を揺るがす行為と判断される。

第4節 取消処分の手続きと実務運用
許可取消処分は最も重い処分であるため、行政手続法に基づく厳格な手続きを経て行われる。
- 違反事実の確認(談合判決確定、暴力団関与証拠など)
- 聴聞や弁明の機会の付与
- 最終的な処分決定と通知
という流れで進められる。兵庫県は、取消し前に営業停止や指示処分など段階的措置を取るケースが多いが、暴力団関与や重大犯罪などの場合は、段階を踏まずに直ちに取消処分を行うこともある。
第6章 具体的な処分事由と日数の目安

第1節 処分日数の算定方針と基本原則
兵庫県処分基準は、違反行為ごとに処分の重さを明示し、営業停止の日数や指示処分の適用基準を細かく定めている。原則は「行為の悪質性」「社会的影響」「違反の態様(故意か過失か)」に応じて処分を加重・減軽する仕組みである。これにより、同じ違反でも情状を踏まえて日数が上下することが可能で、運用の柔軟性を担保しつつも透明性が確保されている。

第2節 談合・贈賄など刑法犯に関する日数目安
刑法犯の中でも特に談合や贈賄は重く扱われ、代表権のある役員が刑に処せられた場合、営業停止1年が基本とされる。代表権のない役員や政令使用人が刑に処せられた場合でも120日以上の営業停止。さらに従業員などそれ以外の関係者の場合でも60日以上の営業停止が科される。また、独占禁止法違反による排除措置命令や課徴金納付命令が確定した場合も、30日以上の営業停止と定められている。

第3節 請負契約に関する不誠実行為の処分目安
請負契約に関して社会通念上誠実性を欠く行為、例えば入札書類や競争参加資格資料への虚偽記載は15日以上の営業停止。特に完成工事高の水増しなど、経営事項審査の虚偽申請は30日以上、監査受審状況の虚偽申告まで加わると45日以上に引き上げられる。このように「単なる記載ミス」ではなく、意図的な虚偽申請には厳しい処分が下される。

第4節 一括下請負・主任技術者未配置等の処分目安
建設業法第22条に違反する一括下請負は15日以上の営業停止が基本。ただし元請側の契約不履行など酌量情状があれば減軽もあり得る。また、主任技術者・監理技術者の不配置(資格を満たさない者を置く場合を含む)は同様に15日以上の営業停止とされ、特に現場安全に直結するため厳格な運用がなされている。
第7章 勧告・指示処分と改善義務

第1節 勧告・指示処分の位置づけ
兵庫県処分基準では、建設業者の法令違反に対してすぐに営業停止処分を下すのではなく、まず勧告や指示処分によって改善を促すという段階的な運用が定められている。
- 勧告…法的拘束力はないが、違反是正や体制改善を求める「行政からの強い要請」(19条の5著しく短い工期の禁止)
- 指示処分…建設業法第28条に基づき発せられる正式な行政処分で、改善義務が法的に課される(建設業法11条、19条、40条、40条の3など)
この二段階があることで、兵庫県は企業に「自ら正す機会」を与えつつ、改善しない場合はより厳しい措置(営業停止・許可取消)へ移行する仕組みを取っている。

第2節 勧告が行われるケース
勧告は、違反行為が判明したものの、直ちに営業停止処分を行うまでに至らない場合や、改善の余地が大きい場合に発せられる。典型例は、談合や贈賄の容疑で役員が逮捕されたが、判決確定前の段階で社会的影響が大きいと判断されるケースだ。また、現場で安全性に重大な懸念がある行為、標識未掲示など軽度だが改善が急がれる違反にも勧告が用いられる。勧告は「改善の呼びかけ」だが、実務上は強い圧力を伴い、企業は迅速な対応を迫られる。

第3節 指示処分の適用と内容
指示処分は、勧告よりも重い段階に位置し、建設業法第28条に基づく正式な行政処分である。行政が定めた改善策(例:標識の掲示、帳簿整備、主任技術者の配置など)を必ず履行しなければならない法的義務が発生する。指示処分は営業停止よりは軽いが、企業の信用への影響は大きい。発注者や金融機関は指示処分の有無を注視しており、コンプライアンス不備の「警告灯」としての意味を持つ。

第4節 改善義務と履行確認
勧告・指示処分を受けた業者は、行政から示された改善措置を期限内に実行し、その報告を行う義務がある。兵庫県は、改善の履行状況を確認するために点検や調査を行うと明記しており、虚偽報告や改善不履行が判明すれば営業停止処分への格上げや許可取消しにつながる。つまり、勧告・指示処分は「単なる紙上の指導」ではなく、行政が継続的に監視・確認する実効性ある制度となっている。