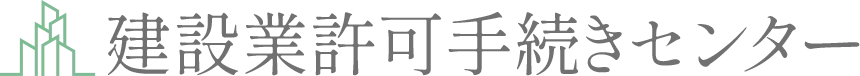建設業法19条「請負契約の内容」について
2025/07/12
建設業法第19条を読み解く – 請負契約の基本ルール
🔹【条文全文】
(建設工事の請負契約の内容)
第十九条 建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
一 工事内容
二 請負代金の額
三 工事着手の時期及び工事完成の時期
四 工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容
五 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
六 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
七 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
八 価格等(物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第二条に規定する価格等をいう。)の変動又は変更に基づく工事内容の変更又は請負代金の額の変更及びその額の算定方法に関する定め
九 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
十 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
十一 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
十二 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
十三 工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
十四 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
十五 契約に関する紛争の解決方法
十六 その他国土交通省令で定める事項
2 請負契約の当事者は、請負契約の内容で前項に掲げる事項に該当するものを変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
3 建設工事の請負契約の当事者は、前二項の規定による措置に代えて、政令で定めるところにより、当該契約の相手方の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて、当該各項の規定による措置に準ずるものとして国土交通省令で定めるものを講ずることができる。この場合において、当該国土交通省令で定める措置を講じた者は、当該各項の規定による措置を講じたものとみなす。
目次
建設業法19条は契約書について定めている

なぜ「書面」で明らかにする義務があるのか?
建設工事は金額も大きく、工期も長く、関係者も多いという特徴があります。そのため、「言った」「言わない」のトラブルを避けるため、必ず契約書(書面)を交わすことを法律で義務付けています。
特に建設業法19条は、建設業者の契約行為における基本的な“約束の形”を規定する条文であり、民法上の契約自由原則の例外的な制限ともいえます。

「19条で定める事項」とは?
全部で16項目があげられていますが、具体的には以下が挙げられます。
工事内容(施工場所、構造、規模など)
請負代金の額および支払時期・方法
工期(着工日、完成日)
受渡し・検査の方法
瑕疵担保責任(保証)に関する取り決め
違約金や損害賠償の扱い
つまり、契約に必要な最低限の項目を法律で規定しているのです。

いつまでに契約書の締結が必要?
条文では「あらかじめ」という表現は使われていませんが、契約書ですので、工事が始まるまでに「あらかじめ」契約書を交わすべきでしょう。
これは工事着工前までに書面を作成し、両者が確認することを意味します。
実務上、「まず現場を動かして、契約書は後日」…というケースがありますが、これは建設業法違反になる可能性が高く、指導・監督処分の対象にもなり得ます。

契約書を交わさなかった場合のペナルティは?
建設業法19条違反そのものには罰則はありませんが、契約書は建設業法第40条の3(帳簿の備え付け)に定める、帳簿の対象となります。
帳簿の添付書類として「契約書もしくはその写しまたは当該契約に関する電磁的記録」があります。
帳簿の備え付け違反には建設業法55条により10万円以下の過料が課されることもあり、軽視できない義務です。
契約書に記載すべき事項

第19条って何を言っているの?
建設業法第19条は、建設工事の契約をするときに、
「契約書に16個の項目を書きなさい」と命じています。
つまり、
✅ 契約前に ✅ 書面を作って ✅ 両者がサインして交換する
これが法律のルール。
でも「何を書けばいいの?」というのがポイントです。

第1項 工事内容(施工場所・構造・規模・工法など)
最初に求められるのは、工事の内容を具体的に書面化することです。
「施工場所」「構造」「規模」「工法」など、いわば工事の設計図的な核心情報を明記する義務があります。
👉 解説ポイント:
「東京都港区○○2丁目1番地の建売住宅3棟新築工事」など、特定できる表記が必要。
規模は延べ床面積や階数、構造は木造・RC造などを明確に。
あいまいな表記(例:「一部改修工事」など)は紛争のもと。

第2項 請負代金額(内訳も含む)
契約金額は工事契約の根幹です。単に「総額いくら」だけでなく、工事種別ごとの内訳や税抜き・税込み表示など、明確な金額設定が求められます。
👉 解説ポイント:
途中変更や追加工事が生じやすい分野のため、初期契約時に基準金額と精算方法も盛り込むべき。

第3項 工期(着工日および完成日)
工期は「開始日(着工日)」と「終了日(完成日)」を特定して記載する必要があります。
👉 解説ポイント:
「天候不順などの場合の延長」「発注者の事情による遅延」についても触れるとトラブル回避になる。
⚠️ 工事を始めてから契約書を作るのはNGです。
建設業法違反になるだけでなく、後から代金請求するときに不利になります。

第6項 「設計変更・工期変更の扱い」 – “追加工事”の定番トラブル回避策
追加工事や仕様変更があったらどうするのか?
工期を延ばす?金額はどう精算する?
これを契約書に書かないと、
「追加工事だから払ってほしい」「そんな話は聞いてない」で揉めます。

第7項「天災・不可抗力」 – 誰が“リスク”を負うか
台風・地震・豪雨など、工事が止まるケースがあります。
✅ その時の工期延長ルール
✅ 損害の負担(資材流出、足場倒壊の片付け費用など)
ここを決めておかないと、災害後の現場でお金の話ばかりになります。

第8項 「価格変動(スライド条項)」 – 物価高騰時代の命綱
資材や燃料の価格が大きく変動したときの契約処理をどうするか、契約書に書き込むことを求めています。近年の「ウッドショック」による木材高騰、鉄鋼やアスファルトの値上がり、さらには輸送コストの増加など、建設工事の現場は常に価格変動の波にさらされています。こうした変化に備え、「価格スライド条項」を契約に入れておくことが不可欠です。
たとえば、契約締結後に資材価格が一定割合以上上昇した場合に請負代金を見直す、あるいは価格が下がったときには差額を調整する、といったルールを事前に明示しておけば、施工者も発注者も不測の損失を避けることができます。公共工事では国や自治体の「スライド条項運用基準」に従うのが一般的ですが、民間工事でもこうした条項がないと、価格変動によるコスト負担をめぐり激しい対立が起こりがちです。
現場と会社を守るリスクマネジメントの要であり、近年の資材価格の高騰局面ではますます重要性を増しています。

第9項 「第三者への損害賠償」 – 近隣トラブル対策
建設業法第19条九号は、工事によって第三者に損害が生じた場合の賠償責任の所在を契約書に明記することを求めています。例えば足場の倒壊で隣家を破損、工事中の飛散物で通行人が負傷、といった事故が典型例です。これを曖昧にすると、元請・下請・施主の間で責任の押し付け合いが起こり、長期化することもあります。事前に「誰が、どの範囲まで責任を負うか」を明確化し、必要に応じて保険加入も契約書で定めておくことが重要です。

第12項 「完成後の代金支払い」 – “最終金”の支払い条件
工事が完成した後の請負代金の支払時期と方法を契約書に明記する義務を定めています。工事完了後、施主と施工者の間で「いつ支払うか」「どのように支払うか」が曖昧だと、支払い遅延や未払いトラブルが起きやすくなります。そこで、検査や引渡し完了から何日以内に振込か現金で支払うのかなど、具体的な条件を契約時に決めておくことが重要です。これにより、工事後の資金回収が円滑になり、双方の信頼関係を守ることにつながります。
✅ 「引渡し後7日以内に支払う」
✅ 「検査完了後に支払う」
支払条件が不明確だと、完成後に“支払い遅延”トラブルが起きやすい。

第13項 「瑕疵担保責任(保証)」 – “欠陥工事”への備え
工事の目的物が契約どおりの品質でない場合の責任(瑕疵担保責任)や、その履行のための保証措置を契約書に記載する義務を定めています。雨漏りや構造不良など欠陥が見つかった際、誰が修繕し、どの範囲まで補償するのかを事前に取り決めていないと、重大な紛争に発展します。
- 雨漏り、床の傾き、構造不良…。
こうした欠陥(瑕疵)に対してどんな保証をするのかを決めます。
住宅工事なら10年保証(住宅瑕疵担保履行法)との整合性も重要です。保証期間・修補方法・保険加入の有無を明確化し、施主と施工者双方の安心を確保します。

第14項 「違約金・遅延損害金」 – “もしもの時”のペナルティ
工事の履行が遅れたり、契約違反があった場合の遅延利息や違約金などの損害金について契約書に記載する義務を定めています。工期遅延や代金未払いなどが起きたとき、事前に取り決めがなければ法定利率に基づく請求になり、双方に不満が残りやすくなります。そこで違約金の金額や遅延損害金の利率、算定方法を明確化しておけば、万一のトラブルでも迅速に処理でき、余計な争いを防ぐことができます。
✅ 遅延損害金の利率
✅ 違約金の金額
これを決めないと、裁判で決まった“法定利率”が適用されてしまいます。

第15項 「紛争解決方法」 – トラブルが起きた時の“出口”
契約に関する紛争が起きたとき、どのように解決するかを契約書に明記する義務を定めています。たとえば「○○地方裁判所を専属管轄とする」や、「まずは調停や仲裁(ADR)を利用する」といった方法を事前に合意しておけば、揉め事が生じたときに解決の手順がスムーズです。これを決めていないと、裁判所選びや解決手段でさらに対立が生まれ、問題が長期化しかねません。契約段階で“出口”を決めておくことが、信頼関係を守る鍵です。
✅ 裁判か仲裁か?
✅ 管轄はどこの裁判所?
最近はADR(裁判外紛争解決)を条文に入れるケースも増えています。
契約書の形態について

契約書は二部作成し、署名又は記名押印して交付
建設業法第19条第2項は、契約書面の作成と交付についての基本的なルールを定めています。ここでは、「契約書は両当事者が署名又は記名押印した上で、それぞれが1通ずつ受け取らなければならない」と規定されています。
この規定の目的は、契約内容を明確にし、証拠性を確保することにあります。契約書を一方だけが持つ、あるいは口頭合意だけで済ませてしまうと、後々「言った・言わない」の争いが起きたときに証明が困難です。また、署名や押印を求めることで、契約内容を正確に確認したうえで合意したことを担保する狙いがあります。
現在は押印廃止の流れもありますが、建設業法では条文上で記名押印が定められている点に注意してください。

契約書に貼るべき印紙税について
建設工事の契約書を作成する際には、印紙税が必要となります。これは、課税文書(印紙税法別表第一)に該当する文書を作成した場合に課される税金で、工事請負契約書はその中の「第2号文書」=請負に関する契約書として扱われます。
✅ 印紙税が必要な理由
工事請負契約書は、一定金額以上の請負契約の証拠となる文書として課税対象になります。契約金額に応じて税額が定められており、契約書には所定額の印紙を貼り、消印(割印)をする義務があります。
✅ 課税額の目安(代表的な区分)
| 契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
| 100万円超〜200万円以下 | 400円 | 200円 |
| 200万円超~300万円以下 | 1,000円 | 500円 |
| 300万円超~500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
| 500万円超~1千万円以下 | 1万円 | 5千円 |
| 1千万円超~5千万円以下 | 2万円 | 1万円 |
| 5千万円超~1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
| 1億円超~5億円以下 | 10万円 | 6万円 |
| 5億円超~10億円以下 | 20万円 | 16万円 |
| 10億円超~50億円以下 | 40万円 | 32万円 |
| 50億円超 | 60万円 | 48万円 |
👉(令和7年7月現在)
✅ 注意すべきポイント
契約金額が1万円未満の場合は印紙税は不要です。
2通作成する契約書のうち、それぞれが原本として扱われる場合は両方に印紙が必要ですが、1通を「正本」、もう1通を「写し(写しに○印)」として作成すれば、写し側には印紙不要です。
電子契約書は印紙税が課税されない(紙の文書に限り課税)。
✅ まとめ
建設工事契約書には、契約金額に応じた印紙税を貼る必要があります。貼り忘れると、税務調査で本来の3倍の過怠税(過怠税)を徴収されることもあります。
正しい金額の印紙を貼り、必ず消印することが重要です。
👉 電子契約化すれば印紙税の負担を減らせるため、近年は公共工事や大手ゼネコンでも電子契約への移行が進んでいます。

基本契約書と注文書+請書の取り扱い
基本契約書を結んで、個々の契約時には注文書と請書のやり取りだけで済ませるといったことも多いと思いますが、その場合は印紙税についてどう判断されるのでしょうか?
基本契約書には金額の記載がないので非課税?と思いがちですが、継続的取引のキホンとなる契約書となるため印紙税がかかります。
さらにそれぞれの注文書、請書にも印紙税がかかりますので注意が必要です。
建設業法19条第3項に定める電子契約とは

電子契約って、書面と同じ効力があるの?
これまで建設業法19条は、「契約書を紙で作成し、署名または記名押印して交付すること」を大原則としてきました。
しかしデジタル化の流れを受け、電子契約制度が19条3項で明確に認められています。
つまり――
✅ 紙じゃなくてもいい
✅ ただし、国交省が定めた基準を守ること
この2つの条件がそろえば、電子契約は紙と同じ効力を持つ契約書になるのです。

国交省が定める“電子契約の基準”とは?
電子契約を使うには、単にPDFをメールで送るだけではNGです。
「国土交通大臣が定める基準」に適合している必要があります。
その基準の主なポイントは――
✅ 当事者双方の同意を確認できる仕組み(合意プロセスの証跡が残る)
✅ 内容が改ざんされていないことを証明できる技術(タイムスタンプや電子署名)
✅ 契約締結後も内容を確実に保存・閲覧できるシステム(クラウド上での長期保存など)
つまり、「信頼できる電子署名+タイムスタンプ」が基本条件です。

建設業法19条3項「電子契約」3つの要件(国交省基準)
① 契約当事者双方の「同意」を確認できること
電子契約は、両者が確実に合意したことを証明できる仕組みが必要です。
メールでPDFを送って「これでOKですね」と返事をもらっただけでは✕。
国交省が求めるのは、誰が・いつ・どの端末から契約に合意したかが明確に記録されること。
実務上は電子署名や認証機能(ログイン認証、ワンタイムパスコード)を用いたクラウド型サービス(クラウドサイン・GMOサインなど)で要件を満たします。
② 内容が「改ざんされていない」ことを証明できること
紙の契約書には署名や押印があり、それが改ざん防止の役割を果たしています。
電子契約も同じように、契約締結後に内容が一字一句変えられていないことを証明する必要があります。
電子署名+タイムスタンプの組み合わせが最も代表的な手段です。
電子署名:契約当事者が確かに署名したことを示すデジタル証明
タイムスタンプ:署名時点で内容が確定していたことを第三者が保証
これにより、仮にPDFが書き換えられても、証明書で即座に不一致が判明します。
③ 長期間の「真正な保存・閲覧」ができること
建設業の契約書は完成後も最低5年間(公共工事なら原則10年)保存が義務付けられています(建設業法40条の3)。
電子契約も締結後に削除されたり閲覧不能になってはいけない。
国交省は、契約締結後も容易に閲覧でき、真正性が担保されたまま長期間保存できるシステムを求めています。
実務では、電子契約サービスのクラウド上での長期保管機能を使うか、ダウンロードして社内サーバーや外部メディアに保管します。

3要件を満たさないケースのNG例
PDFをメール添付で送信し「OK」の返信をもらっただけ → ✅同意の証跡が不十分 ✕
契約締結後にファイルが書き換え可能な状態(パスワードなし)で放置 → ✅改ざん防止が不十分 ✕
クラウドサービスを解約して契約書データが消滅 → ✅保存要件を満たさず ✕