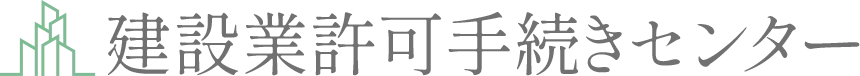建設業許可の欠格要件について
2025/06/28
建設業許可制度は、工事の適正な施工と公共の安全を確保するために、国土交通省および各都道府県により厳格に管理されています。この制度において「欠格要件」は、建設業者としての社会的信用や法令遵守の姿勢を担保するための重要なフィルターです。建設業法第8条および第8条の2に定められたこれらの要件に該当する者は、たとえ他の要件を満たしていても許可を受けることができません。また、許可取得後に該当すれば、更新が拒否され、許可の取消し処分が下されることもあります。許可取得を目指す企業や個人にとっては、まず自社や役員が欠格事由に該当していないかを確認することが、申請準備の第一歩となります。
目次
建設業法上の欠格要件とは~基本の8項目を理解する

欠格要件はなぜ定められているのか?
建設業法において欠格要件が定められているのは、建設業が公共性・安全性の高い業務であるため、一定の資質・適格性を備えた者に限って許可を与える必要があるからです。建設業者は公共工事や民間の重要施設の施工を担うため、反社会的勢力との関係や法令違反歴がある者、信用性を欠く者に許可を与えることは、社会的にも大きなリスクを生みます。欠格要件はこうした者を制度的に排除し、工事の適正な施工、安全確保、発注者の保護を図るとともに、建設業界全体の信頼性と健全性を維持する目的で設けられているのです。これは許可の取得時のみならず、許可の維持期間中にも適用され、常に適格な事業者のみが建設業に携われるよう法的な枠組みが設計されています。

欠格要件は大きく分けて次の8項目
- 成年被後見人・被保佐人である場合
- 破産して復権を得ていない場合
- 禁固以上の刑に処されて5年を経過していない場合(執行猶予中含む)
- 建設業法等に違反し処分を受けてから一定期間が経過していない場合
- 許可取消処分を受けた法人の役員で、処分前60日以内に在籍していた者(処分から5年以内)
- 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者
- 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者(その法定代理人が欠格要件に該当する場合)
- 申請者(法人・個人)の役員・使用人が上記のいずれかに該当する場合
これらは法人・個人を問わず等しく適用され、たとえば役員1人が欠格要件に該当するだけで法人全体が許可を受けられないケースもあります。

成年被後見人・被保佐人である場合
建設業の許可を受けるには、経営や契約の判断を適切に行えることが求められます。そのため、判断能力に制限のある「成年被後見人」または「被保佐人」は欠格要件に該当します。成年被後見人とは、精神上の障害などにより常に判断能力を欠く状態にあり、家庭裁判所によって後見開始の審判を受けた者です。また、被保佐人は判断能力が著しく不十分な者であり、保佐人の援助を必要とする立場です。これらの者が建設業の許可を受けると、適正な契約締結や現場管理が困難となり、工事発注者や社会に不測の損害を与えるおそれがあるため、法律上排除されています。法人の場合は、代表者だけでなく、取締役や監査役などの役員すべてが対象となるため、役員交代時にも慎重な確認が必要です。成年後見制度に基づく審判が取り消された場合は、欠格状態も解除されます。

破産して復権を得ていない場合
破産手続開始の決定を受けた者は、裁判所により法的な支払い能力を欠いたと判断された者であり、一定期間、財産管理や契約行為などに制限が課されます。こうした状態のままでは、建設業者としての信用性や取引適格性を欠くとされ、建設業の許可を取得することはできません。ただし、破産者であっても「復権」を得れば欠格状態は解消されます。復権とは、破産手続きの終了(免責確定や取り下げ等)により、法的な制限が解除されることを指します。建設業法では、許可を受ける者本人だけでなく、法人の役員、個人事業主の使用人についても破産による欠格の有無が審査対象になります。そのため、新たに役員を就任させる場合や事業再建を行う際には、当該人物が復権済みであるかの確認と、必要に応じた登記事項証明書・復権証明書の取得が重要となります。しゅ

禁固以上の刑に処されて5年を経過していない場合(執行猶予中含む)
建設業法では、法令違反や反社会的行為により禁錮以上の刑に処された者が、刑の執行を終えるか、執行を受けることがなくなってから5年を経過していない場合、欠格要件に該当します。禁錮刑とは、懲役と同様に自由を拘束される刑罰であり、重大な犯罪に対して科されるものです。また、執行猶予中の者も欠格とされますが、猶予期間が満了した場合は、そこから5年が経過して初めて欠格状態が解除されるわけでなく、初めから刑自体がなかったものとされるので、執行猶予満了とともに欠格要件には該当しなくなります。
建設業は公共性が高く、安全や信頼性が求められる業種であるため、一定期間は社会的信用の回復を求める趣旨でこの規定が設けられています。なお、刑の執行免除や特別恩赦を受けた場合も、実際にその効力が発生してから5年を経過する必要があります。法人の場合、役員のうち1人でも該当すれば許可は下りませんので、在籍役員の経歴確認が不可欠です。

建設業法等に違反し処分を受けてから一定期間が経過していない場合
建設業法や関連法令に違反して許可取消処分を受けた者は、その処分の日から5年間は原則として建設業の許可を受けることができません。営業禁止・停止処分中のものは処分が明けるまで同様です。これは過去に重大な法令違反を犯した者に対して、一定期間の再許可制限を設けることで、建設業界の健全性と発注者の保護を図る趣旨に基づいています。対象となる法令は建設業法のほか、建築士法・宅建業法・労働安全衛生法・刑法など広範にわたり、たとえば無許可営業、虚偽申請、談合、不正な下請契約などの行為が含まれます。また、処分を受けた本人だけでなく、その法人の役員で処分前60日以内に在籍していた者にも適用される場合があります。

許可取消処分を受けた法人の役員で、処分前60日以内に在籍していた者(処分から5年以内)
建設業許可が取り消された法人において、取消処分の直前60日以内に役員として在籍していた者は、当該処分日から5年間、新たに建設業の許可を受けることができません。これは、名義貸しや不正行為を行った法人からの形式的な逃げ道を防ぐための制度です。仮に処分直前に辞任したとしても、その者が経営に関与していた事実があれば、連帯責任を問われることになります。この規定は、実質的な経営責任を果たす立場にあった役員に対する再発防止措置であり、他法人での再チャレンジや名義上の再登用を制限するものです。なお、この60日という期間は在籍していたかどうかが客観的に判断できる範囲とされ、登記簿や議事録等の記録で確認されます。許可取得後に不正行為が発覚した場合、連座的に他の法人や関係役員にも波及する可能性があるため、役員構成の確認は極めて重要です。

暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者
建設業法では、暴力団員である者、または暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者を欠格要件として明確に排除しています。これは、建設業界が長らく反社会的勢力の資金源とされてきた歴史的背景を踏まえ、業界の健全化を強く推進するためのものです。暴力団員でなくなったとされても、警察等における情報からその関係性が完全に解消されたと判断されなければ欠格は継続するとされるため、事実上の監視期間といえます。また、暴力団と密接な関係にあると認められる者(資金提供、便宜供与など)も、実務上は欠格と見なされることがあります。法人の場合、役員や支店長、営業所長が該当すれば、法人全体が許可を受けられません。反社会的勢力の排除は行政庁における審査の重点項目であり、警察庁との情報連携もなされているため、過去の関係が疑われる場合は特に慎重な対応が必要です。

営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者(その法定代理人が欠格要件に該当する場合)
建設業許可の申請者が未成年である場合、その者が営業に関し成年者と同一の能力を有していないとき、かつ、その法定代理人が欠格要件に該当する場合には、許可を受けることができません。これは、未成年者が単独で契約や経営判断を行うには法的制約があり、実質的に代理人の意思に左右されるため、代理人の適格性も同時に問われることになります。たとえば、法人代表を親権者にして子を名義代表とする場合、その親が過去に建設業法違反などで処分歴があると、子も欠格扱いとなります。逆に、未成年者であっても結婚しているなどの事情により「成年擬制」を受けていれば、欠格とはなりません。実務上は未成年者が許可申請をするケースは少数ですが、家族経営などで法定代理人が関与する場合には、この規定によって思わぬ不許可となるケースがあるため、十分な確認が必要です。

申請者(法人・個人)の役員・使用人が上記のいずれかに該当する場合
建設業の欠格要件は、申請者本人だけでなく、その法人の「役員」や「使用人」にも及びます。ここでいう使用人とは、支店長や営業所長など、実質的に営業活動に関与する責任ある立場の者を指します。つまり、代表者本人が欠格要件に該当していなくても、役員の一人や支店長が該当すれば、それだけで法人全体の許可が認められないという厳格な制度です。これは、建設業が公共性・信頼性の高い事業であり、企業全体のガバナンスや法令遵守が問われるためです。特に注意が必要なのは、役員を新たに選任する際や、営業所を新設して責任者を任命する際です。これらの人物の過去の経歴や法的地位を十分に調査し、欠格に該当しないことを確認する必要があります。誓約書や身分証、登記簿などで形式的に確認するだけでなく、実質的な関与の有無を慎重に判断することが、許可取得と維持の鍵となります。
刑罰歴と欠格~「5年間の経過」がカギとなる判断

刑罰歴がある者がすべて直ちに欠格に該当するわけではありません。建設業法においては、「禁錮以上の刑に処され、執行を終えた日または執行を受けなくなった日から5年を経過していない者」が欠格となります。また、建設業法違反による処分歴がある場合には、その処分から5年が経過していなければ再度の許可申請はできません。注意すべきは、「暴力団排除」や「法令違反に対する厳罰化」の流れが近年強まっており、刑罰の種類や事案の内容によっては許可が極めて困難になるという点です。申請にあたっては、過去の処分や前科の内容・時期を正確に確認し、行政書士等の専門家と相談することが安全です。

「禁錮以上の刑に処された者」の起算日と経過日
【建設業法第8条第7号】
「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者」
起算日とは?
刑の執行を「終えた日」または「執行を受けることがなくなった日」が起算日となります。
状況起算日
実刑判決で服役 → 出所出所日(刑の執行を終えた日)
恩赦等により執行免除→恩赦発令日などで執行を免除された日
※欠格要件に該当するかどうかの起算日は「判決日」ではなく確定日です。

執行猶予、大赦、特赦、の場合
執行猶予付き判決の場合の解釈
刑が「言い渡された」時点で「禁錮以上の刑に処せられた者」に該当する
執行猶予中は「執行が終わっていない」ため、欠格状態にある
執行猶予期間が満了すれば、刑の執行は受けなかったとみなされ、「欠格ではなくなる」
🔍 法的根拠(刑法第27条)
執行猶予期間を経過したときは、その刑の言渡しは効力を失う
ただし、それまでは刑が「言い渡されている」状態であるため、欠格要件の該当性は消えないのが建設業法の実務運用です。
✅ 実務での整理
| 状況 | 欠格該当 | 建設業許可申請すると |
| 執行猶予付き判決直後(猶予中) | ✅ 該当 | ❌ 不許可 |
| 執行猶予満了後(例えば3年) | ❌ 不該当 | ✅ 申請可能(満了日翌日から) |
| 実刑 → 服役 → 出所 | ✅ 該当(出所後5年間) | ❌ 不許可(出所後5年経過で解除) |
大赦、特赦についても刑の執行の免除ではなく、有罪の言い渡しの効力そのものが消滅するので申請可能となります。
役員や使用人も対象~「誰が該当するとダメなのか」を知る

欠格要件は、申請者本人だけでなく、法人の場合は役員(取締役・監査役等)すべてに、個人事業の場合は使用人(支店長・営業所長等)にも適用されます。特に見落とされがちなのが「使用人の欠格」です。例えば、ある営業所の所長に任命した人物が暴力団と関係していたり、過去に建設業法違反で処分を受けていたりすると、それだけで法人全体の許可が拒否される可能性があります。新たに役員を就任させたり、営業所を増設する際には、その人物が欠格事由に該当しないかを必ずチェックすることが、法的リスクを未然に防ぐ鍵となります。
暴力団排除と欠格要件~「密接な関係者」でもNG

建設業界においては暴力団排除が強く推進されており、建設業法第8条では「暴力団員である者、または暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者」や、「暴力団と密接な関係を有する者」も欠格とされています。ここで注意すべきは、「密接な関係」の解釈が広く、暴力団との金銭的関係や便宜供与の事実があるだけでも該当する可能性がある点です。また、暴力団排除条例に基づく通報により、自治体や警察との協議が行われるケースもあります。暴力団との関与は過去のものであっても、現在の許可に深刻な影響を与えることを理解しておくべきです。

暴力団関係の判断基準
【施行令第3条の3】において「密接な関係を有する」とされる例:
- 資金提供・便宜供与を行ったことがある
- 暴力団の威力を利用して不正な利益を得ようとした
- 暴力団の運営や活動に協力していた
- 実質的な関係が継続していると認められる場合
👉 単に形式上の関係がないという主張だけでは足りず、実質的な接点があったか否かが重視されます。

なぜ暴力団排除が重視されるのか
- 建設業界は資金流通が大きく、下請・孫請を通じて暴力団資金が流入するリスクがある
- 公共事業の適正な執行を確保するため、発注者(国・自治体)側でも暴力団排除条項を徹底
- 国交省・警察庁・都道府県が連携して情報照会・通報体制を整備している
欠格要件に該当したらどうなる?~回復の方法と許可維持の心得

欠格要件に一度該当してしまうと、原則としてその状態が解消されるまで新たな許可を取得することはできません。ただし、刑罰歴であれば5年の経過をもって欠格が消滅しますし、破産であれば復権が得られれば再度申請可能となります。一方で、暴力団との関係や虚偽申請による許可取消しの場合には、より厳しく審査され、再許可が事実上困難になる場合もあります。許可取得後も、定款変更・役員交代・支店開設などの際には、常に関係者が欠格に該当していないかを確認する体制が必要です。欠格要件を「取得時だけの条件」と誤解せず、日常的な法令遵守と情報管理の中で、許可の維持を意識することが、安定経営の第一歩です。

欠格に該当した場合の新規許可取得は?
欠格要件に該当した状態では、原則として新規の建設業許可申請をしても許可はされません。たとえば、禁錮以上の刑に処せられた場合は、執行終了または免除から5年間は許可申請できませんし、しても不許可になります。建設業法違反により許可取消処分を受けた法人の役員であれば、処分から5年以内は再申請が認められません。これらの欠格要件は「時間の経過」によって自然に回復するものが多く、制度的な救済措置や例外は基本的に存在しません。したがって、許可取得を目指す者は、まず欠格事由の有無とその解消時期を正確に把握し、適切な時期に申請を行う必要があります。

欠格状態の回復時期と証明書類
欠格状態からの回復は、原則として法令に定められた期間の経過により自動的に成立します。たとえば、破産の場合は復権の決定を得た時点、禁錮刑であれば執行終了から5年が経過した時点、執行猶予の場合は執行猶予が満了した時点が回復の目安となります。申請実務においては口頭の確認はもちろんですが、書類による裏付けの準備をしておかなければ実はまだ欠格期間だったとなると不許可になりますので、確認作業は慎重に行う必要があります。

既存許可者が途中で欠格に該当した場合は?
すでに建設業許可を受けている者が、その後に欠格要件に該当した場合、建設業法第29条第1項第1号の規定により、許可は当然に取消されます。 これは行政庁の裁量によるものではなく、法定義務です。たとえば、代表者が暴力団関係者となったり、役員が禁錮以上の刑を受けた場合などには、欠格事実が確認され次第、聴聞等を経たうえで必ず許可が取り消されます。このため、許可取得後も、役員の選任や営業所長の配置に際しては、欠格事由に該当しないことを厳密に確認し続けることが不可欠です。