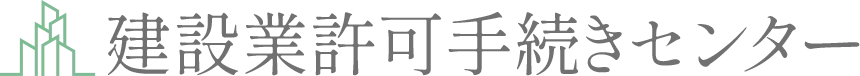建設業許可取得を行政書士に依頼するメリットとは
2025/05/24
建設業を営むには、一定規模以上の工事を請け負う場合、建設業法に基づく「建設業許可」が必要となります。個人事業主から中小企業、さらに法人化を検討している業者にとって、この許可は信用力や営業活動の土台となる重要なライセンスです。しかし、その取得には煩雑な手続きと厳格な審査が伴い、自力での申請は大きな負担となりがちです。
ここでは、許可取得の基礎とあわせて、行政書士に依頼することで得られる具体的なメリットについて詳しく解説します。
目次
建設業許可取得の基本

建設業許可の基礎知識を理解する
建設業許可とは、元請・下請を問わず、一定額以上の建設工事を請け負うために必要な国家資格です。具体的には、以下のいずれかに該当する場合、許可が必要です。
建築一式工事:1件の請負代金が1,500万円(税込)以上(木造住宅の新築で延床面積150㎡超も対象)
その他の工事:1件の請負代金が500万円(税込)以上
建設業許可には「一般建設業」と「特定建設業」があり、元請業者として下請に5,000万円(建築一式は8,000万円)(税込)以上の工事を発注する場合は特定建設業の許可が必要です。
また、業種ごとに29業種(建築・土木・管・電気・解体など)に分かれており、それぞれについて許可が必要です。

許可取得に必要な初期条件を確認する
建設業許可を取得するには、以下の5つの要件を満たす必要があります。
経営業務の管理責任者がいること(経管要件)
一定期間、建設業の経営経験がある役員等の配置が必要。
営業所技術者がいること(技術者要件)
業種ごとに、国家資格者や実務経験者が必要。
財産的基礎があること(財務要件)
自己資本500万円以上(新規の場合)、直近の決算書による確認。
欠格事由に該当しないこと
過去に処分歴があるなど一定の事由に該当する場合は不許可。
営業所の実態があること
専用スペース、固定電話、標識など営業実態の証明が必要。事務所使用できる建物かどうかも要チェック。
これらの条件は一見単純に見えても、証明方法や書類の準備には煩雑な実務が伴います。特に「経営業務の管理責任者」や「営業所技術者」の実務経験の裏付けには、過去の契約書や請求書、従事証明書などを揃える必要があります。

行政書士に依頼するメリット
1.申請手続きの正確性と迅速化
建設業許可の申請書は、各種書式への記入、必要書類の収集と整理、要件の証明など多くの作業を伴います。行政書士は建設業法や許可基準に精通しており、自治体ごとのローカルルールにも対応可能です。不備のない書類をスピーディーに整えられるため、申請から許可取得までの期間を短縮することができます。
2.複雑な要件判断への対応
「経営業務の管理責任者になれるのか?」「実務経験で技術者要件は満たせるのか?」など、判断が難しいケースは多々あります。行政書士は過去の事例や実務運用に基づき、可能性のあるルートを提案し、証明資料の工夫によって突破口を開くことができます。
特に近年は、要件緩和や運用の柔軟化が進んでいる分、「最新の運用解釈」まで踏まえた適切な判断が求められます。
3.要件を満たすための戦略的サポート
すぐに要件を満たせない場合でも、行政書士は将来的な許可取得に向けて「どのような人材を雇用すればよいか」「法人化すべきか」「どの業種で申請すべきか」など、中長期的な視点でアドバイスが可能です。
また、建設業法以外の関係法令(例:建築士法、電気工事士法など)との整合性も踏まえてアドバイスするため、リスクを回避しながら確実な許可取得が目指せます。

4.提出前のチェックと役所対応の代行
建設業許可は提出先によって受付方法が異なり、「予約制」「事前審査あり」「電子申請・郵送不可」など地域差も大きいです。行政書士は、事前相談・提出代行・補正対応などすべての窓口対応を引き受けるため、申請者の手間とストレスが大幅に軽減されます。
5.許可取得後の変更届・更新にも対応
建設業許可は取得すれば終わりではなく、5年ごとの更新や毎年の決算終了後の報告や役員変更・技術者変更などの随時の「変更届出」が義務付けられています。これを怠ると「営業停止処分」や「許可取消」のリスクがあります。
行政書士に継続して依頼することで、変更管理・更新期限の管理も含めた長期的なサポートが受けられます。
行政書士に任せる価値は?

建設業の「決算変更届」を専門家に依頼する5つのメリット
建設業者は、建設業許可を取得した後も継続的に行政への届出義務が生じることをご存じでしょうか。なかでも毎年必ず提出しなければならないのが、「決算変更届(正式には「事業年度終了報告書」)」です。
この届出は、建設業法第11条に基づく法定義務であり、怠ると重大なペナルティが科されることもあります。提出自体は毎年の定型業務に見えますが、内容にミスがあると経審に影響したり、許可更新に支障が出たりする重大な業務でもあります。
ここでは、決算変更届を毎年、行政書士に費用を払ってでも依頼する理由とそのメリットを、制度の基本とともに詳しく解説します。

決算変更届とは何か
✅ 提出義務と法的根拠
建設業者は、毎年決算が終了した後、4か月以内に以下の書類を提出する義務があります(建設業法第11条2項)。
決算報告書(工事経歴書、直前3年の施工金額一覧表、財務諸表)
株式会社については、事業報告書(一定の規模以上の場合はさらに付属明細表など)
変更届(定款、健康保険の加入状況、令3条の使用人の事項、使用人数数に変更がある場合)
この届出を怠ると、「許可更新不可」「経営事項審査が受けられない」「入札資格停止」などの重大な影響を受けることになります。

自力での作成を避ける理由
決算変更届は「定型書類を出すだけ」と思われがちですが、以下のような実務的ハードルがあります。
① 工事経歴書の整合性確認が必要
元請・下請、公共・民間別、工種別の工事内容を分類し、正確に工事経歴書へ反映させる必要があります。
発注者間違い、受注金額間違い、業種違い、配置できない技術者の配置、その他工事の上げ忘れ、などで建設業法違反を吐露していることも多いので注意。
経審の根拠になりますので、そこの記載に虚偽があれば最悪虚偽申請の疑義を持たれることも・・・
② 財務諸表は建設業独自の様式
一般的な会計ソフトで出力した損益計算書・貸借対照表では不十分です。建設業法に則った「建設業様式」で提出しなければなりません。
また内容も税務署へ提出する税務会計と建設業法で求められている建設業会計では仕分けに違いがあるので、税務署に提出した数字を右から左に写すだけではダメなことにもご注意を。製造原価の人件費や材料費がゼロな場合に合理的な説明はつきますか?
③ 過年度との整合性チェック
過去に提出した決算内容と比較し、売上の推移、資産の変動などに整合性があるかを確認する必要があります。特に会計は連続性があるので、税務調査があった年、昨年度の提出した数字との連動制を反映していますか?
④ 経審・更新への影響
提出内容が次年度の経営事項審査(経審)や許可更新時に反映されるため、軽微なミスが後で大きな損失になることも

行政書士に依頼する5つの具体的メリット
1.ミスのない書類作成で経審・更新に備える
行政書士は、決算変更届の作成に精通しており、建設業特有の勘定科目の読み替えや、工事経歴の分類方法、正しい数値処理に精度高く対応できます。
そのため、経審で高得点を狙う企業や、スムーズな許可更新を目指す場合には必須のサポートとなります。
2.過去データとの整合性を確保してトラブル回避
建設業許可の審査では、「前年と比べて急激に資本が減っている」「工事高が不自然に増減している」など、整合性が取れていない場合に行政から問い合わせや説明要求が来ます。
行政書士に継続依頼することで、過去の提出データとの整合性を管理し、整った資料を毎年提出できる体制を構築できます。
3.決算直後から迅速に対応して期限遵守
提出期限である「決算終了後4か月以内」は意外と短く、会計事務所から決算書が仕上がるのが遅れると、その後の届出作成が間に合わないこともあります。
行政書士であれば、決算書が出来次第、迅速に建設業用に転記・編集して提出体制を整えるため、期限内提出が可能になります。
4.営業所・役員変更・資本金変更なども同時対応
決算変更届は単なる決算内容の届出だけでなく、同時に行う「変更届」の契機にもなります。
- 役員変更(辞任・就任)
- 営業所の住所移転
- 技術者の交代
- 資本金の増減
これらの内容を毎年の届出と一緒に把握・申請できるため、法令遵守と許可の維持を一貫して任せられるのも大きな強みです。
5.経審の加点対策にも貢献
行政書士は決算変更届のデータをもとに、経審の対策も立てていきます。たとえば、
- 経常利益や自己資本比率を高めるには?
- 技術職員をどう配置すべきか?
- 財務構造の改善ポイントは?
など、経審でのW点・Y点を向上させるためのアドバイスをデータに基づいて提供できるのは専門家ならではです。

行政書士への依頼費用の相場
|
内容 |
相場(税込) |
こうべ元町事務所 |
| 決算変更届(1業種・1営業所) | 3万~5万円程度 | 41,800~57,200円※1 |
| 経審とセット依頼 | 7万~10万円程度 | 15万~26万※2 |
| 変更届込みパック | 追加1~2万円程度 | 事項による※3 |
※1※2※3とも 次回決算変更までの1年間の基本的な相談料が無料(月3万円~10万円の顧問契約同等(相談)のサービス)
※2 即効性のある経審対策はもちろん、長期での体質改善など伴走性の高いアドバイス、税理士さんを含めた経審対策打ち合わせ、入札参加資格審査格付け対策、入札参加資格もご依頼いただく場合は期限管理、中間年受付、時期変更などにも対応
※3 複数営業所全ての許可要件の確認、維持に向けた戦略的な人事育成や社内体制構築に向けたアドバイスもお任せください。

自社でやるリスクと比較
| 項目 | 自力提出 | 当事務所へ依頼 |
| 書類の正確性 | 自社での誤記や形式ミスが起きやすい | プロによるチェック済みでミスなし |
| 経審・更新への影響 | マイナス評価の原因になることも | 有利な点数取得に繋がる可能性大 |
| 書類整理の手間 | 工事経歴書・財務書類作成に手間 | 一括して対応可能 |
| 提出期限の管理 | 忘れるとペナルティの可能性 | 年次スケジュール管理も対応 |
| 変更届の見落とし | 不提出はもちろん、提出しても法違反を書類に書いて提出していることも | 必要な届出も網羅的に提案 |
毎年の決算変更届は、建設業者としての信頼と法令遵守の象徴とも言える重要な業務です。これを形式的な書類提出と捉えるか、企業価値を高める一貫業務と考えるかが、将来の成長や入札機会にも大きく影響します。
行政書士に依頼することで、煩雑な作業から解放されるだけでなく、経審対策・許可維持・行政対応までトータルで支援が受けられます。
「費用をかけても依頼する価値がある」――それが建設業許可制度と経審制度を熟知した専門家に任せる真のメリットなのです。
「決算変更届の財務諸表」―ただの転記か、戦略的分析か

はじめに
建設業の許可業者にとって、毎年の「決算変更届(事業年度終了報告)」は法定義務であり、適切な提出が求められます。この届出に含まれる「財務諸表(分析用様式)」は、税務署に提出する決算書(法人税申告書)とは異なり、建設業特有の勘定科目に基づいた独自の様式での提出が必要です。
しかし、現場ではこの「分析用様式」について、単純に税務申告書を転記するだけの形式的処理にとどまっているケースも少なくありません。それでは何が問題なのか?そして、費用をかけてでも建設業に詳しい行政書士に依頼するべき理由とは?
以下で、両者の違いとその意味を明確に比較し、実務的な影響を徹底解説します。

分析用財務諸表とは何か?
「分析用様式」とは、建設業許可の維持・経審の基礎資料として、建設業に特化した書式で作成される財務諸表(貸借対照表、損益計算書、完成工事原価報告書など)です。
特徴として:
勘定科目が建設業用に細分化(例:「完成工事高」「完成工事原価」「未成工事受入金」など)
表示様式が一般の会計書類と異なる
経営事項審査(経審)の評価項目に直結
この「分析用様式」の作成方法一つで、次年度の経審評価点が上下し、入札の可否や等級に影響を及ぼすこともあるため、単なる形式書類と侮ることはできません。

税務申告書を丸写しするだけの処理の実態とリスク
税務会計上の財務諸表(法人税申告書の添付書類)をそのまま転記する方法には、以下のような実務的リスクと損失があります。
🔸建設業独自の勘定科目との不一致
例:売上を「売上高」として記載すると、建設業で必要な「完成工事高」との整合が取れず、経審で無得点扱いされることがある。
🔸粗利益率・自己資本比率などの誤認
完成工事原価・一般管理費などの科目分けが適切にされていないと、経営状況分析(Y点)のスコアが実力以下になる。
🔸未成工事受入金や工事未払金の扱いミス
税務会計では見逃されることがある項目も、建設業では重要な指標(資金繰り・信用力)として審査対象になる。
🔸前年度との整合性不備
誤って処理されたまま提出されると、経審で「信用毀損の恐れ」と判断される可能性あり。
つまり、「ただ出すだけ」の届出は、許可維持という観点ではクリアできても、経審や格付け制度の観点では致命的な損失を招く可能性があるのです。

行政書士に依頼する場合の対応と強み
一方で、建設業実務に熟練した行政書士に依頼すれば、次のような高度な分析と最適化が行われます。
✅ 建設業用の会計ルールに基づいた変換処理
税務ベースの決算書を、建設業様式へ正確に読み替え、完成工事高・原価・粗利益を適切に算出します。
✅ 財務スコアの最適化
・流動比率、自己資本比率、利益率など、Y点に影響する主要指標を意識した調整
・不要な長期借入の見直しや資本構成の是正提案
・企業再編手続きを活用した手法も相談可能
✅ 工事経歴書との数値整合
・完成工事高と工事経歴書の合計金額を正確に一致
・公共・民間・元請・下請別の内訳チェックも対応
・業種の積み上げも視野に入れた工事内訳チェックと戦略的な工事配分
✅ 決算の傾向分析と中期戦略への反映
・赤字決算による将来のリスクに対する改善提案
・「来期までに必要な利益水準」などを逆算提示
・決算到来前に試算表をもってシミュレーションすることで今期末までにどのような経営をすればよいかの相談が可能

価値の比較
|
項目 |
項目税務書類の丸写し(会計事務所・自社処理) |
行政書士による分析・作成 |
| 対応内容 | 申告書の写しをそのまま記入 | 建設業用に変換・調整・最適化 |
| 完成工事高・原価の処理 | 不適切な科目分類になりやすい | 経審・Y点意識の正確分類 |
| 数値整合性 | 工事経歴書・財務にズレが出がち | 突合チェックでリスク排除 |
| 経審スコアへの影響 | 評価ダウンのリスクあり | 得点向上のアドバイス含む |
| 将来への影響 | 点数減、等級ダウン、入札機会減少 | 信用向上、受注チャンス増大 |
決算変更にわずかなプラスで分析を処理してもらえる事務所も少なくないようです。ですが、税理士さんの作成した決算書の中身を読み、建設業財務諸表に組み替えるためには再度の内容確認やそれに伴う手間がかかるのが本当のところです。分析手続きが安い事務所はおそらくですが、内容の精査はできないのではないかと思われます。
変更届を行政書士に依頼するべき理由

~「簡単な手続き」の落とし穴と、許可維持のためのリスク管理~
建設業許可を取得した後、建設業者には「許可を維持するための義務」が多数課されます。その中でも、「変更届出」は代表的な維持義務であり、役員の交代・技術者の変更・商号や本店所在地の変更など、身近で小さな変化でも速やかに届出を行う必要があります。
一見、「事務員でもできる」「形式的な手続きだからコストをかける必要はない」と思われがちですが、この“軽視”が将来の許可取消や経審停止、指名停止など、致命的なトラブルの引き金になりうることはあまり知られていません。
本稿では、「簡単な変更手続きも含め行政書士に依頼すべき」理由と、費用以上の価値がある専門家の関与によるリスク回避効果を、実際の想定トラブルを踏まえて詳しく解説します。

変更届出とは何か?義務と期限の基礎知識
建設業法第11条および同施行規則に基づき、建設業者は「許可申請時に届出た情報に変更があった場合、定められた期間内に変更届出を行う」義務があります。
|
変更内容 |
提出期限 | 備考 |
|
商号又は名称の変更 |
30日以内 | 登記完了後速やかに |
|
本店(営業所)所在地の変更 |
30日以内 | |
|
会社代表者の変更 |
30日以内 | 登記日から起算 |
|
役員の変更 |
30日以内 | 監査役は含まれない |
|
経営業務の管理責任者の変更 |
2週間以内 | 専任性と要件の確認が必須 |
|
営業所技術者の変更 |
2週間以内 | 技術資格・実務経験証明必要 |
| 営業所の代表者の変更 | 2週間以内 | |
| 欠格要件に該当したとき | 2週間以内 | |
|
資本金・出資金の額の変更
|
30日以内 | 財務的基礎との整合が必要 |
| 建設業許可業種の廃業(廃止) | 30日以内 | 一部業種をやめた場合も要届出 |
これらの届出を怠った場合、建設業法第50条に基づく指導・監督処分(注意・指導・勧告・営業停止・許可取消)の対象となる可能性があります。

「簡単だから」と油断して起こる主なトラブル事例
ケース1:役員変更届を出し忘れた → 更新申請が不受理に
会社登記簿ではすでに変更済だったが、変更届を出していなかったため、5年後の建設業許可更新の際に「提出済の役員情報と異なる」と指摘され、再提出を求められた結果、更新期限に間に合わず許可失効に。
ケース2:専任技術者が退職 → 未届のまま数か月経過
技術者が突然退職し、代替者が決まらず届出しなかった結果、「専任技術者がいない状態での営業」と判断され、営業停止命令を受けた。
ケース3:営業所の移転届を怠る → 指名停止
市区町村の指名願と建設業許可情報との記載住所が一致せず、自治体より「信頼性の欠如」と判断され3か月の指名停止処分。

行政書士に依頼することで得られる5つの具体的メリット
① 期限管理と自動通知による漏れ防止
行政書士に依頼していれば、下記のような対応が可能です:
- 届出が必要な法定期限をあらかじめ管理
- 登記情報・人事異動・営業所変更などの情報取得に基づき、自動リマインド
- 手続きのスケジューリング支援と代行
これにより、「忘れていた」「急ぎでできなかった」という事態を防止できます。
② 専任性や資格要件の正確な判断
専任技術者や経営業務の管理責任者など、「ただ名前を届け出れば良い」というものではありません。以下のような法的要件が必要です:
- 実務経験年数(業種別)や資格の有無
- 他の会社や自社の専任性のある業務との兼務禁止(専任性)
- 常勤性の確認(社会保険・住民票等による証明)
行政書士は、こうした要件を正確に理解し、就任可能・不可能を判断し、許可基準に適合する形で届け出書類を調整します。
③ 複数変更の同時対応と整合性の確保
例えば「代表者の交代」「経営業務の管理責任者の交代」「役員変更」が同時に行われた場合、それぞれ別個の届出を要します。このように一人の人が複数の地位にあるような場合、すべての手続きを網羅し、提出漏れが無いようにしなければなりません。営業所の技術者などの移動の時期(3月9月)などは要注意です。
建設業に詳しい行政書士であれば:
- すべての変更を一括して把握・処理
- 書類上の整合性確保(記載内容・証明資料の一致)
- 一連の届出を1回で完結する提案
が可能で、作業負担の削減と法令違反リスクの低減につながります。また、登録電気工事業者登録や産業廃棄物収集運搬業、宅建業や建築士事務所登録などの関連する手続きも網羅して行います。
④ 自治体ごとの提出形式への完全対応
建設業法上の届け出の後、公共工事への参加を希望している場合は各入札参加資格を持っている自治体に入札参加資格の変更届の提出も必要になります。参加自治体により、変更届の様式や添付書類、提出方法(持参・郵送・電子)には差異があります。
提出事項も様々で役員や技術者の就退任も届け出対象の場合もあります。また、近年では電子入札が主流になつているため、入札手続きには電子証明書が必要ですが、入札参加資格の登録情報と電子証明書の内容が同じでないと手続きができない場合などもあります。そんな場合は発注者とよく相談の上、入札参加資格の変更提出時期を調整することが実務上楽なこともあります。そういう意味では入札のなさそうな時期に変更は済ませるなどのアドバイスも。。。
詳しい行政書士はこれらの地域差に完全対応しており、「提出したが受理されなかった」というトラブルを回避できます。
⑤ 許可更新・経審・指名願との一体管理
変更届は単体で完了するものではなく、将来的な許可更新、経営事項審査、自治体の格付け申請(指名願)との整合性が求められます。
行政書士であれば:
「前回届出との不整合」による指摘や不受理を回避
将来的な書類との連動を考慮した届出作成
継続顧問契約による全体的な台帳・履歴の管理
といった対応により、長期的かつ安全な建設業経営のサポートが可能になります。

費用と得られる安心感の比較
|
項目 |
自社対応(事務員) |
行政書士依頼 |
| 書類作成精度 | 高くない | 法令・実務両面から正確 |
| 提出漏れリスク | 中~高(個人の能力による) | 管理体制により低減 |
| 役所とのやりとり | すべて自社対応 | 代行・調整可能 |
| 要件判断 | 不正確になりがち | 要件の適格判断あり |
| 結果責任 | 自社責任(というより事務員個人に負わせる?) | 専門家としての責任が伴う |
| 安心感 | 不安が残る | 継続的に「安心できる管理体制」 |

まとめ:手続きの軽視が許可取消に直結する時代
建設業許可は一度取得すれば終わりではなく、“維持すること”の方がむしろ重要かつ難しいのが現実です。
「簡単だから自社で」という姿勢が、数年後の更新拒否・経審停止・営業停止・信用失墜という形で大きな代償をもたらすこともあります。ましてそれが御社の本業である業務であれば、その失敗で従業員全員が路頭に迷うことにもなりかねません。
自社の大切な事務員さんに、過大な責任を負わせることとなるようなことは避けるべきだと思います。我々行政書士事務所に払う報酬なんて、事務員さんをもう一人雇うことを思えば安いものです。この人手不足人件費高騰の世の中事務員さんにいろんな調べ物やなれない手続きに時間を割かせるよりも行政書士に資料をとっとと渡して自身の本業に専念してもらう方が会社の業務効率としては全然プラスだと思います。
行政書士への依頼は、単なる書類作成代行ではなく、“会社の法的リスクを管理するための外部パートナー”としての投資です。
経営事項審査を行政書士に依頼する理由

~入札で勝つための第一歩は「経審の精度」にあり~
建設業者が公共工事を受注するためには、単に建設業許可を有しているだけでは不十分で、経営事項審査(通称:経審)を受けて客観的な経営評価を取得する必要があります。この経審の結果は、発注機関の格付けや指名選定、入札参加資格の根拠となる極めて重要な指標であり、1点の違いが受注可否を左右することもある極めてシビアな制度です。
しかしながら、その手続きには財務・技術・法令・実績・書類作成など、多角的かつ高度な知識が要求され、誤りが致命傷となるケースも少なくありません。
ここでは、経営事項審査を行政書士に依頼することの具体的なメリットと、依頼しない場合に起こり得るリスクについて、実務目線で詳しく解説します。

経営事項審査とは何か?
経営事項審査は、建設業者の「経営力」「実績」「技術力」「社会性」などを数値化して、公共工事の発注者(国・県・市町村など)が、客観的に評価・格付けするための制度です。
経審で得られる「総合評定値(P点)」が高いほど、格付けが上がり、より高額な工事や有利な地域での入札が可能となります。
審査項目(主な構成)
| 評価項目 | 内容 | 点数への影響 |
| X点 | 完成工事高、自己資本、利益額等(経営規模) | 非常に大きい |
| Y点 | 財務健全性(流動比率、自己資本比率など) | 大きい |
| Z点 | 技術職員の保有状況・工事実績など | 非常に大きい |
| W点 | 社会性(法令順守、表彰、BCP、建機など) |
中程度~ 加点効果あり |
この審査を受けるためには、事前に決算変更届の提出が完了していることが前提であり、自治体によってはさらに指名願との整合性、添付資料の形式指定などの厳格な要求があります。

行政書士に依頼するメリット
① 書類作成の正確性と迅速化
経審では、以下のような膨大な書類が必要です:
- 経営規模等評価申請書
- 総合評定値請求書
- 技術職員名簿・資格証明
- 建設機械保有明細
- 直前3年の工事実績
- 財務諸表(分析用様式)
- 営業所や専任技術者の証明書類
- その他、添付資料・証明書・副本等
これらの書類は、1つでも不備や記載ミスがあると受理されず、審査結果の遅延や申請無効につながります。行政書士に依頼すれば、建設業法と経審運用基準に則った正確な様式で迅速に作成され、スムーズな審査通過が実現します。
② 財務指標の「最適化」による点数向上
Y点に関する財務分析(流動比率・自己資本比率・営業利益率など)は、提出する財務諸表の記載方法によって点数が変動します。
行政書士は以下のような対応でスコアの最適化を図ります:
- 原価と一般管理費の明確な区分整理
- 減価償却や引当金の反映調整
- 決算数値を建設業用様式へ変換
- 赤字決算時の影響を抑える工夫
形式的な記載ではなく、「得点を意識した記載」で申請できることが大きなメリットです。
③ 技術職員や建設機械等の加点管理
Z点・W点では、以下のような加点項目が重要となります:
1級施工管理技士等の配置人数
技術者の専任要件・常勤性の証明
建設機械の保有(台数・種類・稼働状況)
表彰・BCP認定・ISO取得・防災協定 など
行政書士に依頼すれば:
- 各加点要素の正確なカウント・証明資料の準備
- 技術者台帳の整備と有資格者の配置戦略
- 誤認・記載漏れによる加点漏れの防止
を通じて、加点要素の取りこぼしをゼロに近づけることができます。
④ 格付け制度や指名願への戦略的対応
経審の点数は、兵庫県・神戸市などの公共団体における格付け制度と連動しています。特に:
- 「A等級になるためには◯◯点以上」
- 「P点の点数があと何点高ければB等級に上がる」
- 「そのランクには完成工事高が直前3年で◯億以上必要」
といった要件があります。
行政書士に依頼すれば、以下のような「格付け取得を見据えた経審対策」が可能です:
- 目標等級に応じた必要点数の逆算
- 完成工事高の工夫(3年平均/直前年度比較/積上業種の選定)
- 財務・技術職員の補強計画
- 指名願との整合性チェック
これにより、単なる申請業務を超えて、「受注のための戦略支援」として機能します。
⑤ 更新管理と次年度対策まで一貫支援
経審の有効期間は「1年間」であるため、毎年の再申請が必須です。行政書士と継続的に付き合うことで:
- 前年との点数比較・増減要因の分析
- 必要資料の自動リストアップ・案内
- 指名願との同時対応・スケジューリング調整
- 税理士との情報共有による決算連携
が可能となり、会社全体の経審体制を効率的かつ安定的に運用できます。

依頼しなかった場合のよくあるトラブル
|
トラブル事例 |
原因 |
結果 |
|
財務指標が悪化した |
原価と経費の区分誤り | Y点が大幅減点、等級ダウン |
| 技術者の専任性証明不備 | 証明資料が揃っていなかった | 技術職員数が認められず加点消失 |
| 提出期限切れ | 提出忘れ・書類不足 | 経審無効 → 指名停止・等級失効 |
| 工事経歴書と完成工事高が不一致 | 伝票処理の不備 | 補正指導・審査遅延 |
| 格付け制度の点数要件未確認 | 自社の格付要件を把握していなかった | 指名願が通らず不参加 |

まとめ:「高得点=受注へのパスポート」は行政書士が鍵を握る
経営事項審査は、単なる書類提出ではなく、「会社の競争力を数値化する審査制度」です。
昔は各社公共工事に参加するために建設営業の方を雇い入れて役所との接点を作っていましたが、談合、癒着をなくす観点から現在ではほとんどそのような方はおられなくなりました。現在役所と会社をつなぐのは受注現場でのやり取りと、経営事項審査+指名願いになっています。
この制度を正しく理解し、最大限の得点を獲得するには、財務・法務・技術・公共調達のすべてに精通した専門家による支援が不可欠です。
行政書士に依頼することで、得られるのは単なる申請代行ではなく、
- 経審スコア最大化
- 格付け等級の向上
- 入札の勝率向上
- 法令順守と安心経営
といった、経営戦略に直結する“経審の武器化”です。費用以上の価値がある確実な投資と言えるでしょう。
信頼できる行政書士事務所と付き合うことの真のメリット

~建設業許可の維持と発展を支える「継続的な法務パートナー」の力~
建設業の世界では、許可の取得だけでなく、それを「維持」し「活かし」ていくことこそが真の経営課題です。法改正、社員の出入り、組織変更、公共工事への参入など、企業を取り巻く環境は日々変化しており、それに伴って建設業法上の義務や注意点も刻々と変化しています。
こうした中で、信頼できる行政書士事務所と継続的に付き合うことには、単なる「書類代行業務」を超えた戦略的な価値があります。以下では、実務的・経営的な観点からその具体的なメリットを詳述します。

特定要件の欠落を「事後」ではなく「事前」に把握できる
建設業許可や経審では、以下のような「要件の欠落」が命取りになることがあります:
- 経営業務の管理責任者(経管)が退職し、要件を満たす者がいない
- 専任技術者が病気・異動・退職し、配置不能となった
- 特定要件流動比率75%、自己資本4000万以上、欠損金がある場合自己資本の20%未満の財産的基礎を下回っていた
- 法定届出(変更届・決算変更届)の提出漏れ
- 新たに許可業種を追加したいが、資格者が不在
これらは往々にして、「気づいたときには遅かった」という事態を招きます。
信頼できる行政書士事務所は、以下のような対応を定期的に行ってくれます:
- 技術者・経管者のリスト管理と任期のチェック
- 社員構成の変化に応じた「要件充足性」診断
- 財務状況と許可基準との整合性チェック
- 許可期限・経審期限のカレンダー管理・通知
これにより、問題を「発生後に処理」するのではなく、「発生前に予防」する体制が構築できます。

経営業務の管理責任者(経管)育成の戦略的アドバイス
経管要件は、建設業許可の根幹を支える存在であり、「5年以上の建設業経営経験(または補助者経験)」が求められるため、急に用意することができません。
信頼できる行政書士事務所は、こうした経管要件に対し:
- 経管要件を満たしているかどうかの事前診断
- 現状で満たしていないが、将来的に候補となる社員の把握
- 補助者経験として認められるような職務経歴・資料の蓄積方法
- 法人化・役員就任の時期・内容に関するアドバイス
など、中長期的な視点で「経管の育成計画」を支援します。
これは許可の維持のみならず、将来的な事業承継や法人設立、組織拡大にも大きく寄与する視点であり、会社の成長戦略と直結する極めて重要な支援です。

建設業法違反を防ぐ「予防法務」としての機能
建設業法違反には、軽微な書類の不備から重大な営業停止・取消処分まで幅があります。
よくある違反例:
- 許可のない業種での請負(無許可営業)
- 無許可業者への発注
- 専任技術者の他業務兼任(専任性違反)
- 許可業者間名義貸し
- 下請代金の不当な減額・支払遅延
- 建設リサイクル法や労災法の違反
信頼できる行政書士は、日頃からの相談窓口として、こうしたグレーゾーンへの「予防的アドバイス」を提供できます。
たとえば:
- 「この業種で請け負って良いのか?」
- 「こんな仕事をここの会社に発注していいの?」
- 「この人材を技術者にできるか?」
- 「施工体系台帳を作成すべきか?」
- 「下請との契約書はどうすればいいか?」
- 「最近付き合いだした会社から大きな案件の受注がありそうなんだけど工期もあるから確実に入金するために何か打てる手はないかな」
といった日常の疑問に迅速に答えることで、トラブルを未然に防ぎ、法令遵守と信用確保の両立を実現できます。