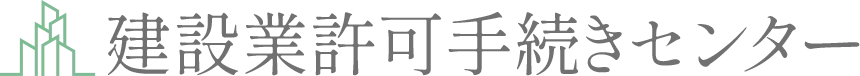建設業許可と行政書士:許可取得を支える専門家の役割とは
2025/05/10
建設業許可とは何か?
以下に、「建設業許可と行政書士の関わり」について、構成で詳しく解説します。
建設業の概要から許可の重要性、行政書士の役割まで網羅的に紹介します。
目次
建設業許可と行政書士

建設業許可とは何か?
建設業とは、住宅や商業施設、インフラなどの「工事」を請け負って行う業種を指します。これらの工事を行うにあたって、一定の金額以上の契約を請け負う場合には、「建設業許可」が必要となります。
建設業法では、次のように定められています。
1件の工事の請負金額が 500万円(税込)以上(建築一式工事は1,500万円ただし、延べ面積150㎡未満の木造建物を除く)の場合
→ 許可が必要
これに該当する工事を無許可で請け負った場合、罰則の対象となるだけでなく、元請業者や発注者からの信頼も失いかねません。したがって、建設業を安定的に営むには、許可取得はほぼ必須といえるでしょう。

建設業許可の種類と構成
建設業許可には、次のような分類があります。
(1)一般建設業と特定建設業
一般建設業:下請に出す金額が1件あたり5,000万円未満(建築一式は8,000万円未満)
特定建設業:上記を超える下請契約を結ぶ可能性がある場合(大規模元請向け)
(2)知事許可と大臣許可
知事許可:1つの都道府県内に営業所がある場合
大臣許可:複数都道府県に営業所がある場合
さらに、29業種に細分化された工事種別(例:土木一式、建築一式、大工、電気、塗装など)ごとに、個別に許可を取得する必要があります。

許可取得のための主な要件
建設業許可を取得するには、形式的な書類提出だけでなく、以下の要件を満たすことが必要です。
(1)経営業務の管理責任体制(いわゆる「経管」)
かつての「経営業務の管理責任者」に代わり、2020年以降は「経営業務を適切に管理できる体制」が必要
建設業の経営経験者や補佐経験者が役員にいることが要件
(2)営業所専任技術者の配置
各営業所ごとに、技術資格や実務経験を有する者を専任技術者として配置
例えば、一級施工管理技士、10年以上の実務経験者など
(3)誠実性と欠格要件の確認
過去に許可取消処分を受けていないか、暴力団関係者ではないかなどの確認
(4)財産的基礎(資本要件)
一般建設業:自己資本500万円以上、または同等の財産的基礎
特定建設業:より厳しい要件(資本金2,000万円以上など)

建設業許可取得の難しさ
上記の要件は形式的なもののように見えて、実務上は非常に厳密な証明書類が必要です。
例えば:
経営経験を証明するには過去の法人登記や確定申告書
技術者の経験には実務経験証明書、工事台帳、裏付け資料としての契約書や注文書+請書など
財産基盤には決算書や残高証明書
これらを「許可行政庁が納得する形で」整える必要があり、知識がないまま手続きを進めると、不許可になるか、再提出を何度も求められることになります。
行政書士を利用するメリット

許可取得の成功率が上がる
建設業許可は、「申請すれば通る」というものではありません。特に問題になりやすいのが以下のようなケースです。
実務経験の証明が曖昧
技術者や経営者の要件に微妙に届いていない
書類の記載内容が不十分、整合性が取れていない
行政書士は、過去の審査事例や自治体ごとの運用を熟知しているため、「この内容なら通る」というレベルにまで書類を整えることができます。

面倒な書類作成や役所対応を丸投げできる
建設業許可の申請書類は、20~30種類以上に及ぶことがあり、しかもすべてを自社で準備するのは非常に手間です。具体的には:
経営業務管理体制の確認
技術者の資格証明
決算書、残高証明書などの財務資料
法人登記、納税証明の取得 など
これらを行政書士に依頼すれば、必要な情報を伝えるだけで、あとはプロが整理・作成・提出してくれます。

書類の不備や手戻りを防げる
行政書士は、書類作成の専門家であると同時に、役所の審査基準も理解している実務家です。
そのため、
不備のある書類を出して、再提出や補正を求められるリスク
何度も窓口に通う手間
を大幅に削減できます。とくに審査が厳しい都道府県では、この点が大きなメリットになります。

法改正や制度変更にも対応できる
建設業許可制度は、過去にも何度も改正されています。
2020年の「経営業務の管理責任者」の廃止
技術者要件や財産基盤の運用見直し
省略可能な添付書類の変化
これらにいち早く対応できるのは、日常的に申請業務をしている行政書士だけです。
安すぎる行政書士に依頼するリスク

必要な業務が含まれていない(=追加費用)
「安い行政書士」には一見魅力がありますが、内容を確認せずに飛びつくと、かえって高くついたり、許可が下りなかったりするリスクがあります。
特に建設業許可のように複雑な手続きでは、金額以上に「何をしてくれるか」が非常に重要です。
たとえば:
書類作成だけで提出は自分でやる必要がある
添付書類(納税証明書、登記簿など)の取得代行は別料金
不備対応や再提出は追加料金が発生する
👉 最初は安く見えても、トータルで高くなることが多いです。

経験が浅く、許可要件の判断ミスがある
安く受けている行政書士の中には、実務経験が乏しい人もいます。
その結果:
経営業務の管理責任者や専任技術者の証明が甘く、補正・再提出に
証明できない資格・実務経験で申請してしまい、不許可になるリスク
審査官とのやり取りに不慣れで、時間がかかる・通らない
👉 許可が下りないと、元請と契約できない/入札に参加できないなど、事業に大きな影響が出ます。

ヒアリングや相談対応が雑・遅い
低価格で業務を回している場合、以下のようなことも多くあります:
担当者が時間をかけて相談に乗ってくれない
メールの返信が遅い、進捗報告がない
質問しても明確な回答が得られない
👉 結果的に、自社で調査・準備する負担が増えること、建設業法違反を見逃してしまうリスクが高いことになります。

無資格者や外注任せになっている場合がある
報酬が極端に安い場合、実際には:
行政書士が関与せず、事務員や外注が実務を担当
内容確認や申請責任を持っていない
👉 確認ミスや手戻りが多くなり、信頼性に欠ける場合もあります。
建設業専門の行政書士を選ぶメリット

建設業許可専門の行政書士事務所とは?
「建設業許可専門」をうたった行政書士事務所とは、建設業許可の取得支援を主な業務としている行政書士事務所のことです。
以下のような特徴があり、建設業者にとっては非常に心強い存在です。
建設業許可申請の経験・実績が豊富
年間で数十件〜数百件の申請を扱っている
一般建設業・特定建設業・大臣許可・経審など、幅広く対応
難案件(要件ぎりぎり、書類が不備など)にも柔軟に対応できる
👉 経験値が高いため、短時間で的確なアドバイスが可能です。

建設業者向けに業務を特化・最適化している
専用のヒアリングシートや必要書類リストを完備
建設業者の業務スケジュールを理解してスムーズに進めてくれる
要件の確認 → 書類収集 → 申請 → 許可後の届出まで一貫対応
👉 手間が減り、申請ミスや手戻りのリスクも最小限に。

建設業に関わる周辺業務にも対応している
経営業務の管理責任者・専任技術者の確認
変更届・決算変更届・更新手続き
経営事項審査(経審)、入札参加資格申請、会社設立サポート
👉 建設業界で求められる「継続的な行政手続き」をワンストップで任せられます
建設業専門の事務所は周辺業務として建設業者の取得が多い、宅建業、産廃、電気工事業、各地の入札参加資格申請などにも経験があることが多いです。

スピードと的確さを両立できる体制がある
建設業専業の事務所であれば建設業許可の重要性を認識しているため、優先順位の判断とその対応にも柔軟性があります。工事受注が決まり、すぐに技術者の変更をしないといけないなど緊急の案件があった場合すぐに対応できる事務所体制があることも重要です。
専任担当者制や複数名体制で対応
役所とのパイプがあり、事前協議・補正もスムーズ
電話・LINE・メールなどでの迅速なやり取りに対応
👉 建設業者の「現場が忙しくて時間が取れない」という事情にも柔軟に寄り添ってくれます。
選ぶべき事務所の規模は?

事務所規模と特徴
行政書士事務所には一人でやっている事務所もあれば、数百人規模の事務所も存在します。特に全国に支店を持ち大々的に営業している事務所であっても建設部門の人間は数人といった事務所も多いです。ここでは行政書士5名以上+補助スタッフ10名以上抱えている事務所を大規模事務所とし、行政書士1名〜2名、補助スタッフ0〜1名の事務所を小規模事務所として扱います。
大規模事務所のメリット
| 特徴 | 内容 |
|
処理スピードが早い |
分業体制・スタッフ数が多いため、対応が迅速 |
|
実績が豊富 |
年間1000件以上など、数多くの案件をこなしている ※当然レアケースの対応も多い |
|
各種専門家との連携 |
税理士・社労士・司法書士などとワンストップで対応可能 |
|
最新情報に強い |
顧客数が多いため法改正や制度変更への対応が早い傾向あり |
デメリットは高品質な分報酬設定が相場より高いことがある。
小規模な事務所のメリット
| 特徴 | 内容 |
| 価格が比較的リーズナブル | 人件費・広告費などを抑えている分、価格に還元されている場合もある |
デメリットは対応できる件数に限りがあることから、多くの案件を同時に扱えず、対応が遅れることも
また、取扱件数が少ないため、レアなケースや事例に対する判断は弱め

信頼性を見極めるためのチェックポイント
建設業許可の信頼性においては事務所としての体制や対応力が大切です。
|
チェック項目 |
見極めのヒント |
| 実績 |
実績過去の件数、対応業種、許可率などの回答に違和感はないか |
|
担当者の説明力 |
要件や手続きをきちんと理解しているか(曖昧な説明はNG。根拠法令や通達への言及があるか) |
|
見積書の内容、外部の評判 |
どこまでが対応範囲か、責任の所在が明記されているか、紹介、同業者からの評判など |
|
継続的な関係性 |
許可後の届出・更新・経審なども対応する意思があるか 日常の相談は無料か有料か |

結論:信頼性は「規模」でなく「体制」と「人」で決まる
|
観点 |
大手の信頼性 |
小規模の信頼性 |
| 組織の安定性 | ◎ 高い | △ 個人依存 |
| 担当者の質 | △ バラつきあり | ◎ 代表対応が多く質が安定 |
| 顧客対応力 | △ 画一的になりやすい | ◎ 柔軟・親身な対応 |
| 情報管理・契約管理 | ◎ 体制が整っている | ○ 明確な説明があれば問題なし |
| 事務所存続の信頼性 | ◎ 法人化されていることも多い | △ 個人事務所は要確認 |

建設業など専門業務は中規模事務所がおすすめ
中規模の行政書士事務所は、大手の組織力と小規模事務所の柔軟性の“いいとこ取り”をしている存在です。
建設業許可のように専門知識と継続的なサポートが必要な分野では、最もバランスの取れた選択肢となることが多いです。

中規模行政書士事務所の主な特徴
|
項目 |
内容 |
| 人員体制 | 行政書士2~4名、補助スタッフ数名程度 |
| 拠点 | 基本は1拠点(都市部や県庁所在地など) |
| 対応件数 | 年間100~500件程度、業種に特化していることが多い |
| 得意分野 | 建設業許可、経審、入札支援などに強みを持つ事務所が多い |
| 分業+担当制 | 担当者がつき、進捗管理や顧客対応は個別に対応 |
| 柔軟な対応力 | 代表も現場に関わるため、要望に応じて動きやすい |
| 価格帯 | 相場の中間的な設定が多い |
| 信頼性 | 経験豊富で、専門性と対応力を両立しているケースが多い |
✅ 中規模事務所のメリット
✔ 建設業許可を依頼するうえでの強み
専門性の高いチームがいる:建設業専門チームを編成している場合も
申請〜経審・入札まで一貫対応が可能:長期的な関係を築きやすい
代表者が現場に出てくるケースが多い:経験と判断力が直結している
スピード対応にも柔軟に対応:緊急案件にも比較的強い
✅ デメリット(注意点)
事務所によってバラつきがある
→ 規模が中間ゆえに、「専門事務所」と「なんでも屋」が混在している
→ 建設業に強いかどうかは実績で確認する必要あり
対応力はスタッフに依存することも
→ スタッフが固定されている分、相性やスキル差が影響することもある
行政書士に聞くべき質問リスト(建設業許可編)

実績・経験について
建設業について
建設業許可申請の実績はどれくらいありますか?
一般と特定の両方の許可申請に対応していますか?
今までに扱った業種(建設業29業種)はどのようなものがありますか?
経営業務の管理責任者や専任技術者の要件証明が難しい案件も扱ったことはありますか?
業種の具体的質問
付帯工事というのはどのようなものでしょうか?
(付帯工事というのは許可を受けた建設業の業種以外の工事ですがその工事がなければ工事の目的を達成できない工事だから、許可がなくても受注できる工事です。例えば塗装工事における足場の組み立て(とび・土工工事業)など。許可がなくてもできるという点では500万円以下の軽微な工事と同じですが、付帯工事は500万円を超えるものを指します)

業務範囲・対応内容について
どこまでやってもらえますか?(書類作成・提出・添付資料の収集など)
必要書類の取得代行(納税証明・登記簿謄本など)は可能ですか?
申請前の要件チェックや、不足書類のアドバイスもお願いできますか?

アフターサポート・継続業務について
許可取得後の決算変更届や更新申請にも対応していますか?
許可取得後の相談などはどのように受け付けていますか?
顧問契約や年間サポートプランはありますか?
経営事項審査(経審)や入札資格の取得にも対応できますか?
行政書士事務所の選び方

建設業許可の実績が豊富かどうか
行政書士を選ぶ際は、「誰に頼んでも同じ」ではなく、経験・対応力・信頼性など複数の観点で慎重に判断することが重要です。特に建設業許可は専門性が高いため、以下のポイントを基準に選ぶのがおすすめです。
建設業許可は行政書士業務の中でも専門性が高く、経験差が顕著に出る分野です。
チェックポイント:
過去に許可申請を何件以上扱っているか(10件以上が目安)
一般だけでなく特定建設業、大臣許可など複雑な案件にも対応できるか
経営業務や技術者要件の証明に慣れているか

地元自治体の審査傾向に詳しいか
建設業許可は都道府県ごとに運用が異なる部分があります。地元の審査官の判断傾向や、よく求められる補足資料を熟知している行政書士は、通りやすい申請をしてくれます。
チェックポイント:
地元での建設業許可の対応実績があるか
審査官とのやり取り経験が豊富か

説明がわかりやすく、対応が丁寧か
制度の仕組みや、なぜその書類が必要なのかをわかりやすく説明してくれる行政書士は信頼できます。逆に、専門用語ばかりで質問をはぐらかすような対応をする人は避けた方がよいです。
チェックポイント:
初回相談時に丁寧なヒアリングがあるか
質問への回答は適切か(根拠条文や通達を提示できるか)
見積書の説明や作業内容が明確か

アフターサポートがあるか
建設業許可は一度取れば終わりではなく、定期的な届け出や更新、経審などの継続支援が必要です。将来的に頼り続けられる行政書士かどうかも確認しましょう。
チェックポイント:
許可取得後の決算変更届・更新対応も可能か
許可取得後の質問は可能か
経審や入札支援の実績があるか
一番古い顧客はどのぐらい継続して付き合っているのか