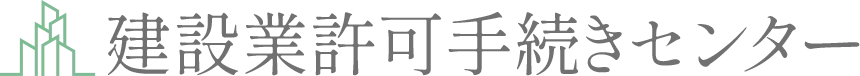建設業の全業種の概要と分類
2025/05/13
建設業法に基づく建設業の全29業種について、それぞれの概要と分類(建築一式・土木一式/専門工事)をわかりやすく解説します。
目次
建設業の分類と全29業種一覧(建設業法施行令第1条)

一式工事と専門工事の違い
建設業は「一式工事」と「専門工事」に分かれていますが、その理由は工事の性質と管理責任の違いにあります。
「一式工事」は、建築一式・土木一式の2種で、建物全体や道路など大規模で多種の工種を統括管理する工事です。元請として工事全体を計画・調整・管理する能力が求められ、実際の作業は多くの専門業者に下請けします。
一方、「専門工事」は、左官・電気・塗装など特定の工種に特化した実作業の工事で、それぞれに専門的な技能と技術が必要です。
すみ分けの基本は、「総合的な企画調整能力が求められるか(=一式)」か、「特定分野の施工能力が問われるか(=専門)」という点です。建設業法ではこの区分に基づいて、許可や責任範囲、技術者要件を明確に分けています。

一式工事業者と専門工事業者の関係性
一式工事業者と専門工事業者は、建設現場において発注者と施工の橋渡しを担う「管理者」と「技能者」の関係にあります。一式工事業者は工事全体を統括し、工期・安全・品質・コストを管理する元請としての役割を担います。実際の施工は専門性が高いため、各工種に応じて専門工事業者に発注(下請)し、それぞれの専門分野の技術力に依存します。一式工事業者は、工程の調整や技術的な指導を行いながら、複数の専門業者をまとめて工事全体を完成させます。このように、両者は「管理」と「実作業」を分担し、相互に補完しながら工事の品質と安全を確保する関係にあります。

土木一式工事とは
土木一式工事は、道路・橋梁・ダム・河川・上下水道などの土木構造物の建設全体を総合的に管理・施工する工事です。単体の専門工事ではなく、複数の工種を組み合わせて一体的に完成させる大規模工事が対象で、工事全体の計画・調整・品質管理を行う能力が必要です。実際の施工は専門業者に発注することが多く、元請業者としての責任が重視されます。また、発注者との契約や設計変更への対応、施工体制の構築なども重要な役割です。建設業法では、単にとび・土工・舗装などの工事を単独で行う場合は土木一式には該当せず、「総合的な企画・調整・指導」を伴う場合に限り土木一式工事とされます。

建築一式工事とは
建築一式工事は、住宅やビル、学校、工場などの建築物を新築・増築・改修する工事全体を総合的に管理・施工する工事です。複数の専門工事(大工、電気、内装、設備など)を統括して一体的に建物を完成させるもので、発注者との契約、設計変更への対応、工程・品質・安全管理などの総合的な能力が求められます。実際の施工は、各工種ごとに専門工事業者へ下請することが多く、一式業者は工事全体の調整役を担います。建設業法では、単に大工や内装などの個別工事を行う場合は建築一式とは認められず、建築物を完成させるために複数工種を取りまとめる工事が対象となります。元請としての責任と調整能力が問われる業種です。

専門工事業者とは
専門工事業者とは、建設業における特定の工種に専門特化した技能と知識を持ち、実際の施工を担う業者のことです。建設業法では、大工、電気、塗装、配管、鉄筋などの27業種が専門工事に分類され、それぞれに応じた技術者や施工体制が求められます。
専門工事業者は、元請となる一式工事業者から下請として発注を受け、現場での実作業を担当します。彼らの技術力が、建設物の品質・耐久性・安全性を左右する重要な役割を担っており、現場の技能者・職人を直接抱えていることが多いのが特徴です。
また、一定規模以上の専門工事を元請として直接請け負うことも可能であり、技術力と実績があれば専門工事業者単体で公共工事の元請を担うケースもあります。建設現場において、一式業者と並び欠かせない存在です。

大工工事業とは
大工工事は、建築物の骨組みや内装の木材部分を施工する工事で、木造建築を中心とした建設現場において極めて重要な専門工事の一つです。主に、柱・梁・床・屋根などの構造体を組み立てる「躯体工事」と、間仕切り壁・天井・建具枠などを仕上げる「造作工事」に分かれます。伝統的な木造住宅の建築に限らず、鉄骨造やRC造の建物でも、内装部分で大工の技術が必要とされる場面は多く、汎用性の高い技能です。
また、設計図に基づき、現場の状況や材料の癖を読みながら施工するため、高度な加工技術と現場判断力が求められます。使用する道具も、かんな・のこぎり・のみといった伝統的な手工具から、プレカット材を組み立てる現代的な施工技法まで幅広く、技能の継承と進化が並行しています。
大工工事業者は、建築現場における基礎的な工種の一つであり、建築一式工事を構成する重要な柱として、住宅から公共施設に至るまで幅広く活躍しています。ですが、近年では木造建物でも電気工事や管工事など他の専門工事と連携し建築物の築造をするケースがほとんどであるため、「躯体部分」を含め「総合的に企画調整」する場合は建築一式に該当すると判断されることが多く、大工工事業の代表例は型枠大工業となっています。

左官工事業とは
左官工事業は、建物の壁・床・天井などにモルタルや漆喰、土、珪藻土などを塗り仕上げる専門工事です。下地調整から仕上げまでを一貫して行い、建物の外観や内部空間の品質・美観・耐久性を左右する重要な工種とされています。伝統的な工法ではコテを使い手作業で丁寧に塗り上げる技術が重視され、熟練の職人技が求められます。
近年では、コンクリートやALCの壁面などにも対応し、下地処理や外断熱材の施工、補修工事、防水下地施工など多様な用途に広がりを見せています。また、タイル工事や塗装工事と連携することも多く、工程管理上でも重要な位置づけにあります。
左官工事は単なる「塗る作業」ではなく、建物の耐久性・断熱性・防水性などの性能向上に貢献する技術であり、特に自然素材や仕上げの美しさが求められる住宅や公共建築で重宝されています。

とび・土工工事業とは
とび・土工工事業は、建設工事の準備段階から基礎構築、構造物の組立までを担う基盤的な工種で、非常に範囲が広いのが特徴です。主な内容としては、足場の組立・解体、掘削・埋戻し、山留め、地盤改良、杭打ち、仮設構造物の設置などが含まれます。また、高所作業における鉄骨建方や鉄塔の組立といった「とび作業」も含まれます。
とび・土工工事は、多くの建設現場で最初に行われる工事であり、他の専門工事が安全かつ円滑に進行するための重要な基礎づくりを担っています。また、重機操作や仮設安全の管理など、高度な技能と安全配慮が求められる業種です。建築・土木を問わず、幅広い現場で活躍する不可欠な専門工事です。
また、建設業法上では他の専門工事のどれにも該当しないものを最終的に受け入れる業種として使用されています。

石工事業とは
石工事業は、自然石や人工石などを用いて構造物や外構、装飾などを施工する専門工事で、石を加工・据付して構造物を形成する業種です。具体的には、石積み擁壁、石張りの外壁・床、記念碑・モニュメント、墓石の設置などが対象となります。建築分野では装飾的な外装材として、土木分野では擁壁や護岸など構造的用途でも用いられます。
石材は重量があるため、据付精度・安全性・耐久性が非常に重要で、クレーンなどの重機操作や、モルタル・接着材を用いた高度な施工技術が求められます。施工には、設計図に応じた石の加工・運搬・据付を一貫して行う専門的な知識と経験が必要です。石工事は、建築物の美観と堅牢さを両立させる重要な工種として多くの現場で採用されています。

屋根工事業とは
屋根工事業は、建物の屋根部分に関する施工を専門に行う工事業種で、屋根材の取付・修繕・葺き替えなどを行う工種です。主な対象は、瓦、スレート、金属板、アスファルトシングルなど多様な屋根材で、建物の構造や地域の気候条件に応じて適切な材料と工法が選ばれます。
屋根は建物の最上部に位置し、雨風・雪・日射など自然環境から建物を守る重要な役割を担っており、耐水性・断熱性・耐久性を確保するための精密な施工が求められます。また、近年では太陽光パネルの設置に対応した施工も増えており、高度な知識と安全管理が必要です。
勾配屋根では高所作業となるため、安全帯や足場の使用など厳格な安全対策も不可欠です。屋根工事は、住宅・ビル・工場などのあらゆる建物に関わる基礎的な工事であり、美観と防水性を両立させる職人技が生きる専門分野です。

電気工事業とは
電気工事業は、建築物や構造物において電気設備を設置・改修・移設・撤去する専門工事であり、建設業法上の「電気工事業」としての許可と、電気工事士法に基づく「電気工事業者登録制度」の両方が関係する点に特徴があります。
建設業法における電気工事業は、受変電設備、配電盤、屋内配線、照明設備、防犯設備、避雷針などの施工を対象とし、工事規模に応じて建設業許可(一般または特定)が必要です。特に500万円以上(材料費含む)の請負工事は許可がなければ受注できません。
一方、電気工事士法に基づく電気工事業者登録制度は、一般用電気工作物(住宅など)や自家用電気工作物(ビル・工場など)を扱う工事において、一定の技術者(第一種または第二種電気工事士等)を配置し、都道府県知事への登録または届出が必要です。建設業者に関してはみなし電気工事業者登録が必要です。
つまり、電気工事業を営むには、建設業法の許可と、電気工事士法の登録の両方を満たす必要がある場合が多く、工事の内容と範囲に応じて正確な制度理解と手続きが求められます。安全性・法令遵守の観点からも、適切な資格者の配置と制度運用が不可欠な業種です。

管工事業とは
管工事業は、建築物や構造物における配管設備の設置・改修・撤去を行う専門工事で、主に給排水、冷暖房、空調、衛生設備、ガス、消火設備などの配管を対象とします。住宅やビルだけでなく、工場・プラント・病院・商業施設など多種多様な建物において、生活インフラや業務機能の根幹を支える重要な分野です。
工事内容は、設備設計図に基づいた配管の取り回し、支持金具の設置、機器との接続、試運転調整などが含まれ、配管の材質(塩ビ・鋼管・銅管など)や接合方法も多岐にわたります。また、水圧試験や気密試験など品質確認も不可欠で、高度な施工技術と法令知識、安全管理能力が求められます。
建物の機能性・快適性を左右する責任ある工種です。冷暖房や衛生環境を支える裏方として不可欠な専門職です。

タイル・れんが・ブロック工事業とは
タイル・れんが・ブロック工事業は、建築物の壁面や床面、外構などにタイル・れんが・コンクリートブロックを張り付けたり積み上げたりする専門工事です。タイルは主に内外装の仕上げ材として使用され、美観や耐久性、耐水性の確保に貢献します。昔は水回りに欠かせない素材でしたが、近年ではユニットバスなどの普及もあり、個人邸では浴室やトイレでも見かけることが少なくなっています。れんがやブロックは、構造物の一部として使用されることもあり、意匠性と強度を両立させる施工が求められます。
施工には、下地調整から始まり、接着剤やモルタルを使用して正確に配置する技術が必要です。特に目地の仕上がりや寸法精度が仕上がりの品質を左右するため、熟練した職人の技術と丁寧な作業が重要です。
また、外構や防火壁、間仕切り壁としてブロック積みが使われるケースでは、耐震性や安全性にも配慮し、鉄筋補強やアンカー施工などが求められます。建築物の仕上げや構造の一部として、機能性と装飾性を担う工種です。

鋼構造物工事業とは
鋼構造物工事業は、鉄骨や鋼材を使用して建築物や構造物を製作・組立・設置する専門工事です。主な対象は、鉄骨造の建物、歩道橋、鉄塔、煙突、タンク、看板架台、ゲートなどで、設計図に基づき鋼材を工場で加工し、現場で組み立てる工程が中心となります。
構造計算に基づいた精密な寸法管理と溶接・ボルト締結などの高い技術力が求められ、耐震性・耐久性を確保するためにも厳格な施工管理と検査が不可欠です。また、高所作業や重機を使用するため、安全対策と作業員の技能も重要なポイントです。鋼構造物工事は、建物やインフラの骨組みを形づくる基幹的な工種として、土木・建築の両分野で幅広く活躍しています。

鉄筋工事業とは
鉄筋工事業は、コンクリート構造物の内部に組み込む鉄筋を加工・組立・配置する専門工事です。対象はビルや橋梁、トンネル、擁壁などの鉄筋コンクリート構造物で、施工精度が建物の強度・耐震性・耐久性に直結します。
主な作業は、図面に基づいた鉄筋の切断・曲げ加工、現場での配筋、結束(番線や溶接)、スペーサー設置、かぶり厚さの確保などです。打設されるコンクリートの中に隠れてしまうため、目に見えない部分こそ厳密な品質管理が求められ、検査も重要な工程となります。
また、現場では他工種との工程調整が必要で、特に型枠・土工・コンクリート工事との連携が重要です。建物の骨格を形成する極めて重要な工種として、土木・建築両方の分野で幅広く活躍しています。

舗装工事業とは
舗装工事業は、道路・駐車場・空港滑走路・歩道などの地表面にアスファルトやコンクリートを敷きならし、交通の安全性や快適性を確保するための専門工事です。新設工事だけでなく、老朽化した舗装の補修や再舗装、区画線(塗装工事)や排水溝築造(とび・土工工事)との連携施工も対象となります。規模の大きなものは土木一式工事に該当することもあります。
主な工程は、路盤の整地・転圧から始まり、アスファルト混合物やコンクリートの敷設、仕上げの転圧までを一貫して行います。施工には専門の重機(フィニッシャー、ローラーなど)を用い、平滑性・排水性・耐久性を確保する高度な施工管理が求められます。
また、道路工事は交通規制や騒音・振動への配慮も必要であり、地域住民や通行者への安全対策も重要な業務の一環です。舗装工事は、公共インフラの維持や都市機能の整備に欠かせない、生活基盤を支える重要な工種です。

しゅんせつ工事業とは
しゅんせつ工事業は、河川・港湾・湖沼・運河などの水域において、水底に堆積した土砂やヘドロを掘削・除去する工事です。これにより、水深を確保し、船舶の安全な航行や排水機能の維持、洪水防止などを図ります。「しゅんせつ」とは「浚渫」と書き、海底や河床をさらって清掃・掘削することを意味します。単なるどぶさらいのようなものはしゅんせつ工事には該当しません。
主な作業は、浚渫船やバックホウ浚渫機などの特殊機械を使用し、水中にある土砂を吸引・すくい上げ、陸上へ搬出・処分する流れです。作業には水流や潮汐の影響を受けるため、高い操船技術と施工管理能力が求められます。
また、環境への影響にも配慮が必要で、濁水対策や底質の管理、漁業・生態系への影響評価なども重要です。しゅんせつ工事は、水域のインフラ維持や治水対策、港湾機能の安定に欠かせない特殊かつ重要な工種です。

板金工事業とは
板金工事業は、金属板(鋼板・銅板・アルミニウム板など)を加工・取付し、屋根・外壁・雨樋・ダクトなどの防水・装飾・換気機能を構築する工事です。主に住宅やビルの屋根葺き、外壁の金属サイディング施工、庇や笠木の仕上げ、雨仕舞い処理などが含まれます。
工事では、金属板を現場の形状に合わせて切断・折曲げ加工し、建物に正確に取り付ける技能が必要です。特に雨漏り防止のため、水勾配や重ね合わせの設計・施工が重要となり、仕上がりの美しさと機能性の両立が求められます。
また、近年では省エネ対策として金属断熱屋根材の施工や、外装の意匠性向上を目的とした装飾板金のニーズも高まっており、高度な施工技術と設計理解力を併せ持つ専門職として活躍の幅が広がっています。

ガラス工事業とは
ガラス工事業は、建築物の窓やドア、間仕切りなどに使用される各種ガラスの取付・交換・修理を行う専門工事です。対象は、透明ガラス・複層ガラス・強化ガラス・防音・防火・防犯ガラスなど多岐にわたり、住宅・ビル・商業施設・公共建築など幅広い現場で施工されます。
主な作業は、ガラスの切断・加工・運搬・取付で、サッシやフレームとの精密な調整が必要です。また、安全性確保のため飛散防止措置や強度確認が求められるほか、高所作業や大型ガラスの設置には専用の吸盤機器やクレーン等の使用もあります。
断熱・防音・省エネなどの性能を備えた高機能ガラスの普及により、高度な施工技術と製品知識が求められる工種であり、建物の快適性やデザイン性の向上にも大きく貢献しています。

塗装工事業とは
塗装工事業は、建物や構造物の外壁・内装・鉄骨・木部などに塗料を塗布し、美観・保護・防水・防錆機能を持たせる専門工事です。住宅・ビル・橋梁・機械設備など、あらゆる分野で行われ、対象素材や目的に応じて適切な塗料と施工方法を選定します。
外壁・屋根・鉄骨・橋梁・タンク等の塗装のほか、道路の区画線や標示(ライン工事)も塗装工事に該当します。
塗装は見た目の美しさだけでなく、構造物の長寿命化に直結するため、維持管理・保全の観点からも重要な役割を果たします。環境対応型塗料や遮熱塗装など新技術の導入も進んでいます。

防水工事業とは
防水工事業とは、建築物や構造物に対して雨水や地下水などの浸入を防ぐための防水層を設ける工事を対象とする、建設業法上の専門工事業です。主な施工対象は、屋上、バルコニー、外壁、地下室、浴室、プール、水槽などで、漏水や劣化を防ぎ、建物の耐久性と居住性を確保する役割を担います。
工法には、ウレタン塗膜防水、シート防水、アスファルト防水、FRP防水などがあり、構造や用途、立地環境に応じて適切に選定されます。特に雨漏りや水漏れは建物の重大な瑕疵につながるため、防水工事は建物保全の要となる工種とされています。
また、タイルや塗装と異なり、「水の浸入を防ぐ性能を持つ層を構築すること自体が工事の目的」であるため、単なる仕上げではなく、機能性重視の専門工事です。

内装仕上げ工事業とは
内装仕上工事業は、建築物の室内空間において、天井・壁・床などの内装部分を仕上げる専門工事業です。主な内容には、壁紙(クロス)貼り、カーペット・フローリング敷設、軽量鉄骨下地組立、ボード貼り、パーティション設置、カーテン・ブラインド取付などが含まれます。
施工は、意匠性・機能性・居住性に大きく関わり、公共施設や商業ビル、住宅など幅広い建物で行われます。空間デザインだけでなく、防音・断熱・耐火などの性能にも関わるため、技術力と設計理解が求められる工種です。
また、他工種との工程調整が重要で、特に建築工事の終盤に集中するため、工程管理と品質管理能力も重視されます。

機械器具設置工事業とは
機械器具設置工事業は、建設業法における専門工事業の一つで、機械器具の据付・組立・設置を行う工事を対象とします。単に機械を搬入するだけでなく、基礎との固定・据付位置の調整・機械の連結や調整作業を伴うものが含まれます。
対象となる機械は多岐にわたり、エレベーター・立体駐車装置・発電設備・冷凍機・搬送コンベヤ・大型ポンプ・水処理装置・印刷機械・集塵装置などがあります。これらの機器を、建築物や土木施設に恒久的に据え付け、安全に稼働する状態に設置することが要件です。
また、電気・管工事や土工事と組み合わせて施工されることも多く、多分野にわたる知識と精密な施工管理能力が求められる業種です。特に大型機器の設置では、基礎アンカーの打設や機器調整、クレーンによる吊上げなど、高度な施工手法と安全対策が必要です。請負金額が500万円以上となる場合には、機械器具設置工事業の建設業許可が必要です。
機械器具設置工事の特徴は、他の専門工事に該当する工事である場合はそちらと判断されます。ですから、同じ名称の工事でも、清掃施設でもなく消防施設でもなく水道施設でもなく、とび土工でなく、管工事でもなく、電気工事でもないものが機械器具設置工事になります。

熱絶縁工事業とは
熱絶縁工事業は、建物や設備の内部・外部に断熱材を設置し、熱の損失や外気との温度差による結露を防ぐ工事を対象とする専門工事です。主な施工対象は、冷暖房配管・ダクト・ボイラー・貯湯槽・冷凍設備・空調機械室・冷凍倉庫・天井裏などで、工場や病院、商業施設、住宅まで幅広く適用されます。
断熱材には、グラスウール・ロックウール・ウレタンフォーム・ポリスチレンフォームなどがあり、用途や温度条件に応じて適切な材料と工法を選定します。目的は、省エネ・安全性の確保・機器の効率維持・結露や騒音の防止など多岐にわたります。
また、屋根や外壁などの建築的断熱のほか、配管・設備に直接施す「設備断熱」も対象です。近年は省エネ意識の高まりにより需要が増加しています。

電気通信工事業とは
電気通信工事業は、電話・インターネット・テレビ放送・LAN・光ファイバー・防犯カメラ・無線設備など、情報伝達に関わる通信設備を設置・接続・調整する工事を対象とする専門工事です。建物内外の通信ケーブルの敷設、基地局の設置、アンテナ工事、データセンターや監視システムの構築も含まれます。
通信機器の高度化により、施工には電気通信の専門知識と情報系技術への理解が求められます。特に光回線やIPネットワークなど、インフラと密接に関係するシステムの整備が多く、安全で安定した通信環境を構築することが目的です。
また、国や自治体の防災無線や教育施設のICT整備などでも重要な役割を担います。

造園工事業とは
造園工事業は、公園、庭園、緑地、校庭、屋上緑化などにおいて、植栽・景観構造物・園路・修景施設などを整備・造成する専門工事です。樹木の植え付けや移植、芝張り、石組み、水景施設、あずまや・ベンチなどの設置工事、地形造成や土壌改良を含む外構空間の総合的な施工が対象となります。
一方、伐採や剪定、草刈り、緑地の維持管理作業のみを行う業務は、建設業法上の造園工事には該当しません。造園工事は、単なる美観の維持ではなく、景観設計や都市の緑化計画に基づく構造物や植栽の施工を伴う、設計意図を反映した造成・整備工事であることが前提です。

さく井事業とは
さく井工事業(削井工事業)は、地下水のくみ上げや地質調査、温泉・ガス井などの掘削を行う工事を対象とする建設業の専門工事業です。主に、井戸の新設・改修・埋戻し、ボーリングによる地盤調査、揚水設備の設置や保守管理などが含まれます。
掘削方法には、ロータリー式やパーカッション式などがあり、地質や地下水位の状況に応じた高度な施工技術と機械操作の知識が必要です。特に、地下水の供給源確保や温泉開発では、周辺環境への配慮と水利権・条例遵守も求められます。
また、土木一式工事や管工事と連携する場面も多く、インフラ整備や災害対策に不可欠な工種です。

建具工事業とは
建具工事業は、建築物におけるドア・窓・ふすま・障子などの可動性を持つ仕切りや開口部材(建具)を製作・取付・調整する専門工事です。対象には、木製・金属製・樹脂製の建具のほか、自動ドアや防火扉、シャッター、間仕切りなども含まれます。
現場では、建築図面に基づき枠や建具本体の取付、丁番やクローザーなどの金物調整、気密性や防火性の確保などが求められ、精度の高い施工と調整技術が必要です。また、近年では高断熱サッシや遮音建具など、機能性を重視した製品の施工ニーズも高まっています。
建具工事は内外装の仕上げに大きく関わり、使い勝手・安全性・美観を左右する重要な工種です。

水道施設工事業とは
水道施設工事業は、公共の上水道・工業用水道・農業用水などの施設や配管を敷設・設置する工事を対象とする専門工事です。主に、取水施設・浄水場・配水池・ポンプ場・本管の布設など、上水道システムの中核をなす施設整備が含まれます。
道路下に布設される「本管」に関しては、上水道の本管は水道施設工事業の対象であり、これは水を各家庭や施設へ配る「配水本管(主管)」で、通常は口径75mm以上の管が該当します。
一方、下水道の本管(汚水・雨水管)は水道施設工事業には含まれず、土木一式工事や管工事業に該当します。この違いは工事の目的と扱う水の性質によるもので、清潔な飲料水を供給する設備が水道施設工事、排水処理や排水路を整備するのは別の業種として扱われます。
上水・下水の本管工事は外見が類似していても、建設業法上では明確に区別されており、適切な業種許可の取得が必要です。

消防施設工事業とは
消防施設工事業は、火災の発生を防ぎ、万一の火災時に初期消火や避難誘導を可能にするための消防用設備を設置・改修・点検する専門工事業です。対象となる設備は、スプリンクラー設備・屋内外消火栓・自動火災報知設備・非常警報・誘導灯・泡消火設備・不活性ガス消火設備など多岐にわたります。
これらの設備は消防法に基づき、建物の用途・規模に応じて設置義務があるため、施工には建築基準法および消防法の知識と設計理解が不可欠です。また、電気工事や管工事と一体的に行われることも多く、複数分野にまたがる施工管理能力も求められます。
施工には消防設備士や消防設備点検資格者の関与が必要な場合が多く、工事後の性能試験・届け出も法令で義務付けられています。防災上の機能を直接担うため、確実かつ法令に適合した設置が求められる重要な工種です。

清掃施設工事業とは
清掃施設工事業は、ごみ処理やし尿処理、汚泥処理などを行うための廃棄物処理施設を建設・設置する専門工事業です。対象施設には、ごみ焼却場、リサイクル施設、最終処分場、し尿処理場、脱水・乾燥・焼却設備、灰溶融施設などが含まれます。
これらの施設は、地域の衛生環境や生活インフラを支える重要な社会資本であり、構造が複雑で高温・高圧処理や高度な排ガス・排水処理設備を伴うことが多いため、土木・建築・機械・電気・管工事などの複合的な技術と調整力が求められます。
また、施工にあたっては公害防止、悪臭対策、耐震性確保といった厳しい法規制や技術基準への対応が必要です。公共事業としての整備が中心であることから、設計段階から高度な専門知識が必要であり、特定建設業としての許可が求められるケースも多い工種です。

解体工事とは
解体工事業は、建築物や土木構造物を安全かつ計画的に取り壊す専門工事業で、平成28年6月の建設業法改正により、それまで「とび・土工工事業」に含まれていた解体工事が独立した業種として位置づけられました。対象となるのは、木造・鉄骨造・RC造などの建築物、煙突・橋梁・擁壁などの構造物で、重機や手作業による解体、アスベスト除去、廃材の分別・搬出などが含まれます。
安全管理や騒音・粉じん対策が厳しく求められ、建設リサイクル法や労働安全衛生法など多くの法令に対応した施工体制が必要です。請負金額が500万円以上となる場合は、解体工事業の建設業許可が必要であるというのは他の業種と同じなのですが、一式工事の許可を持たない者は500万円未満の工事をする場合は解体工事業者登録がなければ施工ができない点に注意が必要です。

よくある勘違い
建築一式工事の許可があれば建築系の土木一式工事の許可があれば土木系の工事を総合的に受注できる。❌ 500万円以上の単独専門工事は不可です。
建設業における「一式工事業(建築一式・土木一式)」の許可を持った会社が、他の工事(特に専門工事)を行う場合には、できることとできないことが明確に定められています。以下に、【建築一式・土木一式の許可のみを持つ会社】が行える範囲について詳しく説明します。
✅ 一式工事業者が行える工事の範囲
▶ 一式工事の許可だけで可能な工事:
複数の専門工事を組み合わせて、建築物や土木構造物を一体的に完成させる工事
例:住宅の新築(大工、屋根、内装などを統合管理)
例:道路整備(舗装、排水、標識、造成などを一括発注)
一式業種に該当しない専門工事でも、金額が軽微であれば可能
❌ 一式工事の許可「だけ」では原則できないこと
単体の専門工事を500万円以上で請け負うこと
例:屋根工事単独で600万円の請負 → ×
例:電気工事単独で700万円の工事 → ×
これらは、それぞれの専門工事業種の許可が別途必要です。

許可がなくても施工ができる軽微な工事とは
建設業法では、一定規模未満の工事については建設業の許可がなくても施工が可能とされており、これを「軽微な工事」と呼びます。具体的には、
①建築一式工事で請負金額が税込1,500万円未満、かつ木造住宅で延床面積が150㎡未満の工事、
②それ以外の専門工事で請負金額が税込500万円未満の工事
が該当します。これらの軽微な工事は、元請・下請を問わず許可不要で受注・施工が可能です。ただし、金額には消費税を含めて判断するのが国土交通省の公式な運用です。
反復継続して業として行う場合や公共工事に参加する場合は、軽微でも許可取得が実務上求められることが多いため注意が必要です。
建設業に関連する業務について

電気工事業者登録とは
電気工事を適法に行うには、「建設業法」と「電気工事士法」の双方の制度を理解する必要があります。まず、建設業法における「電気工事業」は、1件あたり税込500万円以上の電気工事を請け負う際に必要な許可であり、営業所ごとに専任技術者や経営業務管理責任者などの要件を満たす必要があります。一方、金額が500万円未満であれば、電気工事業の許可がなくても施工は可能です。
これとは別に、電気工事士法に基づく「登録電気工事業者制度」は、請負金額にかかわらず、一般用・自家用電気工作物を施工する全ての事業者に適用されます。この制度においては、一定の有資格者(電気工事士や電気主任技術者など)の配置と、都道府県知事への登録(または届出)が求められます。
このとき、建設業法の許可を受けていれば、電気工事業の許可がなくても「みなし登録電気工事業者」として届出を行うことで、登録電気工事業者と同様の扱いを受けることができます。重要なのは、自動的に登録されるのではなく、必ず都道府県への「みなし登録の届出」が必要だという点です。
つまり、建設業許可があるからといって無条件に電気工事ができるわけではなく、施工内容と金額に応じて、建設業許可と電気工事士法の制度を正しく使い分ける必要があります。

解体工事業者登録
解体工事業者登録とは、建設リサイクル法に基づき、一定規模以上の建築物等の解体工事を元請として請け負う際に必要となる制度である。対象となるのは、建設業法に基づく「解体工事業」、「建築一式工事業」「土木一式工事業」の許可を持たない業者で、床面積80㎡以上の建築物などを解体する場合には、都道府県知事等への登録が義務付けられる。一方、解体、建築、土木の3業種の許可を有している者はこの登録が免除される。請負金額が500万円以下で建設業許可が不要な軽微な工事であっても、リサイクル法の対象構造物に該当する場合には登録が必要となる点に注意が必要である。
「解体工事業に係る登録等に関する省令」第7条の5により、5年ごとの更新を受けなければ、登録は効力を失います。
よって、継続して元請として解体工事を行うには、更新手続きの管理が必須です。

住宅改修業者登録とは
兵庫県では、住宅改修による消費者被害の発生を受け、平成18年度から住宅改修業者登録制度を実施しています。この制度は、住宅改修工事の請負実績や事業者情報を県民に公開することで、安心して業者を選べる環境を整備するとともに、業者の資質向上と住宅改修業の適正化を目的としています。登録業者は、施工実績、苦情処理体制、建設業許可の有無などが審査され、登録後は県のホームページ等で公表されます。制度により、県民の信頼性の高い業者選びが促進されています。

(神戸市)指定給水装置工事業者とは
神戸市指定給水装置工事事業者とは、神戸市水道局から指定を受け、水道法に基づき給水装置の新設・改造・修繕などの工事を適正に行うことが認められた事業者です。指定を受けるには、必要な技術資格(給水装置工事主任技術者)を有し、資力・信用・設備などの基準を満たす必要があります。指定業者でなければ、神戸市の水道本管から分岐する給水装置工事を行うことはできません。指定後も定期的な更新や技術者の継続配置が求められ、市民の安全な水の供給と適正施工の確保を図っています。

建築物排水管清掃業とは
建築物飲料水貯水槽清掃業とは、マンションやビルなどに設置された飲料水用の貯水槽(受水槽・高架水槽)を定期的に清掃・消毒し、水の衛生を保つ専門業種です。建築物衛生法に基づき、特定建築物においては年1回以上の清掃が義務づけられており、清掃業者は都道府県等への登録が可能です。清掃は、水の供給を一時停止して槽内の汚れや沈殿物を除去し、塩素などで消毒を行います。適切な清掃は水質事故や健康被害の防止につながり、専門技術と衛生管理が求められる業務です。

建築物排水管清掃業とは
建築物排水管清掃業とは、ビルやマンション等の排水設備において、台所・浴室・トイレなどの排水管内にたまった汚れやスケールを専用機器で洗浄・除去し、詰まりや悪臭、害虫の発生を防止する業種です。建築物衛生法に基づく登録制度が設けられており、一定の機材や有資格者を備えた業者は、都道府県知事の登録を受け「登録建築物排水管清掃業」と称することができます。ただし、この登録は任意であり、登録を受けていない業者が業務を行うことも法的には制限されていません。実務上は、信頼性や受注機会の観点から登録が推奨されています。

建築物環境衛生総合管理業とは
建築物環境衛生総合管理業とは、多数の人が利用する特定建築物において、空気環境の測定や調整、清掃、給排水の管理、飲料水の水質検査など、建築物の衛生的環境を総合的かつ一体的に維持管理する業種です。建築物衛生法に基づき、一定の機器や有資格者(建築物環境衛生管理技術者など)を備えている事業者は、都道府県知事に登録を申請することができ、登録を受けると「登録建築物環境衛生総合管理業」と称することが可能です。この登録は任意であり、未登録でも業務自体は行えますが、特定建築物における信頼性確保や入札要件等の観点から、登録が推奨されています。

建設業の業種の選定についてのアドバイス
建設業の業種選定においては、自社が実際に施工する工事の内容や実績に基づいて、該当する専門工事業種を正確に把握することが重要です。例えば、内装工事を行っている業者が誤って大工工事や建具工事を申請すると、許可後に施工対象外と判断されるリスクがあります。また、将来的な事業拡大を見据えて、現在の受注状況だけでなく、見込み案件や発注者からの要望も考慮するとよいでしょう。建築一式や土木一式の取得は要件が厳しいため、まずは該当する専門工事から取得し、実績を積んでから追加取得を検討するのが現実的です。行政書士や建設業専門のコンサルタントに相談することで、ミスマッチを防ぎ、スムーズな許可取得につながります。