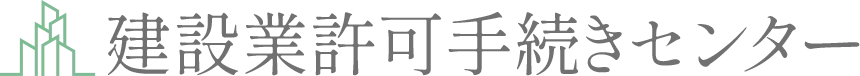建設業許可について
2025/05/05
建設業許可とは、一定規模以上の建設工事を請け負う際に必要となる「国または都道府県の許可」です。建設業を営むための「営業ライセンス」のようなもので、建設業法に基づいて規制されています。
目次
建設業許可とは?

なぜ建設業許可が必要なのか?
無許可業者による手抜き工事やトラブルを防ぎ、適正な工事と事業運営を確保するためです。発注者(元請や施主)にとっても「許可を持っている=一定の信用がある」とみなされることが多いため、営業面でも有利になります。

許可が必要なケース
建設工事のうち、下記のいずれかに該当する場合には建設業許可が必要です。
建築一式工事:1件あたり1,500万円(税込)以上 または 木造住宅で延べ面積150㎡以上
それ以外の工事(専門工事など):1件あたり500万円(税込)以上
※これより小規模な工事だけを行う場合は「許可がなくても」営業できます(軽微工事に該当)。

許可の種類
建設業許可は、次のように分類されます。
1. 国土交通大臣許可と都道府県知事許可
区分説明
国土交通大臣許可・・・複数の都道府県に営業所がある場合に必要
都道府県知事許可・・・1つの都道府県内にしか営業所がない場合
2. 一般建設業許可と特定建設業許可
区分説明
一般建設業・・・元請・下請問わず受注できますが、1件あたり下請け総額5,000万円未満(建築一式は8,000万円未満)の工事を請け負う場合
特定建設業・・・下請に出す総額が5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上)の場合に必要(主に大規模元請業者向け)
一般と特定の選び方

一般建設業と特定建設業の違い【概要】
| 区分 | 一般建設業 | 特定建設業 |
| 主な対象者 | 主に下請や小規模元請業者 | 大規模な元請業者 |
| 下請負契約の規模 | 1件あたり5,000万円未満(建築一式は8,000万円未満) | 1件あたり5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上)を下請に出す場合 |
| 技術者要件 | 営業所技術者がいればOK | 一級資格や指導的実務経験者が必要 |
| 財産要件 | 資本金や自己資本額の制限なし(ただし500万円以上の資金力必要) | 純資産額4,000万円以上など厳しい財産基準あり |

詳しく見る:どういうときに「特定建設業」が必要?
たとえば、以下のようなケースでは特定建設業の許可が必要になります。
あなたが元請業者で、1つの建設工事に対して下請業者に総額5,000万円以上(建築一式なら8,000万円以上)の工事を発注する場合。
つまり、「大規模な工事の元請けとして、工事全体の管理を行い、かつ多額の工事費を他社に任せる」ような場合は、発注者保護の観点からも、より厳しい審査が必要とされているのです。

営業所技術者・経営責任者の要件の違い
| 要件項目 | 一般建設業 | 特定建設業 |
| 営業所技術者 | 二級施工管理技士や実務経験者でもOK | 一級施工管理技士や高度な実務経験者が必要 |
| 経営業務管理責任者 | 経験年数や役職で要件を満たす必要あり(※2020年法改正により多少緩和) |
同じく必要 |

実務的なポイント
ほとんどの中小企業は「一般建設業」で十分です。
公共工事や大型民間工事の元請けをするなら「特定建設業」も検討する必要があります。
特定建設業は申請や維持が大変なので、「将来的に必要になる見込みがあるか?」を見極めて選びましょう。

一般建設業 or 特定建設業 判断チェックリスト
| チェック項目 | はい |
いいえ |
| 元請として公共工事を請け負いたい(市・県など) | 特定建設業の検討 | 一般建設業でOK |
| 一件の工事で下請業者に5,000万円以上(建築一式なら8,000万円以上)を発注することがある | 特定建設業の検討 | 一般建設業でOK |
| 下請に出す金額が基本的に少額(500万円未満〜2,000万円程度) | 一般建設業でOK | 特定建設業の検討 |
| 自社で完結できる規模の工事が多い | 一般建設業でOK | 特定建設業の検討 |
| 資本金が2,000万円未満、純資産もそれほど多くない(増資予定もない) | 一般建設業でOK | 特定建設業の検討 |
| 一級施工管理技士などの有資格者が社内にいない | 一般建設業でOK | 特定建設業の検討 |
| 将来、大手ゼネコンの下請けやJV(共同企業体)参加を予定している | 特定建設業の検討 | 一般建設業でOK |
具体的な事例
■ 事例①:町の水道設備業者(従業員5名)
自社で施工する工事が中心(下請けに出すことは少ない)
1件あたり300〜1,000万円の工事が多い
→ 「一般建設業」で十分対応可能
■ 事例②:地場ゼネコンとして工事を元請け
民間マンション建設を元請けで受注
配管・内装・電気などを全て下請に出す予定(合計8,000万円)
→ 「特定建設業」が必要(発注額が基準超過)
■ 事例③:将来の成長を見越して
今は500万未満の軽微な工事が多いが、将来的に元請けとして公共工事に進出したい
財務基盤も徐々に整備中、技術者の採用予定あり
→ まずは「一般建設業」で取得 → 将来的に特定へ切り替えが現実的
🔎 アドバイス
一般建設業から始めて、必要に応じて特定建設業へ「許可換え」するのが一般的です。
特定建設業はメリットも大きいですが、維持・更新のコストや要件が厳しいため、事業計画に応じて段階的に検討しましょう。
大臣許可と知事許可違い

大臣許可と知事許可の違い【基本】
「大臣許可」と「知事許可」の違いは、建設業者の営業所の所在地の数と範囲によって決まります。以下で分かりやすく解説します。
| 区分 | 簡単な説明 |
| 国土交通大臣許可 | 2つ以上の都道府県に営業所がある建設業者が必要とする許可 |
| 都道府県知事許可 | 1つの都道府県内だけに営業所がある建設業者が取得する許可 |

「営業所」の考え方が重要!
ここでいう「営業所」とは、単なる事務所ではなく、「常時建設工事の契約を締結できる拠点」です。
たとえば:
兵庫県に本店があり、京都府にも支店(営業所)がある場合 → 大臣許可
兵庫県内のみに本店+支店がある → 兵庫県知事許可
📝【注意】作業現場の仮設事務所、単なる連絡所は「営業所」には該当しません。ただし、黒部ダムの建設現場などは規模の関係から建設業法上の営業所とされるケースがあります。

許可の種類の構成(全体像)
① 許可の区分(営業エリア)
┗ 国土交通大臣許可 or 都道府県知事許可
② 業務の規模(元請として下請へ出す金額)
┗ 一般建設業 or 特定建設業
つまり、許可の種類は「①×②=4通り」あります。
| 区分 | 説明 |
| 知事許可(一般) | 1県内で営業(見積もり、契約締結)し、小規模の工事を行う |
| 知事許可(特定) | 1県内で営業し、大規模な元請工事を行う |
| 国土交通大臣許可(一般) | 複数都道府県で営業し、小規模の工事を行う |
| 国土交通大臣許可(特定) | 複数都道府県で営業し、大規模な元請工事も行う |

どちらが有利?
|
観点 |
大臣許可 | 知事許可 |
| 対象エリア | 全国(営業所を増やしやすい) | 営業所は都道府県内に限定される(工事現場は全国可能) |
| 手続き負担 | やや複雑・審査も広域的 | 比較的簡易(県の判断) |
| 成長余地 | 将来の拠点展開を見据えやすい | 地域密着型に向いている |

建設業許可の種類判定フローチャート
Q1. 営業所(常設拠点)は、複数の都道府県にありますか?
├─ はい → Q2へ進む(国土交通大臣許可が必要)
└─ いいえ → Q3へ進む(都道府県知事許可が基本)
Q2. 今後、下請に5,000万円以上の工事を出す予定がありますか?(建築一式は8,000万円以上)
├─ はい → 【国土交通大臣・特定建設業許可】
└─ いいえ → 【国土交通大臣・一般建設業許可】
Q3. 今後、下請に5,000万円以上の工事を出す予定がありますか?(建築一式は8,000万円以上)
├─ はい → 【都道府県知事・特定建設業許可】
└─ いいえ → 【都道府県知事・一般建設業許可】
例:このフローチャートでの判定イメージ
兵庫県のみで営業しており、500万円~1,500万円の工事が主力
→【知事許可・一般】が最適
東京本社+大阪支店あり、元請として下請に1億円規模を外注予定
→【大臣許可・特定】が必要
建設業許可に必要な営業所技術者について

営業所技術者とは?
営業所技術者(以下「営業所技術者」)は、建設業許可を取得・維持するために各営業所に常駐させる必要がある重要な人材です。以下にポイントを整理して解説します。
営業所において、建設工事の技術的な責任を負う人です。建設業法では、「常勤」かつ「適切な資格・経験を持っている者」が営業所技術者として求められます。
対象となる営業所とは?
「営業所」とは、契約締結や見積業務などを常時行う事業拠点
工事現場の仮設事務所は対象外です。

営業所技術者の要件
【1】常勤性(専任性)
該当営業所に常勤していること(他の会社や現場との兼務不可)
原則、同一人物が複数営業所の営業所技術者にはなれない
社会保険、住民票の住所などで実態確認されることも
【2】資格・経験要件(いずれかを満たせばOK)
| 区分 |
要件(例) |
| 有資格者 | 一級・二級施工管理技士、建築士などの国家資格保有者 |
| 学歴+実務経験 | 大学卒+3年以上、高卒+5年以上の実務経験 |
| 実務経験のみ | 10年以上の実務経験がある者(資格・学歴なしでも可) |
※業種によって必要な資格は異なります(例:電気工事=電気工事施工管理技士、管工事=管工事施工管理技士など)

営業所専任技術者の役割(現場とは異なる)
営業所技術者の役割は、建設業者が営業所において技術的に適正な業務を行えるようにすることです。現場の責任者(主任技術者や監理技術者)とは異なり、営業所に常駐して、社内の技術面を支える立場になります。
|
役割 |
内容 |
| 契約前の技術的確認 | 見積もりや契約内容について、技術的観点からの妥当性を確認する |
| 設計・施工方法の検討 | 工事内容に応じて、技術的アドバイスや施工方法の選定をサポート |
| 技術職員・現場管理者への指導 | 現場に配置される主任技術者・監理技術者への指導・教育を行う |
| 技術力の対外的な証明 | 許可を維持するうえで、「この営業所には一定以上の技術力がある」と証明する存在 |
| 行政対応 | 行政(県や国)からの照会に対し、技術面での説明責任を果たす立場になることも |
建設業許可に必要な経営業務の管理責任者について

経営業務の管理責任者とは?
「経営業務の管理責任者(けいえいぎょうむのかんりせきにんしゃ)」は、建設業許可を取得・維持するうえで非常に重要な役職です。経営面での適格性を担保するための要件で、以前は、「建設業に関して5年以上の経営経験を有する者」が、常勤役員や個人事業主として必ず1人いなければ許可を取得できませんでした。この人が「経営業務の管理責任者(経管)」と呼ばれていましたが、現在(2020年改正以降)は「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するもの」が要件となっています。
認められる体制(代表的なパターン)
|
パターン |
内容 |
| ① 経営経験者が役員にいる | 建設業の経営に関して 5年以上の経験がある人が、法人の役員や個人事業主である |
| ② 経営補佐経験者が役員にいる | 経営業務を補佐した経験が 6年以上ある人が役員である(例:部長や経理責任者) |
| ③ 年数不足の役員経験OR外部人材+支援体制 | 建設業に関する役員経験の年数が不足する者に、他業種での役員経験や経理・労務・経営の3部門のどれかの運営経験を持ったものを登用して、自社のそれぞれの部門での5年以上の経験を持つものを補佐人として補佐させている体制がある。 |

経営経験の証明方法
|
区分 |
必要な書類例 |
| 5年以上の経営経験 | 登記事項証明書、確定申告書、許可証の写し など |
| 6年以上の補佐経験 | 在籍証明書、職務内容の説明書、辞令、組織図など |
実務でのポイント
法人では、常勤の役員であることが必須です(非常勤役員は原則不可)
他業種(建設業以外)の経験では認められないため注意(一部利用できる場合あり)
「経営経験があるが、証明できる書類がない」場合は、実務的にハードルが高くなります

認められる経験の詳細
パターン①:建設業の経営経験5年以上の者(王道パターン)
最も確実・シンプルな方法
「取締役(常勤)」としての勤務が登記簿等で確認できる
兼業している場合、建設業への関与実態が問われることも
必要書類例:
許可業者としての登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
許可通知書の写し
役員でなくても、個人事業主や、営業所の代表者(令3条の使用人)としての経験も同様に扱われます。
パターン②:建設業の経営を補佐した経験が6年以上ある者を常勤役員に配置
補佐経験とは、個人事業主の家族(奥さんや息子さん)が家業を手伝っているような場合に役員に準じているとして経営経験を認める場合です。
法人の場合の「取締役ではなかったが、経理部長・工務部長など経営に近い職務」であった場合も同様に経営経験を認めてもらえます。
「単なる技術者」「現場監督」は補佐経験とはみなされないので注意
必要書類例:
個人事業主の場合は、証明者(建設業者)の確定申告書の専従者欄や賃金欄への記載があるもの、組織図など。
法人の場合、勤務先企業の組織図・職務分掌表
辞令・在籍証明書
経理・予算管理等を行っていた証拠資料 など
パターン③:年数を満たす者がいない場合に、建設業以外の経営経験や自社で役員に準ずる地位で経理・労務・経営の経験を持つ者に、自社の経理・労務・経営の運用経験を5年以上持つ者を補佐人として付ける体制を整備した場合
「実態として、経営業務管理責任者を補佐する者(最大3名)が補佐すること」が条件

執行役員でも経営業務の管理責任者になれる
法改正前は経営業務の管理責任者には役員の中から選ばなければなりませんでしたが、現在では役員等として執行役員でも経営業務の管理責任者になることが可能となりました。
ただし、ハードルは低くありませんので、執行役員でも役員同様に簡単にOK が出るとは思わないようにしてください。
要件
①取締役会設置会社であること
②取締役会の決議を経て取締役会もしくは代表取締役から建設業に関する具体的な権限移譲を受けていること
③建設業を所管する他の執行役員がいないこと

経営業務の管理責任者がいなくなったら
経営業務の管理責任者は建設業許可の要件の一つであることから、いなくなれば許可は維持できなくなります。建設業法にも要件の欠落があった場合には許可を取り消さなければならないとの条文があるぐらいです。
よくある誤解に、届け出をしなければ許可は取り消されないから、その間に次の要件を満たした人を連れてくればよいといった考えをする方がいますが、それは悪手です。そもそもいなくなった時点で許可は形骸化しており、実質効力を失っています。さらに許可の要件者に変更があった場合は14日以内に届け出義務がありますので、それをせずに、形骸化した許可で営業を続けたということで悪質性も指摘されかねません。