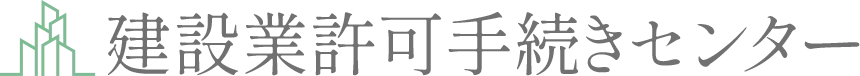建設業許可に必要な営業所専任技術者の要件とは?
2025/04/25
建設業許可を取得する際、営業所専任技術者の配置は欠かせない要件の一つです。本記事では、建設業許可をスムーズに取得するために知っておきたい専任技術者の条件や資格について詳しく解説します。特に、技術者の経歴や実務経験がどのように評価されるのか紹介し、許可取得を目指す方々が直面する疑問を解消します。
目次
営業所技術者の役割と建設業許可取得の重要性

専任技術者が果たすべき重要な役割
建設業法で専任技術者という場合違う二つの役割を表していることがあります。一つは建設業許可を取得する際必要な営業所専任技術者、もう一つは現場に配置される現場配置技術者になります。
専任技術者が在籍していることで建設業者は技術的な担保が保証されているといっても過言ではありません。
現在は少子高齢化も相まって、建設技術者の人手不足が叫ばれています。これは、多くの建設業者が抱える共通の課題であり、その解決策として、専任技術者の計画的な育成が挙げられます。

建設業許可における営業所専任技術者の必要性
営業所専任技術者は許可上の企業の技術的な信用を裏付ける重要な役割を担っています。設置目的は許可を受けた営業所で契約する建設工事に関する請負契約の適正な締結及びその履行の確保です。ですから通勤ができないもの、他の仕事を持ついわゆる非常勤のもの、他法令で専任を求められる業務(例外あり)に従事する者などは営業所専任になれません。同じ理由から、現場専任を求められる後掲の現場配置技術者(のうち一定金額以上の受注額の工事に対して)として配置ができないとされていますし、一定額以下であったとしても、営業所専任技術者を現場配置技術者にすることは望ましくないとされています。

現場に配置が求められる現場配置技術者
もう一つ、現場配置される技術者のことも専任技術者と呼びます。こちらの現場配置技術者は、現場での指導や技術的な助言を行い、工事が適切に進行するように監督します。また、彼らは工事の品質や安全性を確保し、法律や規制に違反しないよう現場を監理します。特に、建設業許可においては、専任技術者を置くことで適正な工事が行われることを期待していますので、企業にとっては適切な人材の配置が不可欠です。

法的要件としての専任技術者
営業所専任技術者は建設業許可において法的に求められる要件の一つであり、許可を受けるためには、特定の資格・経験を持つ技術者が在籍していることが不可欠です。
言い換えると許可業者には必ず許可を受けた建設業に対応した技術者が在籍し、工事を監理できるということを表していることから信頼性が担保されています。
建設業許可に必要な専任技術者の資格とは

認定されるべき資格の種類
専任技術者といっても二つの意味があるとお伝えしましたが、この二つは役割は違いますが、求められる要件は同じになります。
求められる要件としては資格と経験になります。
一般的に認定される資格には、建設業法で定められる各種の施工管理技士があります。また、そのほかに他法令に基づいて認定されている資格のうち国土交通大臣が同等の技量があると認めたもの、一級または二級の建築士や電気工事士、各種技能士などがあります。
それぞれの資格は、特定の業種に応じた専門的な技術知識を有することを証明するものとされています。
次にこれら資格の取得が困難な業種もあります。例えば機械器具設置工事や清掃施設工事などがあげられます。これら業種は技術士の資格が求められています。
また、施工管理技士などで対応可能な業種であっても一定程度の現場経験があるのであればそれを実務経験として資格と同様にみなすことが可能です。

専任技術者に求められる学歴
専任技術者として認定されるためには、資格の取得が一番です。しかし、現場に従事しながら資格を取得することは容易ではありません。そのため、実務経験で技術者要件を充足するといったことも少なくありません。
その場合には学歴も重要な要素となります。
建設業法では10年以上の実務経験が認められると専任技術者の要件が認められます。この10年という期間を短縮できるのが指定学科卒業という学歴です。つまり専門的な知識があるのであれば、経験年数が短くてもよいということです。
昔は電気科、機械科、土木科など一目でどんな学科かわかったものですが、最近では学科名だけではわからないケースも増えてきました。そのため具体的には履修科目がわかる成績証明書などを提出し、指定学科として認められるかを許可行政庁に確認することとなります。
確認の上認められると、大学の指定学科卒は卒業後3年、高校の指定学科の場合は卒業後5年の経験があれば資格者要件を認められます。
これに加え、各種施工管理技士の技師補以上の資格を取ることで、指定学科卒と同様に(土木施工管理技士であれば土木に関する学部、建築施工管理技士であれば、建築学に関する学部といった具合に)扱われる制度ができました。
この場合は資格取得後の経験年数が短縮されるため、早く資格取得できればメリットが大きくなります。

資格取得のためのステップ
建設業許可を取得するにあたって、専任技術者として認定されるためには、まずは適切な資格を取得することが重要です。試験はすぐに取得できるわけではなく、1次試験と2次試験に分かれており、実施される時期も決まっているので、申し込みから合格発表までには年単位の時間がかりますので注意が必要です。
まず、希望する資格の受験資格を確認し、申込期間と試験の実施日、必要な書類や手続きの確認をしましょう。次に、試験対策をしっかりと行い、試験に臨みます。日常の仕事をこなしながらの受験勉強は大変だと思いますが、合格しないと勉強は続きます。まずは合格し試験勉強からの解放を目指して頑張りましょう。
合格後は、資格証の発行を受け、建設業許可申請の際に活用します。また、資格取得後も新たな法令や技術の変化に対応できるよう、継続的な学習を心がけることが重要です。これにより、専任技術者としての信頼性が高まり、許可取得がスムーズに進むことが期待できます。

実務経験と資格の関係性
建設業許可の専任技術者として認定されるためには、資格のみならず実務経験も重要な要素となります。資格があることで技術的な基礎知識を証明できますが、それに加えて一定の実務経験が必要となる場合があります。特に、指定建設業(土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園)以外の監理技術者となるためには指導監督的実務経験が必要とされることから、経験年数や実績として、過去のプロジェクトにおける役割や従事期間が評価されます。この指導監督的実務経験は元請の技術者としてその工事全般を指導監督的立場で差配した経験をいいますので、それぞれの工事においては一人しか認められません。
したがって、指導監督的立場を証明するためには、その内容をしっかりと記録し、証明できる形にしておくことが求められます。このように、資格と実務経験が相互に補完し合うことで、監理技術者としての認定が受けやすくなります。

資格の更新と保有の重要性
建設業許可を維持するためには、営業所専任技術者の在籍が必須とお伝えしましたが、前述したように資格を充足していた者がいなくなれば許可は取り消されます。そのため資格に期限のある場合その更新をしなければどうなるのか?ということが問題になります。
一般的な資格に関しては有効期限がないものが多いため、問題になることはありません。監理技術者証なども期限がありますが、こちらについては期限が切れていても証明になると通達が出されています。
ただし注意が必要なのが大臣認定の場合です。現在では対象者がかなり少なくなっていますが、指定建設業(土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園)においては一級の施工管理技士資格がなければ監理技術者登録ができませんが、そのように決まる前から業をしている方の救済として大臣認定されていることがあります。その認定は切れてしまうと効果がなくなるものですので、更新期限を忘れて許可が取り消されるといったことがないようにしましょう。
営業所専任技術者の配置について

専任配置の要件緩和について
令和6年12月13日の改正で営業所専任技術者が専任性を要する現場の配置技術者となることができるようになりました。
今までは専任性を要しない規模の現場であれば望ましくはないけれども、それを禁止したら一人親方などは工事が取れないとなりかねないため、基準もあいまいながら黙認されていた感がありましたが、この度1現場に限り要件を充足できれば4,000 万円(建築一式 8,000 万円)以上の工事であっても 1 億円未満 (建築一式 2 億円未満)の工事の場合は一定の要件を満たすことで専任技術者と監理技術者等として兼務 可能となります。

求められる要件とは
【営業所技術者の兼務可能な要件】以下のとおりです。
◆工事現場について
① 営業所技術者の所属営業所で請負契約が締結された建設工事であること
② 請負金額が 1 億円未満(建築一式は 2 億円未満)の工事であること
③ 現場数の上限が 1 現場までであること(営業所専任+1現場まで兼任可能)
④ 営業所と工事現場間の距離が、1 日で巡回可能かつ移動時間が片道おおむね 2 時間以内であること
⑤ 工事現場以外の場所から ICT 技術を活用して、現場状況を確認することができること
◆施工体制について
⑥ 工事全体の下請次数が 3 次以内であること
⑦ 工事現場に連絡員として技術者を配置すること
⑧ 工事現場の施工体制が CCUS 等により把握可能であること(施工体制を確認できる情報通信技術については、 遠隔から現場作業員の入退場が確認できるシステムであれば問題ない)
◆運用について
⑨ 人員の配置を示す計画書の作成、現場据置及び保存(電磁的記録媒体による措置も可能)
上記要件はすべて満たすことが求められていますので経営者の方はよく理解をしてください。

異なる業種における配置の事例
建設業許可の取得において、営業所専任技術者の配置は業種ごとに異なる要件が求められます。例えば、土木工事業では土木工学に関する高度な知識と経験が必要とされ、建築工事業では建築学の知識と現場経験が求められます。それぞれの業種において、専任技術者の経歴や実務経験がどのように評価されるかを理解することが重要です。また、複数の業種を扱う企業においては、各業種の許可要件を満たすために複数の技術者を配置する必要が生じる場合もあります。これは、各業種ごとの法令遵守を確実にするための重要なステップです。さらに、各自治体によっても若干の配置基準が異なるため、地域に密着した情報収集と専門家への相談が成功のカギとなります。

営業所技術者の配置
営業所専任技術者の配置は、適切な技術者の選定から始まります。この際、建設業許可に関する法律や業種別の要件を十分に理解していることが求められます。まず、候補者の資格証明書や実務経験を確認し、業種ごとの要件を満たすかどうかを見極めます。
資格がある形式は大切ですが、実際に現場の施工管理ができる知識と経験を持った技術者の配置が何よりも重要であるということを心掛けることが重要です。また、技術者の継続的な教育や資格の更新を行うことで、最新の技術と法律に対応できる体制を維持することが求められます。

出向者、期間雇用者でも営業所技術者になれる
営業所技術者と現場に配置される技術者ですが、この両者に求められる要件に違いがあります。それは「直接的かつ恒常的な雇用関係」があるかどうかです。
建設業法第7条に定められる営業所技術者に関しては、「雇用契約等により事業主体と継続的な関係を有し、休日その他勤務を要しない日を除き、通常の勤務時間中はその営業所に勤務し得るもの」(大成出版社建設業法解説より)とされている
一方26条に定める現場配置技術者の場合は前述建設業法解説の中で、直接的な雇用関係は技術者と所属建設業者との間に第三者の介入する余地がないことを求めていることから、在籍出向、派遣社員に関しては直接的な雇用関係がないとしている。
また、恒常的雇用関係に関しては「一定の期間にわたり当該建設業者に勤務し、日々一定時間以上職務に従事することが担保されていること、技術者と所属建設業者双方の持つ技術力を熟知し、組織として有する技術力を十分活用できることが求められている(要約)」ため工事期間だけの雇用ではだめで、ある程度(公共工事の場合は入札日の3か月前より。公共工事を含め工期中に切れてしまう雇用期間は問題だが、一般的には1年以上を求められることが多い)の期間継続的に雇用されていることが求められている。
そのため、営業所技術者に関しては出向者や期間雇用者に関しても選任可能とされています。
ただ、条文上明確に言葉を使い分けられているわけでないので、両方に直接的かつ恒常的な雇用関係を充足する技術者を選任できる体制を作っておくことが望ましいのは言うまでもありません。
専任技術者に求められる経歴と経験の証明方法

専任技術者に求められる要件
専任技術者は建設業者の技術力の裏付けの根拠です。
そのため技術力を証明するものとして各種資格もしくは一定の工事業種ごとの経験が必要になります。このうち資格に関しては資格者証や合格者証で証明は容易ですが、一定の実務経験はそういった資料がないため、期間、所属、内容などをどう証明していくかが重要になります。

証明書類の準備に関する注意事項
建設業許可を取得するためには、営業所専任技術者の資格や実務経験を証明するための書類が必要です。この際、適切な証明書類を準備することが不可欠です。何を証明するかといえば、いつからいつまでの期間どこの会社(現場)で、どんな工事にどんな役割でかかわったのか。です。
まず、いつからいつまでどこの会社でについては、過去の社会保険の加入履歴や給与明細などがあれば信用性が高いでしょう。
次にどんな現場でに関しては、当時の所属会社が許可業者であれば当時の決算変更に添付していた工事経歴書や、工事契約書、契約書で内容がわからなければ、工事内容のわかる仕様書や計画図面などがかんがえあれるでしょう。
そしてどんな役割で現場に携わったのかそれにより現場経験をした業種が何かが決まります。土木一式の工事で下水管の埋設後の穴埋め戻しプラスアスファルト補修であれば、土木一式もしくは、とび土工や舗装工事などが考えられます。同じような工事でも上水配管なら水道施設工事なども。
そして一定期間その業種の工事を経験したという形の実務経験証明書を作成し、前述資料をその裏付け資料として準備します。

実務経験期間は原則重複できない
実務経験での技術者認定は複数業種の認定が可能です。ただし、それぞれの期間は重複できません。例えば管と電気を同じ期間に経験していても管の実務経験期間として使った期間は、電気の実務経験は認められないといった具合です。ですから複数業種の認定を希望する場合はその年数に応じた期間の資料の準備が必要になります。
例外は平成28年5月以前の解体工事についてはとび土工の工事にも使用が可能なのと、複数業種に係る実務経験として定められている大工工事の建築と大工、大工と内装。とび・土工工事業の土木ととび、とびと解体。屋根工事業の建築と屋根などで両方の業種を12年以上経験し、そのうち8年以上該当する専門工事の経験を積んだものは2年間は重複できるといったものがあります。

証明が難しい場合の解決策
営業所専任技術者の立場で実務経験を証明することが難しいケースも少なくありません。特に、古すぎて正式な資料が残っていないものや、当時の会社が倒産したりして証明してくれる当時の会社役員の所在が不明瞭な場合には、証明が困難です。しかし、建設業許可を取得するためには、これらの問題を解決する必要があります。まず、過去の同僚や上司からの証言を得ることが有効です。彼らに直接連絡を取り、実務経験を裏付ける証言書を作成してもらうことで、証明の一助となるかもしれません。また、過去の契約書や業務報告書の再調査、当時のメモや日記など使えるかもしれません。これらの資料をもとに、役所に事情を説明するとともに実務経験を整理し、推認してもらうことが重要です。最後に、行政書士や専門家のサポートを受け、証明書類の作成や申請プロセスを効率的に進めることも考慮しましょう。これにより、建設業許可の取得が円滑に進む可能性が高まります。