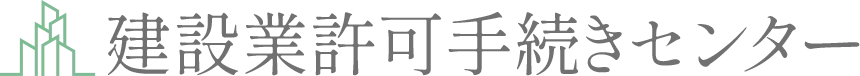建設業許可事務ガイドライン 解説
2025/04/19
「建設業許可事務ガイドライン」とは、国土交通省が都道府県などの許可行政庁に対して示している建設業許可に関する運用基準・審査手続きの統一的な指針です。正式には「建設業法に基づく建設業許可事務ガイドライン」と呼ばれ、建設業者の申請に対して、行政がどのように判断・審査すべきかを定めた文書です。
目次
ガイドラインってそもそも何?

【ガイドラインの主な役割】
① 許可審査の透明性と公平性の確保
都道府県や地方整備局ごとにばらつきが出ないように、許可の判断基準を明文化し、統一的に運用することを目的としています。
② 実務における解釈・判断基準を明示
例えば、
「経営業務の管理責任者」の経験年数のカウント方法
「専任技術者」が複数業種を兼ねる場合の要件
「営業所」や「常勤性」の具体的な確認方法
など、実際に迷いやすい判断基準を具体的に記載しています。
③ 制度改正に対応する実務運用の指針
建設業法が改正されるたびに、このガイドラインも改訂されます。最近では、2023〜2024年にかけての改正内容(専任技術者の兼務緩和など)も反映されています。

建設業者にとってのガイドライン
ガイドラインを理解すれば、許可取得・維持のための正しい対策ができる
曖昧だった基準(例:実務経験の証明方法など)について明文化された判断材料が得られる
行政書士や担当者とのやり取りの中で、根拠を持って相談・交渉ができる
簡単に言えば、「建設業許可に関する審査の“ルールブック”」です。行政だけでなく、申請する事業者側にも非常に有用な資料といえます。

リスク管理としての建設業許可の重要性
建設業界において、リスク管理は企業の持続可能な発展を支える重要な要素です。そして、建設業許可はその中核を成す要素として機能します。許可取得は、事業を合法的に進めるための第一歩であり、クライアントやステークホルダーに対する信頼性を確保します。許可を持つことで、法的なトラブルを未然に防ぎ、事業の安定性を高めることができます。また、許可の維持は企業の財務的・技術的基盤がしっかりとしている証でもあり、リスクを最小限に抑えるための重要な手段です。さらに、許可の更新や新規取得に際しては、常に最新の法規制を遵守することが求められ、これが結果的に企業のガバナンスやコンプライアンスの向上につながります。

市場競争力維持に必要な建設業許可
建設業界における市場競争力を維持するためには、建設業許可の取得が不可欠です。許可を持たない企業は受注機会を大幅に制限されることになります。許可は、企業が法的に適正かつ信頼できるパートナーであることを証明し、市場での競争力を高めるための重要な要素です。さらに、許可を取得している企業は、技術力や経営力が評価され、顧客からの信頼を得ることができます。市場環境が厳しくなる中で、許可を持つことが競争優位性を保つカギとなり、企業の持続的な成長を可能にします。加えて、許可の取得や更新には専門的な知識と経験が求められるため、プロフェッショナルのサポートを受けることが成功への近道となります。
建設業許可に必要な「5つの要件」を押さえる

建設業許可を取得するためには、法律で定められた5つの要件をすべて満たす必要があります。これは、個人事業主でも法人でも同じです。以下に、建設業者にとって重要な「5つの要件」を、実務に即してわかりやすく解説します。

要件①:経営業務の管理責任者(経管)がいること
✅ 要件①:経営業務の管理責任者(経管)がいること
■ どんな要件?
事業の経営を適切に管理できる「責任ある人」が必要です。これが「経営業務の管理責任者(通称:経管)」です。
■ 要件のポイント
法人なら役員、個人事業なら本人が該当します。
過去に 一定年数以上、建設業の経営経験(役員や事業主としての経験)が必要です。
要件としては
建設業者での5年以上の役員経験(個人事業主経験)
■ よくある課題
建設業以外の他業種の経験ではNG。
経営経験を「証明する書類」がないと認められない(登記簿・確定申告書など)。

要件②:専任技術者がいること
■ どんな要件?
各営業所に、一定の資格や経験を持つ技術者が常勤していることが必要です。
■ 要件のポイント
「建設業の専門性」を示すために必要。
専任技術者は原則一人一業種。
資格保有か、実務経験のどちらかで要件を満たします。
| 方法 | 条件 |
| 資格 | 1級・2級施工管理技士、建築士など |
| 経験 | 10年以上(学歴により短縮可)の実務経験 |
■ よくある課題
資格証の写しだけでは不十分な場合もあり、原本提示が求められることも。
令和6年改正により、現場兼務が一部緩和されましたが、条件付きです。

要件③:誠実性があること
■ どんな要件?
過去に違法行為をしていない、ルールを守って営業できる会社かどうかが問われます。
■ 要件のポイント
虚偽申請、建設業法違反の経歴があるとNG。
役員や使用人(支店長など)も含めて、誠実な経営が求められます。
■ よくある課題
他業種、他法令での行政処分歴があっても、内容次第では問題になることがあります。

要件④:財産的基礎があること
✅ 要件④:財産的基礎があること
■ どんな要件?
建設工事を請け負ったときに、途中で資金が尽きないように、経済的な安定性を証明する必要があります。
■ 要件のポイント
一般建設業:自己資本500万円以上、または資金調達能力があること
特定建設業:さらに厳しく、純資産2,000万円以上などの基準があります
■ よくある証明書類
貸借対照表(直近の決算書)
預金残高証明書
金融機関の融資証明書
■ よくある課題
起業直後や赤字経営では要件を満たせないことがある。
残高証明で証明した場合、5年以内の業種追加には残高証明が都度必要になることがある。

要件⑤:欠格要件に該当しないこと
✅ 要件⑤:欠格要件に該当しないこと
■ どんな要件?
申請者(法人では役員や使用人)が、法令違反や重大な経歴問題を抱えていないかをチェックされます。
■ 主な欠格事項(例)
禁固以上の刑を受けて5年経過していない
破産して復権を得ていない
暴力団員やその関係者
許可取消処分を受けて5年以内
■ よくある課題
元役員や取締役などが過去に処分を受けていた場合、間接的に影響を受けることもある。
法人の「表に出てこない実質的経営者」も調査対象になりうる。
5つの要件はすべて揃っていないと許可は下りない!
この5つの要件はすべて満たさないと申請しても不許可になります。特に経歴や財産面の証明資料が重要なカギになります。申請前に、行政書士などの専門家と相談しておくことが成功のポイントです。
経営業務の管理責任者(経管)とは何か?

建設業許可を取得するためには、「経営業務の管理責任者(以下、経管)」が建設業の主たる営業所に1名以上、常勤していなければなりません。この制度の目的は、建設業という専門性が高く法的責任も大きい業種において、十分な経営経験を持つ人物が経営に関与することで、適正な事業運営を保証することにあります。

経営業務の管理責任者の定義と役割
経管とは、過去に一定年数以上にわたって建設業の経営業務を行ってきた人のことです。単なる事務職員や現場監督ではなく、「経営者としての判断や管理を行っていた」ことが求められます。つまり、資金繰り・契約・人事・安全管理など、会社運営全般に責任を持っていた立場であったことが必要です。
この人物が常勤することで、役所は「この会社は建設業を安定的かつ責任を持って運営できる」と判断します。経営未経験の素人が突然起業し、公共工事や大規模案件を請け負っても適切に遂行できないリスクを避けるための制度です。

要件を満たすための経歴とは?
経管の経歴は、下記のようなケースで要件を満たします。
| 経歴の内容 | 必要な年数 |
|
法人の常勤役員としての建設業の経営経験 個人事業主(建設業)としての経営経験 |
5年以上 |
| 令三条の使用人 | 5年以上 |
| 建設業の経営を補佐した経験 | 6年以上 |
| 執行役員として建設業を業務執行した経験 | 5年以上 |
| 建設業以外の役員経験+建設業の役員経験※ | 建設業での役員経験2年以上で通算5年以上 |
| 建設業者での役員に次ぐ職責で人事・経営・経理の経験+建設業の役員経験※ | 建設業での役員経験2年以上で通算5年以上 |
※は下記「最近の緩和措置(補佐経験制度)」参照
ポイントは「建設業の経営」に関与していたかどうかです。他業種(飲食業や小売業など)の経験では代替できません。経営の実態があり、常勤で判断を行っていたことが重要です。

経管を証明するための資料とは?
役所は口頭での説明だけでは経営経験を認めてくれません。以下のような証明書類の提出が必要です。
登記簿謄本(役員としての就任期間が記載されている)
確定申告書(個人事業主の場合)
建設業許可の履歴がある場合は、その写し
契約書、請求書、決算書などの実務資料(場合による)

最近の緩和措置(補佐経験制度)
令和2年(2020年)からの制度改正により、経管の「補佐経験」が認められるようになりました。これは、経管経験者のもとで経営補佐的な立場にあった者(部長、支店長など)でも、一定の条件を満たせば経管になれるという制度です。
この措置により、5年の期間を満たさない場合でも補佐的業務を処理する立場にあった方が経管に就く道が開けました。ただし、補佐経験は通常の経管よりも厳格に審査される傾向があり、特例になるため十分な事前打ち合わせが必要になります。

経管の配置で注意すべきポイント
経管は常勤性が必要です。他の会社と兼務している、遠隔地にいるといった場合はNGとなります。
社会保険の加入状況や勤務実態も確認されるため、名義だけの経管は認められません。
経管を退任した場合や変更した場合には、2週間以内に変更届が必要です。
経管がいなくなると、建設業許可は維持できません。そうならないためにも常に要件者がいるような人事を考える必要があります。
■ まとめ
経営業務の管理責任者は、建設業者としての「信頼性・安定性」を示す重要な要件です。申請の際には、ただ経歴を並べるだけでなく、役所が納得できる客観的な証明資料を添付しなければなりません。また、令和以降の法改正で緩和されたとはいえ、審査は依然として厳格です。
「うちは経管要件を満たせるのか?」「証明書類はどれが適切か?」と迷ったら、経験豊富な行政書士に相談するのが確実です。経管の適格性をクリアすることが、建設業許可取得の第一歩となります。
専任技術者(専任)の要件と証明方法

営業所専任技術者とは何か?
建設業許可を取得するためには、「営業所ごとに1名以上の専任技術者」を配置することが法律で義務付けられています。この制度の目的は、建設業を営む拠点(営業所)に、専門的な技術力・知識を持った人材が常駐していることを確保し、工事の品質や安全を担保するためです。
つまり、単に事務所があるだけではなく、そこに工事内容を理解し技術的判断ができる責任者が存在していることが求められています。

専任技術者の「専任」とは?
専任とは、次の2つの条件を満たしていることです。
その営業所に常勤していること
他の事業所や他の会社と兼務していないこと
例えば、週に2日しか出勤しない、現場ばかりで営業所にいない、他の法人の役員を兼ねているといった場合は「専任」として認められません。
令和6年(2024年)の法改正により、一部の要件を満たせば、専任技術者が現場代理人と兼務することも認められるようになりましたが、次のような条件があります。
■ 現場兼務が認められるケース(2024年改正)
◆工事現場について
① 営業所技術者の所属営業所で請負契約が締結された建設工事であること
② 請負金額が 1 億円未満(建築一式は 2 億円未満)の工事であること
③ 現場数の上限が 1 現場までであること(営業所専任+1現場まで兼任可能)
④ 営業所と工事現場間の距離が、1 日で巡回可能かつ移動時間が片道おおむね 2 時間以内であること
⑤ 工事現場以外の場所から ICT 技術を活用して、現場状況を確認することができること
◆施工体制について
⑥ 工事全体の下請次数が 3 次以内であること
⑦ 工事現場に連絡員として技術者を配置すること
⑧ 工事現場の施工体制が CCUS 等により把握可能であること(施工体制を確認できる情報通信技術については、 遠隔から現場作業員の入退場が確認できるシステムであれば問題ない)
◆運用について
⑨ 人員の配置を示す計画書の作成、現場据置及び保存(電磁的記録媒体による措置も可能)
つまり、全面的に自由になったわけではなく、適用できるかどうかは慎重な判断が必要です

専任技術者になるための要件(資格 or 実務経験)
専任技術者になるには、次のいずれかの条件を満たしている必要があります。
✅ A. 技術資格を持っている場合(資格者要件)
多くの専任技術者は、次のような国家資格を有していることで要件を満たします。
| 業種 | 主な資格 |
| 建築一式工事 | 一級・二級建築士、1級・2級建築施工管理技士 |
| 土木一式工事 | 1級・2級土木施工管理技士 |
| 電気工事 | 1級・2級電気工事施工管理技士、電気主任技術者など |
この方法のメリットは、資格証明書の写し(免状など)を提出するだけで要件を満たせる点にあります。審査も比較的スムーズです。
ただし、注意点として「資格取得後、5年以上の実務経験が必要な場合」や「学科試験合格だけでは不十分」なケースもあるため、取得状況を確認する必要があります。
✅ B. 実務経験で要件を満たす場合(経験者要件)
資格を持っていない場合でも、一定年数以上の実務経験があれば専任技術者として認められることがあります。
| 最終学歴 | 学科 | 必要な実務経験年数 |
| 大学・短大・高専卒 | 指定学科 | 3年以上 |
| 高校卒 | 指定学科 | 5年以上 |
|
高校卒指定学科以外 学歴なし・中卒など |
不問 | 10年以上 |
この場合の「実務経験」は、その業種に該当する工事の施工に直接関わった経験である必要があります。単なる補助作業や事務作業では認められません。
🔍「指定学科」とは?
国土交通省が指定する、建設工事に関する知識を体系的に学んだと認められる学科です。例えば「土木工学科」「建築学科」「設備工学科」などが該当します。それ以外の普通科、商業科などは「指定外」として扱われ、実務経験が10年以上必要になります。

実務経験をどう証明するか?
実務経験によって要件を満たすには、「いつ・どこで・どんな工事に関わったのか」を証明する書類の提出が必要です。これが非常に重要かつ難しい点です。
■ 提出すべき証明資料の例
工事経歴:建設業者での経験の場合所属会社の実績を証明
契約書や注文書、請求書:工事内容と本人の従事を証明
在籍証明:法人の場合は社会保険強制加入なので社会保険の加入履歴証明書、加入証明で証明できない個人事業に勤務の場合は、出勤簿、給与明細、源泉徴収票:その会社で働いていたことの証拠
実際には、数年前の資料を揃える必要があり、元勤務先が廃業している場合や資料が残っていないケースでは、原則は不可ですが、行政側と個別相談のうえ「第三者証明」などで対応してもらえることもあります。

専任技術者の配置における実務上の注意点
● 他の会社・営業所と兼任できない
専任技術者は、「一人一営業所」が原則です。他社や別の営業所と兼任することはできません。法人であれば「役員兼技術者」というパターンも可能ですが、その場合も常勤性が問われます。
● 書類の整合性が重要
社会保険の加入履歴や勤務状況などと、申請書の記載内容に矛盾があると、要件不適合と判断されることがあります。過去の工事実績をまとめる際は、一貫性のある書類整理が大切です。
● 技術者が退職したら、速やかに後任の配置が必要
専任技術者が退職・異動した場合は、2週間以内に変更届を提出する必要があります。(選任は退任時)これを怠ると、無許可営業とみなされるおそれがあります。
財産的基礎の確認方法とその実務

建設業許可を取得・維持するためには、「財産的基礎があること(経営の安定性)」が法令上の要件のひとつとされています。この要件は、建設工事という高額で長期間にわたる業務を、途中で資金不足にならず責任を持って遂行できる体力があるかを判断するために設けられています。
以下では、財産的基礎の確認方法と実務対応について、わかりやすく丁寧に解説します。

財産的基礎とは?
建設業を行う上で、資金不足により工事を途中で放棄するような事態を防ぐため、国や都道府県は「経済的に一定以上の安定性があること」を求めます。これを満たしていることを書類で証明しなければ、許可は認められません。

許可の種類による基準の違い
建設業許可には「一般建設業」と「特定建設業」があり、それぞれで求められる財産要件が異なります。
| 許可区分 | 財産的要件(法人または個人事業) |
| 一般建設業 | 下記①または②のいずれかを満たすこと |
| 特定建設業 | 下記③〜⑤のすべてを満たすこと |
■ 一般建設業の財産要件
① 自己資本が500万円以上ある
決算書(貸借対照表)における純資産が500万円以上であることが必要です。
② 500万円以上の資金調達能力がある
直近の預金残高証明や、金融機関からの融資証明書などで、すぐに使用可能な資金があることを証明します。
※赤字企業や創業直後で自己資本が少ない場合でも、この方法で要件を満たせる場合があります。
■ 特定建設業の財産要件(かなり厳格)
欠損(赤字)が資本金の20%を超えていないこと
流動比率が75%以上であること(流動資産 ÷ 流動負債 × 100)
資本金が2,000万円以上であること
自己資本が4,000万円以上であること
経営業務の管理責任者が財務内容を把握している体制であること
※要件を一つでも満たさない場合、特定建設業許可は取得できません。

証明に必要な書類
実際に財産的基礎があることを確認するには、以下のような書類の提出が求められます。
■ 決算書(法人の場合)
貸借対照表
損益計算書
株主資本等変動計算書(新会計基準)
注記表(中小企業会計指針に基づく場合)
法人は直近1期分(多くは1年以内)の決算書を提出する必要があります。
■ 預金残高証明書(個人事業・創業間もない法人向け)
銀行発行の残高証明書(500万円以上)
発行日から1ヶ月以内のものが必要(兵庫県の場合)
名義は申請者本人または法人名義でなければ無効
■ 融資証明書(ほとんど利用されない)
金融機関の発行した借入可能証明、または借入申込受理証明書
金額明記があり、返済条件も記載されたもの

実務上の注意点と対処法
● 創業直後の法人・個人事業主は要注意
創業直後は決算書がないか、純資産がほぼゼロというケースが多く見られます。この場合は、自己資金を増やして預金残高証明を取得する方法が一般的です。
👉 例:500万円を一時的に入金して、金融機関に残高証明書を発行してもらう。
● 赤字決算企業は専門家と相談
赤字決算が続く場合や、債務超過となっている場合、自己資本額が要件を満たさない可能性があります。その場合は、資本増資や役員借入金の増加など、決算書上の調整が必要となることがあります。
👉 例:債務超過を解消するため、代表者から会社への増資を行う。
● 決算期が過ぎている場合は最新のものを提出
建設業法では決算終了後4か月が決算変更届の提出期限になっています。しかし、申請時点で4か月は超えていないが前期決算を超えている場合、最新の決算書の提出が求められることもあります。

財務基盤の確認を怠るとどうなる?
財産的基礎を証明できない場合は、建設業許可が不許可になります。また、既に許可を得ている場合でも、更新時に財産状況が悪化していれば更新ができないこともあり得ます。
さらに、特定建設業を維持するためには、毎年提出する「決算変更届」で常に要件を満たし続けているかが審査されるため、継続的な財務管理が重要です。
✅ まとめ
| 内容 | 一般建設業 | 特定建設業 |
| 自己資本 | 500万円以上 | 4,000万円以上 |
| 資本金 | 制限なし | 2,000万円以上 |
| 流動比率 | 審査されない | 75%以上必須 |
| 証明方法 | 決算書 or 預金残高証明 | 決算書+要件全て |
財産的基礎の要件は、書類上の数値で明確に判断されるため、事前準備と確認が何より大切です。特に創業間もない方や赤字企業の場合、適切な資金対策・証明資料の取得が許可取得のカギを握ります。難しい場合は、行政書士や税理士など専門家に相談することで、実現可能な対策を一緒に検討することができます。
営業所の実態確認とは何か?

営業所の実態確認とは、建設業許可を申請する際に、その営業所が「形式だけでなく、実際に業務を行っている拠点かどうか」を確認する審査のことです。建設業許可を取得するうえで、営業所の実在性・専任性は非常に重視されるポイントであり、不備があると不許可や是正指導の対象になる可能性があります。

なぜ「営業所の実態確認」が重要なのか?
建設業許可では、営業所ごとに専任技術者を配置することが義務づけられています。このため、営業所の存在が「書類上だけ」であると、配置要件が満たされていないと判断され、不許可になるおそれがあります。
形式だけで設置された“ペーパーオフィス”や、自宅・他社との共用スペースで実態がないものは、原則として認められません。また、賃貸物件で使用目的が(住居専用や倉庫専用など)事務所使用を認めていない場合は使用権原がないものとして認められませんのでご注意ください。

「営業所」の定義(国交省ガイドラインより)
契約の締結、工事の受注、施工の指揮監督などの業務を常時行う体制が整っている事務所
つまり、下記のような特徴を備えていることが必要です。
営業所の要件チェック例:
| 確認項目 | 内容 |
| 常駐職員がいるか | 専任技術者・事務担当者などが常勤しているか |
| 契約が締結されているか | 見積もり、入札、契約締結などそこで請負契約を実際に行っているか |
| 電話・FAX・机・パソコンなどの備品 | オフィス機能が整っているか |
| 看板・表札 | 事務所であることが外形的にわかるか |
| 社会保険加入状況 | 常駐職員の保険証の所在地がその営業所と同じか |

実態確認の方法(行政側のチェック)
申請書類の記載内容だけではなく、以下のような方法で実態を確認されることがあります:
① 書類審査
賃貸契約書の提出(使用目的が「事務所」であること)
公共料金(電気・水道・電話)の請求書の写し
事務所内の写真(外観・内観、看板など)
② 現地調査(抜き打ち・予定調査)
担当職員が営業所を訪問し、人が常駐しているか・設備が整っているかを確認する
郵便物を転送不可で送って届くかで確認する場合あり
不在や実態上営業所としてわからないなどであれば、後日再訪問または不許可につながる可能性あり
③ 社会保険や税務の登録情報との突合
健康保険・雇用保険・労災保険などの登録住所と一致しているかを確認
欠格要件の詳細と確認方法

欠格要件とは?
欠格要件とは、建設業許可を受けるにあたって「不適格」と判断される具体的な条件のことです。建設業は公共性が高く、法令遵守や社会的信頼が求められるため、一定の経歴や法令違反歴がある者には許可を与えない仕組みになっています。
欠格要件に該当すると、たとえ他の要件(経営業務の管理責任者や営業所技術者など)を満たしていても、無条件で不許可となります。
欠格要件の対象者
法人の場合、欠格要件は以下の人々に及びます:
申請者(法人そのもの)
役員(代表取締役を含む全取締役)
営業所長などの使用人(支店長クラス)
経営業務の管理責任者
営業所技術者
そのため、「代表取締役に問題がなくても、他の役員が該当していたため不許可」というケースもあります。

欠格要件の主な内容(建設業法第8条)
・成年被後見人または被保佐人
・破産者で復権を得ていない者
・禁固以上の刑に処され、5年以内に執行を終えていない者
・建設業法・建築士法・労働安全衛生法等に違反して処分を受け、5年以内の者
・暴力団員やその関係者
・過去に建設業許可を取り消された者で、取り消しから5年以内の者
・営業停止命令などに違反した者
・著しく不正または不誠実な行為を行った者
たとえば、過去に無許可で建設業を行っていた、名義貸しをしていた、労働法違反で罰金を受けた、といった事実がある場合、欠格要件に該当する可能性があります。

確認方法と提出書類
行政庁は、申請時に提出された書類をもとに欠格要件の該当有無を審査します。代表的な確認方法は以下のとおりです。
① 誓約書
申請者および関係者全員について、「私は欠格要件に該当していません」という内容の誓約書を提出します。これは様式が決まっています。
② 略歴書
過去の経歴を記載し、刑罰歴や処分歴がないことを確認します。行政庁はこれをもとに照会・調査を行います。
③ 登記簿謄本・住民票など
登記簿で役員構成を確認し、本籍地での「身分証明書」や「登記されていないことの証明書」が必要です。必要に応じて住民票で本籍地情報を取得することも。
④ 行政庁による照会
過去に許可取消や行政処分を受けた履歴があるか、警察・労基署・税務署等への照会が行われる場合もあります。

注意点と対策
形式的な誓約書提出だけでなく、実態的な調査が行われるため、虚偽申告は許されません。
役員を追加する際や、法人名義を変更する際には、新たに欠格要件を確認し直す必要があります。
心当たりがある場合は、事前に専門家(行政書士など)に相談し、影響の有無を精査すべきです。
許可取得後に必要な「更新・変更届出」などの実務

建設業許可は「一度取れば終わり」ではありません。許可取得後も、継続して事業を行うためには「更新」や「変更届出」などの義務が発生します。これを怠ると、無許可営業とみなされたり、許可取消し・営業停止といった処分を受ける可能性もあります。
以下に、許可取得後の実務として必要な「更新・変更届出」などについて、わかりやすく解説します。

許可の有効期間と「更新申請」
■ 有効期間は5年間
建設業許可の有効期間は5年です。更新せずに期限が切れると、自動的に無許可状態となり、以後の営業は違法となります。
■ 更新手続きの概要
提出時期:許可満了日の30日前までに申請(原則)
内容:現在の体制や業務状況を再確認する
書類:財務諸表、経営業務の管理責任者や技術者の継続確認資料など
■ 実務上の注意点
期限を過ぎると「新規申請」となり、審査が厳しくなる
更新には「決算変更届」が提出済である必要がある(未提出だと受付不可)

「決算変更届(事業年度終了報告)」
■ 毎年必須の報告義務
建設業者は、毎年事業年度終了後4か月以内に、決算内容を「決算変更届」として提出する必要があります。
■ 提出書類(一例)
工事経歴書
財務諸表(貸借対照表・損益計算書など)
変更届出書(様式第22号)
付属明細書(完成工事高、元請・下請内訳)
■ 未提出のリスク
経営事項審査(経審)が受けられない
更新申請ができない
行政処分(指導、勧告、営業停止等)の対象。最悪許可取り消し(建設業法29条第4項)に該当する恐れも

「変更届(随時提出)」の種類と期限
以下のような変更が生じた場合、変更があった日から30日以内(または2週間以内)に届出が必要です。
| 変更内容 | 届出期限 | 提出書類例 |
| 商号・名称、所在地の変更 | 30日以内 | 登記簿謄本、地図など |
| 役員の変更(就任・退任) | 30日以内 | 略歴書、誓約書、住民票など |
| 経営業務の管理責任者の変更 | 2週間以内 | 経歴証明書、確認書など |
| 営業所技術者の変更 | 2週間以内 | 資格証明書、在籍証明など |
| 営業所の新設・廃止・移転 | 30日以内 | 賃貸契約書、写真、地図 |
| 使用人の変更(支店長等) | 30日以内 | 略歴書、誓約書等 |
| 資本金の増減 | 30日以内 | 登記簿謄本、財務資料 |
✅ 経管と専任はなぜ2週間(14日以内)なのか?
経営業務の管理責任者と営業所専任技術者は、建設業許可の最重要要件の一つであり、空白期間があること自体が「許可要件不充足」の状態とみなされるためです。
そのため、変更があった場合は2週間以内で、できる限り速やかに届出を行わなければなりません。
この2週間には土日は含まれないため14日以内と説明されることもあります。
✅ (経管、専任)実務上の対応ポイント
経管・専任の退任が決まった段階で後任の人選を済ませておくのが理想です。
「2週間以内」とは実際の変更があった日から起算して2週間以内です(就任登記日など)。
書類には、後任の経歴証明書・誓約書・確認書・略歴書などが必要となります。
許可を維持し、トラブルを防ぐための心得

建設業許可を維持し、トラブルを未然に防ぐためには、法令遵守はもちろん、日々の業務の中で「当たり前のことを、当たり前にやる仕組みづくり」が何よりも重要です。以下に、建設業者として許可制度を安定的に維持し、トラブルを避けるための心得を8つの観点からご紹介します。

「許可は維持して初めて価値がある」という意識を持つ
建設業許可は一度取得すれば終わりではありません。更新・届出などの手続きを怠れば、不許可や取消しのリスクがあります。
▶ 心得:許可を“資産”ととらえ、5年先・10年先を見据えて計画的に管理する。

毎年の「決算変更届」を忘れずに提出する
これを提出しないと、更新や経審ができません。忘れやすいけれど最重要のルーティン業務です。
よく見落とされがちですが、建設業法29条(許可の取り消し)第4項をご確認ください。「許可を受けてから1年以上営業を休止した場合」との文言がありそれに該当した場合は許可を取り消さなければならないとされています。決算変更届の提出を怠っているということは営業を休止しているととらえられる要素になるので注意が必要です。
▶ 心得:決算が締まったら、4か月以内に届出を行うスケジュールを社内で習慣化する。

外注先や下請の選定にも慎重に
名義貸しや下請けの無許可営業に関与すると、自社の許可まで取り消される可能性があります。
▶ 心得:下請契約前には相手の建設業許可の有無を必ず確認する。台帳で管理すると◎。

行政からの通知・書類は即確認・対応
更新案内や届出不備の連絡を放置すると、期限を過ぎてしまい、再申請が必要になったり、指導対象になることも。
▶ 心得:官公庁や行政書士からの通知書・メールは必ずその日のうちに確認・対応。

専門家との連携をルーティン化する
毎年の決算や人事異動、法改正のたびに一から調べていては非効率。信頼できる行政書士・税理士との連携が許可維持の近道です。
▶ 心得:「わからないことはすぐ聞ける関係性」を築くことが、最小の手間で最大の安心につながる。
おわりに|ガイドラインを“活かす”ことが許可維持のカギ

建設業許可を取得した後、その許可を安定的かつ確実に維持することは、公共工事の受注や元請からの信頼確保のうえで極めて重要です。そこでカギとなるのが、国土交通省が定める「建設業許可事務ガイドライン」の活用です。
このガイドラインは、単なる行政向けマニュアルではなく、事業者にとっても「正しい判断」と「的確な対応」を行うための実務の指針として機能します。

ガイドラインが許可維持に不可欠な理由
1. 制度改正の内容と実務対応が分かる
ガイドラインは、最新の法改正(例:営業所技術者の兼務緩和など)を反映しており、変更点をどのように運用すべきかが明記されています。
▶ 例:「現場兼務が認められる条件」や「テレワーク中の常勤確認方法」などが具体的に示されている。
2. トラブル予防につながる実務判断が明文化されている
「営業所の実態」「経営業務の管理責任者の要件」「財産的基礎の確認方法」など、許可取得や更新でつまずきやすいポイントの判断基準が整理されています。
▶ 曖昧だった基準が明文化されているため、書類の不備や誤解を未然に防ぐことが可能。
3. 届出漏れや期限違反のリスクを回避できる
変更届・更新手続き・決算変更届などの法定期限・必要資料が網羅されており、これを参照することで許可維持の「落とし穴」を回避できます。
▶ 誤認しやすい「届出期限」も、条文ごとに明確に記載あり。
4. 自社の体制を客観的に見直すツールになる
ガイドラインをチェックリストとして活用することで、自社が法的要件を満たしているかを自主点検できます。
▶ 行政対応の前に、自社で改善すべき点を洗い出せる。

活かし方のポイント
| 活用場面 | 活かし方 |
| 新規許可・更新時 | 要件の確認にガイドラインを参照し、先回りで書類整備する |
| 体制変更があったとき | 経管・技術者・営業所の変更に対し、適切な対応方法と提出期限を確認 |
| 曖昧なケースの判断に | 迷ったときはガイドラインの「Q&A」や「例示」をもとに判断する。それでもわからなければ、詳しい行政書士に |
| 社内教育・業務管理 | 担当者にガイドラインを読ませることで、実務の正確性と自覚を高める |