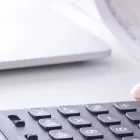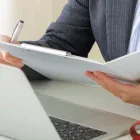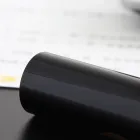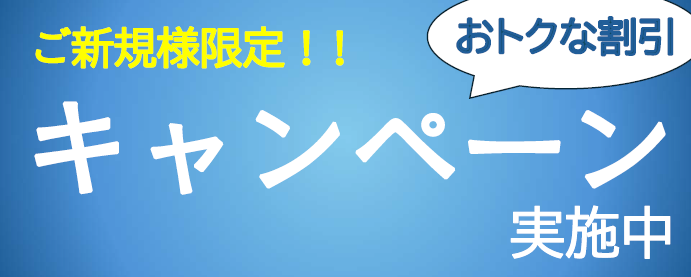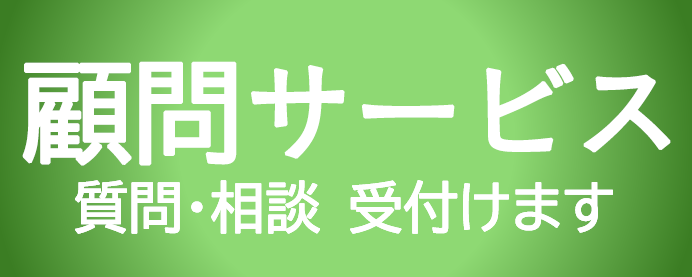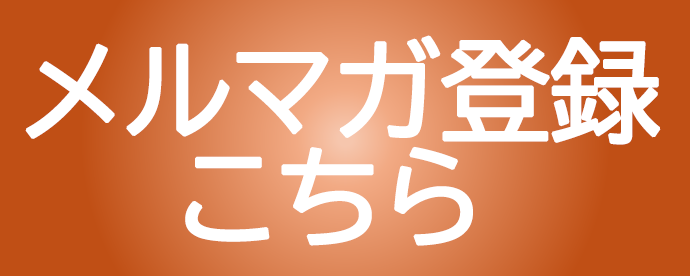手続きや運営体制に関する質問に回答
FAQ
建設業許可の取得や各種手続きに関して、多く寄せられる質問をまとめています。必要な登録や申請の流れ、許可取得にかかる期間、対応可能な工事など、事業を進める上で気になる点について分かりやすく解説しています。建設業を営む上で知っておいていただきたい情報のほか、事務所の運営体制やご相談後の進め方などについても紹介しております。不明点があれば、お気軽にお尋ねください。
よくある質問
- 建設業者として注意すべき請負額について教えてもらえますか?
- 建設業法では、様々な金額が定められています。
その中でも、請負額に関して特に注意すべき数字は以下の通りです。
・現場専任が求められる公共性のある施設の請負額
4,500万円(建築一式は9,000万円)
・特定建設業でなければ施工できない(現場には監理技術者を配置する必要がある)下請額
5,000万円(建築一式は8,000万円)
・指導監督的実務経験として認められる請負額
4,500万円
<建設業に関連する請負額の考え方まとめ>
【建築一式以外の工事】
500万円超(以下、税込み): 建設業許可が必要
4,500万円以上: 建設業許可 + 現場への技術者専任が必要
下請発注金額が5,000万円以上の場合: 建設業許可(特定建設業) + 現場への技術者(監理技術者)専任が必要
【建築一式工事】
1,500万円超(以下、税込み): 建設業許可が必要
9,000万円以上: 建設業許可 + 現場への技術者専任が必要
下請発注金額が8,000万円以上の場合: 建設業許可(特定建設業) + 現場への技術者(監理技術者)専任が必要
指定建設業
土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の7業種
上記以外の業種で監理技術者となるために必要な指導監督的実務経験として認められる請負額
元請として4,500万円以上の工事
- 公共工事の受注には「ケイシン」が必要だと聞きましたが、本当ですか?
- 建設業法第27条の23では、以下のように定められています。
「1.公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営に関する客観的事項について審査を受けなければならない。」
この審査のことを経営事項審査(経審、ケイシン)といいます。
また、建設業法施行規則18条の2では、
「法第27条の23第1項の建設業者は、同項の建設工事について発注者と請負契約を締結する日の1年7月前の日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければならない。」
と定められていることから、建設業者は公共工事の受注(軽微なもの及び災害復旧などを除く)に際し、経審を受けている必要があります。
そのため、受注時に経審を受けていない場合は、発注者にその旨を伝えるとともに、受注を避ける義務が発生します。経審を受けずに受注した場合、建設業法第28条第1項の「この法律の規定」に違反することになり、指示処分を受ける可能性があります。
さらに、第1項第2号の「建設業者が請負契約に関し不誠実な行為をしたとき。」に該当する可能性があり、第3項の「第1項各号の一に該当するとき」の規定により、営業停止処分が科されることもあり得ます。
つまり、入札の有無に関わらず、公共工事の受注を希望する建設業者は、経営事項審査を受けている必要があります。
- とび・土工の許可があれば、解体工事業者登録をしなくても問題ありませんか?
- 答えは「ダメです。」
平成28年5月までは、土木一式工事業、建築一式工事業、とび・土工工事業の建設業許可を持っている場合、解体工事業者登録をしなくてもよいとされていました。
しかし、解体工事業が新設されたことにより、とび・土工工事業の許可を持っている場合でも解体工事業者登録をしていなければ、税込500万円未満の解体工事を行うことができなくなりました。
現在では、土木一式工事業、建築一式工事業、解体工事業のいずれかの許可がなければ、500万円未満の解体工事を行うために解体工事業者登録が必要となりますので、ご注意ください。
また、とび・土工工事業の許可を持つ会社の中には、「当社は解体工事業が必要となる500万円以上の解体工事を行わないため、解体工事業許可は不要」と考えているケースがあります。
しかし、土木一式工事業または建築一式工事業の許可がない場合、500万円未満の解体工事を請け負うためには解体工事業者登録が必要です。
ただし、平成28年5月までにとび・土工工事業の許可を取得していた会社については、平成31年5月末日までは解体工事業の許可がなくても解体工事を継続できる経過措置が設けられています。
見落とされがちですが、平成28年6月以降にとび・土工工事業の許可を取得した方には経過措置が適用されません。このため、気付かないうちに建設業法違反となっているケースも散見されます。
- 500万円以上の資金調達能力を証明する際に、複数の金融機関の残高証明書の金額を合算しても問題ありませんか?
- 一般建設業の許可を受けるためには、500万円以上の資金調達能力が必要です。
その証明に必要な資料として、以下のいずれかが求められます。
・金融機関の残高証明書
・融資証明
・法人の場合: 直近決算の自己資本(設立後、決算期を迎える前であれば資本金の額)
このうち金融機関の残高証明書については、申請者名義の預金が複数の金融機関にある場合、すべての残高証明書の「残高日」(発効日ではない)を統一し、その合計額が500万円以上あれば認められます。
なお、兵庫県では、残高証明書の有効期間は「残高日」から1カ月間と定められていますので、ご注意ください。
- 知事許可と大臣許可には、どのような違いがありますか?
- 知事許可は、1つの都道府県内にのみ営業所を置く場合に必要となります。
一方、大臣許可は、2つ以上の都道府県に営業所を置く場合に必要です。
同じ都道府県内に複数の営業所があっても知事許可で問題ありませんが、1か所でも県外に営業所を設置する場合、大臣許可が必要となります。
例:
知事許可のケース
神戸市(兵庫県)に本店があり、姫路市(兵庫県)、洲本市(兵庫県)、豊岡市(兵庫県)に営業所がある場合 → 兵庫県知事許可
大臣許可のケース
尼崎市(兵庫県)に本店があり、西淀川区(大阪府)に営業所がある場合 → 大臣許可
この区別は、営業所の設置状況によるものであり、知事許可・大臣許可のいずれであっても、営業する地域や工事を施工する地域に制限はありません。
ただし、建設業の営業所を設置するには、各営業所が建設業の営業を行える状態(事務所の使用権限および一定の要件を満たす技術者の配置)を備えている必要があります。
- 申請をすれば、誰でも建設業許可を受けることができますか?
- 営業所技術者を営業所ごとに配置していること
建設業では、長期にわたり社会で使用されるインフラや建物の施工を行うため、確かな技術力が必要です。
そのため、建設業法では、以下のいずれかに該当する技術者を営業所ごとに配置することを許可の条件としています。
・現場での10年以上の実務経験がある者
・一定の資格を有する者(施工管理技士、建築士、電気工事士など)
- 監査役を変更しましたが、役員変更届の提出は必要ですか?
- 監査役・執行役員の変更については届出の必要はありません。
ただし、建設業では、法人の役員等や個人事業主、支配人に変更があった場合には届出が必要です。
また、5%以上の株主に変更があった場合には、変更届の提出が必要になりますので、ご注意ください。
- 建設業の各種届出には、提出期限などの規定がありますか?
- 主な変更内容の提出期限は以下の通りです。
① 事実の発生から2週間以内
・経営業務の管理責任者の変更(氏名の変更も含む)
・営業所技術者の変更(氏名の変更も含む)
・令3条の使用人(従たる営業所の代表)の変更
② 事実の発生から30日以内
・商号または名称の変更
・株主・役員等の変更(新任・辞任・退任、氏名の変更も含む)
・代表者の変更(氏名の変更も含む)
・資本金(出資総額)の変更
・営業所の名称、所在地の変更
・営業所の新設・廃止
・営業所の業種の変更
③ 毎事業年度終了後4ヶ月以内
・決算報告
・健康保険等の加入状況
・定款の変更
- 建設業の許可を持っていれば、公共工事の入札に参加することができますか?
- 残念ながら、建設業の許可を持っているだけでは公共工事の入札には参加できません。入札に参加するためには、「経営事項審査」を受ける必要があります。
公共工事の各発注機関は、入札に参加しようとする建設業者に対して、事前に資格審査を行い、欠格要件に該当しないかを審査します。その後、客観的事項と主観的事項を審査し、点数化して順位付け・格付けを行います。
このうち、客観的事項の審査が「経営事項審査」と呼ばれるもので、これは「経営状況」や「経営規模、技術的能力、その他の客観的事項」について数値で評価する制度です。
経営事項審査の有効期間は、結果通知書を受領した後、審査基準日(前期の決算日)から1年7ヶ月の間です。そのため、毎年公共工事を直接請け負おうとする場合は、毎年決算後に速やかに経営事項審査を受ける必要があります。
- 建築工事業(建築一式工事)の許可を受けた場合、建築に関連するどのような工事でも請け負うことができますか?
- 建築工事業(建築一式工事)の許可を保有していても、各専門工事の許可を持っていない場合、500万円以上(税込)の専門工事を単独で請け負うことはできません。土木工事業(土木一式工事)も同様に扱われます。
例:「○○邸内装改修工事」という名称の工事の場合、一般的には「内装仕上工事」に該当することが多く、その場合、建築一式工事業の許可のみでは500万円以上(税込)の工事を請け負うことはできません。 ※「建築一式工事」とは、総合的な企画、指導、調整のもとで建築物を建設する工事を指します。通常、新築や増改築などの大規模工事を元請けとして請け負う工事が該当します。それ以外の工事は、原則として各業種の専門工事となります。
- 一式工事の許可を持っていれば、専門工事も施工して問題ないでしょうか?
- 過去には、一式工事業者を総合建設業として扱っていた時期もあり、そのため一式工事は他の専門工事を含む全ての工事ができると考えられていたこともあったようですが、現在では、一式工事の許可を持っていても、専門工事の許可がない場合、専門工事は単独で受注できないという見解が国土交通省から示されています。
- 営業所技術者は現場に配置できないのでしょうか?
- 許可の要件である営業所技術者の職務は、「常時その営業所に勤務し、その営業所で契約された工事の施工を技術的観点から管理監督する」ことです。営業所技術者は、基本的に「休日やその他勤務を要しない日を除き、通常の勤務時間内にその営業所に勤務できる者」の中から選ばれ、その職務に「専任」しなければならないとされています。
そのため、原則として現場への配置はできません。ただし、一人親方の場合などでは仕事ができなくなってしまうため、国土交通省は平成15年4月21日の通達で、「当該営業所において請負契約が締結された建設工事であって、工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事できる程度に工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡をとれる体制が整っている場合には、当該営業所において営業所専任技術者である者が、当該工事の現場における主任技術者または監理技術者(法第26条第3項に規定する専任を要する者を除く。以下「主任技術者等」という。)となった場合でも、「営業所に常勤して専らその職務に従事している者」として取り扱う。」としています。
現状の取り扱いとしては、現場専任を要しない工事で、往復約30分以内(許可権者によって若干異なる場合もありますが)で行き来できる場合、営業所技術者であっても現場に配置できるとされています。
※令和6年12月13日 建設業法改正により 要件が緩和されました。
詳しくは知っとくニュース2025年1月21日号をご確認ください。
- 技術者は現場に常駐しなければならないのでしょうか?
- 基本的に建設業法では、金額にかかわらず、現場の配置技術者については工事施工中、現場への常駐が求められています。ただし、工場製作期間や下請工事で自社の施工がないなど、現場が全く動いていない場合は常駐する義務はありません。
さらに、税込税込4,500万円(建築一式では9,000万円)以上の工事の場合は公共性の高い工事とされ、現場専任が求められています。
このことから、現場での専任について質問をいただくことがありますが、平成29年8月9日付の通達で「ここでいう専任とは、他の工事現場に係る職務を兼務せず、常時継続的に当該工事現場に係る職務にのみ従事することを意味するものであり、必ずしも当該工事現場への常駐(現場施工の稼働中、特別の理由がある場合を除き、常時継続的に当該工事現場に滞在していること)を必要とするものではない。」とされています。
そのため、技術者の方が打ち合わせや休暇などで現場にいないといったことをもって即ダメと言われるものではないことがわかります。
ただし、通達上、適切な施工が確保できる体制を整えることを条件に、技術研鑽などのために短期間現場を離れることを例に挙げていますので、休暇が長期にわたるなどの場合は専任の要件を満たさないと考えるべきでしょう。
- 標識に関することについて教えていただけますか?
- 建設業の許可を受けた者は、その店舗または公衆の見やすい場所に標識を掲示しなければなりません(建設業法第40条)。
■標識の記載内容等
(1)商号または名称
(2)代表者の氏名
(3)一般建設業または特定建設業の別
(4)建設業許可年月日、建設業許可番号
(5)許可を受けた建設業
縦35cm以上・横40cm以上の長方形であること
※大きさや記載事項に誤りがなければ、材質等には規制はありません。プリントアウトして額に入れたものでも構いません。
ただし、建設業法では常に公衆の見やすい場所(オフィスビルであれば扉の横やオフィスの入り口等)に掲示する必要があるため、見た目に貧相なものだと本当に掲示しているのかと指摘されることがありますので、ご注意ください。
- 費用の分割払いは可能でしょうか?
- 分割払いについては、取扱っておりません。
- 個人経営の小さな会社でも、顧問を依頼することはできますか?
- 当事務所では、会社の規模によって契約をお断りすることはありません。
- 紹介がなくても相談は可能でしょうか?
- もちろん、相談可能です。