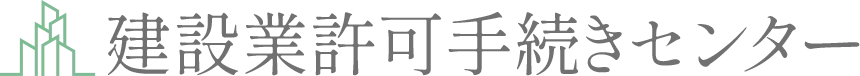建設業法違反について
2025/06/21
建設業界においては、日々多様な取引や現場施工が行われていますが、その根幹を支えているのが「建設業法」です。建設業法は、建設業の健全な発展を図るとともに、工事の適正な施工を確保し、発注者や元請・下請の保護を目的とする法律です。しかし、現場ではこの建設業法を軽視、あるいは誤解したまま業務を行っている事例も少なくありません。とくに「うちは小さい会社だから」「前からこうやってきた」といった感覚で行われる行為が、実は重大な法令違反に該当していたということにならないよう説明していきます。
目次
第1章 建設業法違反とは何か~違反は「知らなかった」では済まされない

ついうっかりで会社が危機に
建設業を営むうえで避けて通れないのが、建設業法の遵守です。この法律は昭和24年に制定され、以降、建設業の健全な発展と工事の適正な施工を目的として、たびたび改正されながら現在に至っています。建設業法は単なる形式的な法規範ではなく、発注者・元請・下請の保護や、公共の安全・品質・信頼性の確保に直結する重要な法律です。
にもかかわらず、現場では「長年の慣習」や「手続きの簡略化」を理由に、法令が軽視されてしまう場面が少なくありません。「うちは規模が小さいから」「知り合い同士だから問題ない」といった認識が、思わぬ法令違反につながるケースも多く見られます。特に、契約書を取り交わさずに工事に着手していた、無許可の状態で請負契約を結んでいた、現場に技術者を配置していなかったといった行為は、典型的な建設業法違反に該当します。
また、建設業法違反は、単なる指導で済むような軽微なものだけではありません。違反の内容や悪質性によっては、業務停止処分や許可取消処分、さらには刑事罰にまで発展する場合もあります。とりわけ、許可制度に関する虚偽申請、名義貸し、談合などは、重大な法令違反として、関係者の社会的信用を著しく損なうことになります。
さらに、建設業法違反が発覚すれば、都道府県や国土交通省からの指名停止措置を受けることになり、公共工事の受注機会を失うリスクも生じます。とくに中堅・中小建設業者にとっては、一度の違反が事業継続に直結するほどの打撃となりかねません。
こうしたリスクを回避するためには、建設業法を「申請時に読む書類」としてではなく、「日常業務に常に適用される実務ルール」として認識することが重要です。経営者だけでなく、工事部門や総務・経理担当者も含めた全社的な法令遵守体制の整備と意識改革が求められています。法令は、知っていなかったからといって免責されるものではなく、すべての事業者に等しく適用されます。
建設業界において法令遵守は、単なる義務ではなく、取引先や発注者からの信頼を獲得するための「経営戦略の一部」と捉える必要があります。違反を未然に防ぐための内部チェック体制や、定期的な知識のアップデートが、これからの時代には不可欠です。

~建設業法28条「指示・営業停止」と29条「許可取消し」の違い~
①建設業法第28条は、「指示」および「営業停止」という2段階の行政処分を定めています。
- 指示処分(第28条第1項)
これは比較的軽微な違反に対し、業者に業務改善を促す「警告」的性格の処分です。たとえば以下のようなケースが該当します。
・建設業許可の変更届を怠った
・帳簿や契約書の整備が不十分
・建設業許可票の未掲示
この段階では、まだ「改善の機会」が与えられています。指示内容に従って速やかに是正すれば、それ以上の処分に至らないことが大半です。 - 営業停止処分(第28条第2項)
より重大な違反行為や、指示無視の再違反には、営業の一部または全部を一定期間停止する処分が行われます。
例:
- 虚偽申請による許可取得(軽度な場合)
- 無資格技術者の現場配置
- 下請代金の不払い・著しい遅延
営業停止期間は、1日~1年以内とされており、処分が確定した場合、その期間中は該当工種または全業種の業務ができません。自治体や国交省のHPで公表されるため、社会的信用にも大きく影響します。
②建設業法第29条では、より重大で改善の余地がない場合に対して「建設業許可の取消し」を命じることができます。これは、業者にとって極めて重大な処分であり、再取得にも長い時間と手続が必要です。
【取消し事由(主な例)】
- 欠格要件に該当したまま営業を継続(暴力団との関係、破産等)
- 虚偽・不正の手段で許可を取得
- 技術者・経管がいないのに営業
- 指示や営業停止を繰り返し無視
取消し後の影響:
- 再度の許可取得まで5年間の欠格期間
- 経審参加不可・入札資格喪失
- 元請契約の継続困難(信用喪失)
まさに建設業者にとっては「廃業に等しい処分」となります。
③28条と29条の処分を比較して整理
| 項目 | 第28条 | 第29条 |
| 処分の種類 | 指示/営業停止 | 許可の取消し |
| 性格 | 是正機会を与える/一時的制限 | 根本的営業資格の剥奪 |
| 対象となる違反 | 軽微な違反・初犯・形式違反など | 欠格要件・重大な虚偽・反復違反など |
| 処分後の再許可 | 営業停止期間終了後に再開可能 | 欠格期間(原則5年)経過後でなければ再許可不可 |
| 公表の有無 | 原則公表(行政庁HPなど) | 公表+各種契約停止措置もあり |
④処分を回避するには~予防的実務が命~
第28条や第29条の処分を回避するには、次の3点がカギとなります。
- 定期的な自己点検(技術者や経管の在籍、届出漏れの確認)
- 契約・帳簿・許可票など形式面の徹底
- 行政書士や顧問との連携による予防法務
とくに行政庁から「指示」を受けた段階で放置することは厳禁です。28条の指示が、29条の取消しの「前段階」となることも多く、早急な対応が必要です。
まとめ
建設業法第28条と第29条は、行政処分の軽重を分ける二つの柱です。
第28条は「警告的処分」、第29条は「資格の剥奪」です。
法令違反への対応を怠れば、信用の喪失や事業停止へ直結します。
日々のコンプライアンス意識が、重大処分から会社を守る最善の防波堤です。

建設業法違反に係る罰則
建設業法第45条以降には、法令違反に対して科される刑事罰(罰則)が定められています。これは、単なる行政処分(指示・営業停止・許可取消)とは異なり、刑罰としての「罰金刑」や「懲役刑」を科すことで、違法行為を抑止するための強い制裁手段です。

建設業法 第47条:罰則(刑事罰)の詳細解説
条文の構造(第1項)
第47条第1項は、以下の5つの違反行為に対して、「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」を科すことができると規定しています。
❶ 第三条第一項違反(無許可営業)
許可を受けずに建設業を営んだ場合
もっとも基本的な違反。
許可を要する金額(原則500万円以上)を超える建設工事を反復継続して請け負えば、営業性ありと判断され、許可が必要。
個人事業主でも対象。
❷ 第十六条違反(下請契約制限違反)
一般建設業者が、適切な専任技術者を配置せず、一定規模以上の下請契約を締結した場合など。
特定建設業者でなければ締結できない額の下請契約を違法に結んだ場合(建築一式で1,500万円以上、その他で500万円以上)。
違反すると、重大な監督処分と刑事罰が科され得ます。
❸ 第二十八条第三項または第五項違反(営業停止命令違反)
行政庁から営業停止処分を受けたにもかかわらず、その期間中に建設業を営んだ場合。
停止命令を無視して営業を続けた場合は、重大な違反とされ、刑事罰の対象。
❹ 第二十九条の四第一項違反(営業禁止命令違反)
反復して違反を行った場合に命じられる「営業禁止命令」に違反したとき。
悪質な違反を繰り返す業者に対して命じられる建設業界からの永久追放処分。
違反すると厳罰必至。
❺ 虚偽・不正申請による許可・認可取得
許可・認可申請において虚偽や不正があった場合。
たとえば、虚偽の専任技術者経歴や財務書類の偽造などが該当。
許可更新や認可(経管要件緩和、技術者の認定など)も含まれる。
第2項:併科の規定
「情状により、拘禁刑および罰金を併科することができる」
単にどちらか一方でなく、悪質性が高い場合には懲役刑+罰金刑の両方を科すことが可能。
刑事事件として立件されれば、社会的信用の失墜にもつながります。
✅ まとめ表:建設業法第47条の違反類型と処罰
| 違反行為 | 内容 | 根拠 | 処罰内容 |
| 無許可営業 | 許可を受けずに建設業を営む | 第3条違反 | 3年以下の拘禁刑 or 300万円以下の罰金 |
| 違法な下請契約 | 特定建設業の義務違反など | 第16条違反 | 同上 |
| 営業停止 | 命令違反処分を無視して営業 | 第28条違反 | 同上 |
| 営業禁止 | 命令違反恒常的な違反業者 | 第29条の4違反 | 同上 |
| 虚偽申請 | 不正手段での許可・認可取得 | 第3条・17条等 | 同上 |

建設業法 第50条(虚偽申請等に対する刑事罰)
🔹【条文抜粋(正確版)】
第五十条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
一 第五条(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による許可申請書
又は第六条第一項(同上)の規定による書類に虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
二 第十一条第一項〜第四項(同上)の規定による書類を提出せず、
又は虚偽の記載をして提出したとき。
三 第十一条第五項(同上)の規定による届出をしなかったとき。
四 第27条の24第2項、第27条の26第2項の申請書、
又は同第3項の書類に虚偽の記載をして提出したとき。
第2項:前項の罪を犯した者には、情状により拘禁刑と罰金の併科が可能。
解説:どのような違反が対象になるか
この条文は、建設業者の許可・変更・届出等の行政手続きにおいて、虚偽または不提出という「形式違反」に対し、刑事罰を科す根拠となるものです。
◉ 該当条項とその違反内容
| 項目 | 該当条文 | 違反行為の例 |
| 第50条第1号 | 第5条・第6条 | 新規・更新の許可申請時に、虚偽の内容を記載して許可申請をした。 |
| 第50条第2号 | 第11条第1~4項 |
許可取得後の変更届(役員変更、資本金変更など)をせず、または虚偽で出す 事業年度終了後の決算変更届を提出しない |
| 第50条第3号 | 第11条第5項 | 許可要件者の退職等により許可要件が欠落しているのに届出をしていない |
| 第50条第4号 | 第27条の24・26 | 分析・経営事項審査の申請において虚偽の内容で申請 |
実務上のリスク
「提出忘れ」だけでも刑事罰の対象になり得る(第2項、第3項)。
→ 特に決算変更届の未提出はありがちだが、これは明確な法令違反です。
虚偽記載がある場合は、刑事罰だけでなく、行政処分(指示・営業停止・取消)にも波及する(建設業法28条・29条)。
法人の場合も、代表者や担当役員が処罰対象となる可能性があります。
罰則の内容
拘禁刑(懲役に相当):6ヶ月以下
罰金刑:100万円以下
併科可能(第2項)
これは、重大な不正行為でなくとも、形式的な違反に対しても科される可能性があるため、「行政処分とは別に、刑事責任が問われ得る」点が大きな特徴です。

建設業法 第52条(罰則)
第五十二条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
| 項目 | 内容 | 対象行為 |
| 一 | 第26条第1項〜第3項または第26条の3第7項の規定による主任技術者または監理技術者を置かなかったとき | 技術者の適正な配置義務違反 |
| 二 | 第26条の2の規定に違反したとき | 建設業者が主任技術者を専任で配置しなかった等の違反 |
| 三 | 第29条の3第1項後段の規定による通知をしなかったとき | 建設工事の請負契約を締結した旨の通知義務違反 |
| 四 | 第27条の24第4項または第27条の26第4項の規定による報告や資料提出をしなかった、虚偽の報告をした | 技能者等に関する調査や登録に係る報告義務違反 |
| 五 | 第31条第1項、第41条の2第4項または第42条の2第1項の報告をしない、虚偽報告行 | 政機関への報告義務違反 |
| 六 | 第31条第1項、第41条の2第4項または第42条の2第1項の検査を拒否・妨害・忌避 | 実地調査や検査を妨げる行為 |
| 七 | 第41条の2第3項の命令に違反したとき | 建設キャリアアップシステム等に係る命令違反 |
解説
本条は、建設業法における実務運用・監督義務に違反した場合の罰則を定めたもので、建設業の現場管理体制の適正化を図る趣旨に立脚しています。主任技術者・監理技術者の未配置や、関係機関への報告義務違反、虚偽報告・忌避行為などが対象であり、いずれも「百万円以下の罰金」となります。
なお、これらの違反は刑罰(拘禁刑)を伴わない点で、重大な法令違反(例:無許可営業=47条)とは処分の重さが異なりますが、行政処分(指示処分・営業停止処分)と併せて科される可能性があり、注意が必要です。

建設業法 第53条【両罰規定】(令和4年改正後)
【条文原文】
第五十三条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人、その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、
その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、
その人(自然人)に対して各本条の罰金刑を科する。
| 違反条文 | 対象規定 | 法人に科される罰金刑 |
| 一 | 第47条(無許可営業等) | 1億円以下の罰金刑 |
| 二 | 第50条または第52条 | 各本条に定める罰金刑(例:100万円以下など) |
解説
1. 両罰規定の意義
この条文は、法人や個人事業主の名義で行われる業務において重大な法違反があった場合に、
① 違反行為を実行した個人(従業員・役員など)と、
② 組織としての責任を負う法人・人
の両方を罰するという考え方を示しています。
これにより、組織ぐるみでの法令違反、または組織が放置・黙認していた違反に対して法人に罰金刑を科すことができます。
2. 対象条文の解説
| 項目 | 内容 |
| 第47条 | 無許可営業、下請契約違反、営業停止命令違反など。最も重い罰則(懲役3年以下・罰金300万円以下)。法人には1億円以下の罰金刑が科される。 |
| 第50条 | 虚偽の許可申請・届出等に対する罰則(懲役6か月以下・罰金100万円以下)。法人にも同様の罰金刑。 |
| 第52条 | 主任技術者の未配置、報告義務違反等に関する軽微な違反(罰金刑)。法人にも同等の罰金刑が科される。 |
3. 実務的注意点
法人が直接違反を行ったわけでなくても、従業員や役員が違法行為を業務の一環として行っていた場合、法人も同時に罰則を受ける可能性が高い。
特に無許可営業(第47条)の罰金額は重く、1億円以下と非常に高額であるため、事実上の死活問題になり得ます。
経審(経営事項審査)の社会性評価にも大きなマイナスがつくため、コンプライアンス対策・内部監査の体制整備が重要です。

建設業法 第五十五条(過料の規定)
【条文】
第五十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一 第十二条(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠つた者
二 正当な理由がなくて第二十五条の十三第三項の規定による出頭の要求に応じなかつた者
三 第四十条の規定による標識を掲げない者
四 第四十条の二の規定に違反した者
五 第四十条の三の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿若しくは図書を保存しなかつた者
解説
この条文は、刑罰(懲役・罰金)ではなく「過料」(行政制裁)として科される違反行為を定めたものです。
◉ 対象となる行為の内容
| 項番 | 違反行為の内容 | 該当条文 | 補足 |
| 一 | 建設業許可に関する変更届等の提出義務違反 | 第12条 | 商号、代表者、役員等の変更届などを怠った場合 |
| 二 | 出頭命令への不応 | 第25条の13第3項 | 審査会による調停への出頭要請に正当な理由なく応じなかった場合 |
| 三 | 標識掲示義務違反 | 第40条 | 営業所や現場に掲示すべき「建設業許可標識」の未掲示 |
| 四 | 不正表示の禁止違反 | 第40条の2 | 無許可業者が、あたかも許可業者であるかのように表示した場合 |
| 五 | 帳簿整備・保存義務違反 | 第40条の3 | 工事内容や契約金額の帳簿を整備せず、記載せず、または保存しない場合等 |
実務的注意点
この条文による「過料」は、刑事罰ではないため前科にはなりませんが、行政上の信頼性低下や営業停止処分などに波及する可能性が高いです。
特に、帳簿整備(40条の3)や標識掲示(40条)の不備は、立入検査等でよく確認され、指導・処分の原因になりやすいです。
なお、「過料」は原則として都道府県知事または国土交通大臣の所管により科される行政制裁です。

建設業法違反のリスクと企業が果たすべきコンプライアンス管理の重要性
⚠ 法令違反がもたらす3つの重大リスク
信用失墜と指名停止のリスク
公共工事を受注している企業が法令違反を起こせば、指名停止措置が即座に取られることもあり、経審・格付にも影響します。
→ 小規模な違反でも自治体の内規によっては数ヶ月〜1年の停止となるケースも。
監督処分による業務への支障
営業停止(建設業法第28条)処分により、一定期間工事を受注できなくなることで、現場工程、従業員の雇用、協力業者との関係にも影響を及ぼします。
許可取消のリスクと再取得の困難さ
一度許可を取り消されると、再取得のために数年を要するほか、「欠格要件該当者」として再申請が困難になる場合があります。
🛡 コンプライアンスを徹底することが企業防衛の第一歩
建設業法の遵守は単なる法律上の義務ではなく、企業としての社会的信用を守るための“防衛策”です。とりわけ、法令違反が「悪質」と認定されれば、民事訴訟や損害賠償請求などにも発展する可能性があります。
建設業者にとって、建設業法違反は「バレなければ問題ない」ではなく、「気付いたときには取り返しがつかない」という現実があります。
第2章 無許可営業の危険性~500万円未満でも安心できない

無許可営業の危険性~許可不要のラインを正しく理解する
建設業法の根幹を成すのが、第3条に定められた「許可制度」です。この条文では、建設工事の完成を請け負う営業を行う者は、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければならないとされています(第1項)。ただし、その例外として、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合には、許可を要しないことが第2項において明記されています。
ここでいう「軽微な建設工事」とは、建設業法施行令第1条に定められており、①建築一式工事の場合は1件1,500万円未満(または木造住宅で延べ面積150㎡未満かつ1,500万円未満)、②その他の工事であれば1件あたり500万円未満とされています。この金額を超えない限りは、たとえ反復継続して請け負っていたとしても、許可は不要です。
したがって、「反復継続して請け負っていれば営業にあたる → 許可が必要になる」という説明がされることがありますが、これは正確には**「営業にあたるとしても、その請け負う工事が軽微であれば、許可は不要」というのが法文上の解釈です。営業性と許可の要否は連動しているようでいて、実際には別の判断軸(工事金額)を挟んで整理されている**点に注意が必要です。
実務では、「500万円未満なら許可はいらない」と安易に考える傾向がある一方で、「営業」として工事を請け負っていれば許可が必要になるのではと混同するケースもあります。しかし、建設業法第3条第2項は、営業性の有無にかかわらず、工事が軽微であれば例外扱いするという規定であり、これにより反復継続して行われる小規模工事(500万円未満)であっても、許可は不要とされているのです。
一方で、許可が不要だからといって「何をしてもよい」というわけではありません。軽微な工事でも、名義貸しや建設業者を装った虚偽表示、また発注者に誤認を与えるような広告表示を行っていた場合には、別の法令違反に問われることがあります。特に元請事業者が、実態は無許可業者である者に発注していたような場合は、建設業法上の指導・監督義務違反が問われるおそれもあります。
建設業を行ううえで重要なのは、工事金額の基準を正しく理解したうえで、自社がどの範囲に属するかを明確にすることです。無許可であることが直ちに違法とは限らず、工事規模と業務実態を照らして判断する必要があります。そのうえで、将来的に請負金額が拡大する可能性があるのであれば、早めに建設業許可を取得しておくことが、トラブルを未然に防ぐための賢明な選択といえるでしょう。

建設業法上の構造と条文の確認
第1項
建設工事の完成を請け負う営業をしようとする者は、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければならない。
第2項
前項の規定は、次に掲げる建設工事(いわゆる「軽微な建設工事」)を完成させることを請け負う営業を営もうとする者については、適用しない。
政令(建設業法施行令第1条)で定める軽微な建設工事
- 建築一式工事:1,500万円未満(税込み)または延べ面積150㎡未満の木造住宅
- その他の建設工事:500万円(税込み)未満

無許可営業と判断される代表的ケース
| ケース | 内容 |
| ① 500万円(税込)を超える工事を無許可で受注 | ※請負金額が基準を超えている場合は即違反 |
| ② 形式的には請負契約をしていないが、実質は請負 | 報酬を得て継続的に工事を行えば違反とみなされる |
| ③名義借りで他人の許可を使って工事を行う | 許可の「貸与」も違反行為(名義貸し) |
※違反している工事は許可申請や実務経験の証明に使用することもできないのでご注意。
※請負金額の見積り誤差や、契約後に追加工事が発生して結果的に500万円を超えることもあるため、慎重な工事計画と契約管理が求められます。さらに、許可を有していない者が、500万円を超える請負契約を1件でも締結すれば、たとえ一度きりであっても「無許可営業」として建設業法違反に問われるおそれがあるため、注意が必要です。

違反時の罰則(建設業法第50条)
無許可営業を行った者には以下のような罰則があります:
- 懲役6ヶ月以下または罰金50万円以下
- 法人が違反した場合、代表者・役員も責任を問われる可能性あり
- 違反が発覚した場合は「営業停止」や「許可不交付」の行政処分対象にもなる

許可業者が見落としがちな盲点
~営業所未届出のまま工事を請け負うリスクとは~
「うちは建設業の許可を持っているから、軽微な工事(500万円未満)ならどこで請けても問題ない」。
そう考えている建設業者は少なくありません。しかし、営業所の運用実態に着目すると、その考えには重大なリスクが潜んでいます。
✅ 法律は「どこで請け負ったか」も見ている
建設業法では、許可を取得していれば軽微な工事であっても比較的自由に受注できると思われがちです。しかし実際には、工事の契約を締結した「営業所」が許可行政庁に届出済みかどうかが大きなポイントとなります。
たとえ金額が軽微な範囲内であっても、その工事を受注・契約した場所が「未届出の営業所」である場合、以下のような法令違反とみなされる可能性があります:
- 建設業法第3条第3項(営業所の届出義務)違反
- 建設業法第7条(専任技術者の配置義務)違反
- 建設業法第28条(指示処分・営業停止処分等)の対象行為
✅ なぜ無許可業者はOKで、許可業者はNGなのか?
一見矛盾しているように見えますが、制度の設計上は一貫性があります。
🔹 無許可業者:制度的に「軽微な工事」のみを請け負うことが前提のため、営業所の届出義務なし。
🔹 許可業者:すでに一定の能力を認定された事業者であるため、「許可を受けた営業所」単位で営業活動が管理される。
つまり、許可を持っている業者であればあるほど、「営業所管理」の責任が重く課せられているのです。
✅ 実務でよくある誤認
「地方の現場事務所で軽微な工事契約を結んだ」
「出張所レベルの拠点で、名刺交換・契約・着工まで完了」
「支店を設けて営業していたが、届出をしていなかった」
いずれも、「契約行為を現地で行った=実質的に営業所である」と判断され、無許可営業と同等の扱いになることがあります。
✅ 行政処分だけではない“隠れた代償”
営業所未届出の状態での受注行為が発覚すると、以下のような影響も避けられません:
❌ 経営事項審査(経審)の評価への影響
❌ 指名停止や指名除外(公共工事の機会損失)
❌ 元請や取引先との信用失墜
❌ 保険・瑕疵担保責任の適用除外の懸念
「たかが支店で契約しただけ」と見逃される時代ではなく、営業所の届出を怠ることは重大なコンプライアンス違反として厳しく問われます。

経営者が取るべきアクション
- 営業所の定義を再確認
契約権限のある拠点・支店・現地事務所が該当します。
- 全営業拠点をリストアップし、届出の有無を確認
届出漏れがあれば速やかに行政庁へ追加届出を行いましょう。
- 専任技術者の配置確認
営業所には、原則として専任技術者の設置が必要です。
まとめ:
許可を持っているからこそ、営業所の管理は極めて重要です。軽微な工事であっても、未届出の営業所で契約行為を行えば、建設業法違反として指示処分・営業停止・許可取消の対象となり得ます。
小さな盲点が、企業の信用を大きく損なう――。
その前に、今一度「営業所の適正運用」を見直すことが、許可業者に課された義務といえるでしょう。
第3章 技術者配置違反~監理技術者・主任技術者の要件を軽視してはいけない

技術者配置違反~「名義だけ」の配置は許されない
公共・民間問わず、一定規模の建設工事においては「主任技術者」または「監理技術者」の配置が義務づけられています。これらの技術者は、現場の施工管理・品質確保・安全管理に直接関与する責任者であり、建設業法上も明確に配置義務が規定されています。ところが、実際には「資格だけ持っている社員の名前を借りている」「別の現場と兼任している」「形式的に配置しているだけ」といったケースも見受けられます。こうした「名義のみの配置」は、建設業法上の重大な違反行為です。近年では国土交通省による監査や発注者の抜き打ち調査も厳格化されており、違反が発覚した場合には指名停止や許可取消など、重い行政処分の対象となります。技術者の配置は、単なる「書類上の処理」ではなく、現場運営の根幹です。

主任技術者・監理技術者の配置義務とは
建設業法第26条第1項では、建設工事の現場には、請負金額の多少を問わず必ず主任技術者を配置しなければならないと定められています。この配置義務には金額要件はなく、たとえ軽微な工事であっても、主任技術者の配置は必要です。
この主任技術者は、発注者から直接請け負ったか否かに関係なく、建設業者が元請・下請の立場であっても必要となります。

監理技術者の専任配置義務 ~特定建設業での大規模下請負時に発生
建設業法第26条第2項に基づき、元請業者が「特定建設業の許可に基づいて」発注者から直接請け負った工事を施工し、一定額以上の下請契約を締結する場合には、主任技術者ではなく監理技術者を専任で配置しなければなりません。
この「一定額」とは、以下の通りです:
建築一式工事:下請契約総額が8,000万円(税込)以上
その他の工事:下請契約総額が5,000万円(税込)以上
監理技術者は、複数の下請け業者を統括し、安全・品質・工程を総合的に管理する役割を持ちます。主任技術者との違いは、あくまで「元請であること」「下請が一定額を超えること」「特定建設業であること」が重なったときに、より高い管理能力が求められるために設けられた制度です。

違反行為とそのリスク~名義貸し、兼任、不在の常態化
実務では、技術者の名義だけを借りて現場に一切従事していない「名義貸し配置」や、一人の技術者が複数の現場を掛け持ちする「兼任配置」などが横行しています。こうした行為は明確な法令違反であり、発覚した場合には以下のような処分が下されます:
- 建設業許可の営業停止または取消
- 公共工事の指名停止
- 社会保険未加入等との併発による立入検査強化
- 悪質な場合は刑事告発に発展することも
発注者との信頼関係にも重大な傷がつくことになり、再起が困難となるケースも少なくありません。
第4章 下請契約の適正化~契約書面の未交付は法違反

下請契約の適正化~「口約束」は許されない時代に
建設業における契約行為は、ただの商習慣ではなく、法律によって明確にルールが定められています。建設業法第19条第1項では、「建設工事の請負契約は、契約の内容を明らかにした書面を作成し、相互にこれを交付しなければならない」と規定されています。これは、請負金額の大小を問わず、すべての建設工事に適用される義務です。たとえ10万円の補修工事であっても、契約内容を書面にしなければ違反となります。
しかし、実務の現場では「いつも一緒にやってるから」「見積書と注文書だけで済ませている」「急いでいるから後で書類をまとめる」などの理由から、正式な契約書が取り交わされないまま工事が始まることがしばしばあります。こうした慣習的な運用は、法令違反であるだけでなく、トラブルの原因にもなります。たとえば、追加工事の範囲・代金・支払時期に関する認識が食い違った場合、文書による証拠がなければ元請・下請いずれにとっても不利益が生じます。
契約書には、建設業法で定められた記載事項があります。具体的には、①工事の名称・場所、②請負代金・内訳、③工期、④使用材料や工法の基準、⑤代金の支払い方法、⑥設計変更や契約解除に関する定め、⑦瑕疵担保責任、⑧損害賠償責任などが挙げられます。これらはすべて、発注者・受注者双方の権利と義務を明確化し、トラブルを未然に防ぐために必要不可欠な項目です。
また、契約時に注文書・請書といった様式で代替されているケースも多く見られますが、それらが上記の記載事項を全て網羅していなければ、形式的に契約書を交わしたことにはなりません。国土交通省はこうした点を重視しており、建設業者に対する立入検査の際には、契約書類の整備状況が重点的に確認されます。
さらに重要なのは、下請負人の保護という観点です。契約書がないまま着工させ、工事後に「思っていた金額と違う」「追加工事を認めない」といった支払いトラブルに発展する事例が後を絶ちません。こうした事態を防ぐためにも、すべての契約は、着工前に書面で交わすことが鉄則です。
一方で、建設業法第19条第3項では、建設工事の請負契約書について、電磁的記録による作成および交付が認められており、クラウド契約サービスや電子署名を活用したデジタル契約の運用も可能です。紙ベースの契約書にこだわらず、時代に即した電子契約の導入は、契約漏れのリスクを減らし、事務処理の効率化にもつながります。
契約書の整備は単なる形式的な義務ではありません。それは、「トラブルから会社を守る盾」であり、「取引の信頼性を示す証拠」でもあります。建設業における契約管理は、法令遵守と経営リスクの回避という両面において、ますます重要な意味を持つ時代に入っています。

契約書を交わさない建設業者に待つリスクとは ― 建設業法第19条
建設業界では「契約は口約束で済ませる」慣行が今なお残る現場も少なくありません。しかし、建設業法第19条は明確にこう定めています。
「建設工事の請負契約にあたっては、契約内容を書面により明らかにし、注文者に交付しなければならない」(第1項および第3項)
この規定は、単なる形式的な要求ではなく、「契約を守る」以前に「契約内容を明らかにする責任」を建設業者に課すものです。そして、これを怠ることで、思わぬリスクが生じます。
❗ リスク1:発注者とのトラブル発生時に不利
書面がなければ、「言った・言わない」の水掛け論になります。
- 「代金が支払われない」
- 「仕様変更を依頼されたのに、追加分が未払い」
- 「完成後に『こんな内容は頼んでいない』と言われた」
こうしたトラブルのほとんどは、契約内容が不明確なことに起因します。契約書は唯一の法的証拠であり、未作成の状態で紛争になった場合、立証責任は圧倒的に建設業者側に偏ります。
❗ リスク2:建設業法違反による「指導」「監督処分」
建設業法第19条違反は、法第50条(指示)および第28条(許可の取消し等)に基づき、行政処分の対象になります。
- 書面を交付しなかった場合 → 「建設業法第19条違反」として国交省または都道府県から指導の対象に
- 繰り返し違反または悪質な場合 → 営業停止処分や許可取消しもあり得る
また、国交省の指導ガイドラインでは「契約内容の不記載・契約書の不交付」を重大な違反として扱っており、経営事項審査や公共工事入札にも悪影響を及ぼすおそれがあります。
❗ リスク3:瑕疵担保責任などの責任範囲が不明確に
建設工事には、契約後も一定期間にわたる瑕疵担保責任が課せられます。書面がなければ、
- 保証期間の明示がない
- 補修対象の範囲が曖昧
- 保険契約(瑕疵担保責任保険)の証拠がない
などの状態に陥り、本来発注者と共有しておくべき義務の所在が不明確になります。

建設業法第19条第1項に定める契約事項(記載必須事項)
① 工事内容
どのような工事か(工種・仕様・数量など)を具体的に記載。
施工範囲が不明確だとトラブルの原因になります。特に追加工事の線引きをするためにも詳細に記載が必要です。
② 請負代金の額
税込・税抜の内訳を明示すること。
材料費・労務費・諸経費等を明示すると、のちのトラブル(値引き交渉・未払請求など)を防ぎやすくなります。
③ 工事着手の時期及び工事完成の時期
着工日・完了予定日を記載。
天候や資材調達の都合で変更が生じやすいため、変更手続き(後述⑥)との整合性にも注意が必要です。
④ 工事を施工しない日または時間帯の定めをするときは、その内容
休日や夜間作業の有無など。
近隣対応や安全管理にも直結するため、たとえば「日曜・祝日は作業を行わない」など明確に定めます。
⑤ 請負代金の前金払・出来高払の定めがある場合は、その支払時期及び方法
支払条件を明確にし、入金遅延を防ぐ。
振込日・現金渡し・手形などの形式も含め記載。元請と下請の双方に重要な資金繰り情報です。
⑥ 設計変更・工期延長・中止があった場合の代金変更・損害負担と算定方法
追加工事や中止による損害金の算出ルールを記載。
「口頭で追加された工事費が払われない」といった典型的なトラブルを防ぐ上でも重要です。
⑦ 天災その他不可抗力による工期変更・損害負担とその算定方法
天候や地震、資材の輸送遅延等への備え。
リスクマネジメントの観点からも、具体的な「変更条件」を記載すると安心です。
⑧ 価格等の変動(物価変動等)による内容・請負代金の変更及びその算定方法
鋼材・木材など価格高騰が激しい資材への対応として、単価見直しルールを記載。
「単価スライド制」などを導入しておくことも有効です。
⑨ 第三者損害発生時の賠償負担の定め
施工ミスや事故等で通行人や隣地に損害が出た場合の責任範囲を明確化。
保険(建設工事保険や賠償責任保険)の適用範囲を記載することも望ましいです。
⑩ 注文者が資材提供・建設機械貸与をする場合の内容と方法
足場材や重機を注文者が提供する場合など、責任分界点を明確に。
所有権・搬入時期・破損時の対応などを明記しておくと安心です。
⑪ 完成確認の検査時期・方法および引渡し時期
完成検査の実施者・基準、そして完了日をいつとするか。
引渡し=契約履行完了という重要な節目であるため、トラブル防止の観点から記載必須です。
⑫ 請負代金の支払時期および方法(工事完成後)
最終的な請求・支払のスケジュール。
完了検査後〇日以内支払など、現金・手形の別を明確にします。
⑬ 瑕疵担保責任・保証保険契約の締結などに関する定め(定める場合)
完成物が契約通りでない場合の責任追及・補修義務。
保険加入(住宅瑕疵担保責任保険)や補修費の範囲などを記載します。
⑭ 履行遅滞・債務不履行時の遅延利息・違約金・損害金
完成遅れ・不払い等へのペナルティ内容。
遅延利率(年〇%)や違約金の有無、上限などを契約に反映させます。
⑮ 契約に関する紛争解決方法
裁判所の管轄や、あっせん・調停の利用を明記。
「〇〇地方裁判所を第一審の専属的合意管轄」といった定型文が多く使われます。
⑯ その他国土交通省令で定める事項
例:電子契約を利用する場合の方式、押印省略の取扱いなど。
情報通信技術の利用に関する規定(第19条第3項)もここに含まれます。
この16項目は、元請契約だけでなく下請契約にも原則適用されます。実務では漏れのない記載と相互交付を行うことで、監督処分や契約無効のリスクを未然に防ぐことができます。

契約書の交換が省略できるケース
🔹基本契約と注文書・請書による契約の成立
【1. 基本契約書の締結と交付】
- まず、発注者(元請)と請負者(下請)との間で、継続的な取引に関する「基本契約書」を締結し、両当事者が署名または記名押印のうえ、相互に書面を交付します。
- この基本契約書には、次のような共通的な契約条件(契約約款)を明記します。
※建設業法19条に定める項目のうち注文書に記載されない事項
- 契約書に代わる個別注文書・請書の取り扱い
- 支払条件
- 瑕疵担保責任
- 契約解除事由
- 損害賠償や遅延損害金の扱い
- 紛争解決方法 など
【2. 取引ごとに注文書・請書を交換】
実際の個別取引(建設工事の発注)ごとに、下記の手続きを取ります。
- 元請が注文書(契約書に代わる文書)を発行
- 下請が請書(注文書への同意書)を返送
- 双方が記名押印または署名をして、相互交付または写しを保管
注文書と請書には、工事内容・金額・工期など、その工事に固有の事項を明記します。
【3. 約款の明示・添付が必要】
この方法を有効とするには、注文書・請書と一体として「基本契約約款(共通契約条件)」を明示することが重要です。具体的には:
- 注文書・請書に「基本契約日付とその内容に準拠する旨」を記載する
- 基本契約の約款を注文書に添付、または裏面印刷する
- 注文書に「別紙約款を契約内容とする」旨の条項を含める
この形式により、建設業法第19条に基づく「契約内容の明確化」「相互交付義務」が事実上満たされるとされています。
※留意点
| 項目 | 留意内容 |
| 法的要件 | 書面(紙)による相互交付が原則。電子契約の場合は別途同意が必要。 |
| 約款の明示 | 基本契約の存在と内容を、注文ごとに確認できるようにする。 |
| 紛争リスク | 書面不備や約款の未確認は、契約の有効性や解釈を巡るトラブルに発展することがある。 |
まとめ
この「基本契約+注文書・請書方式」は、実務上非常に広く用いられており、一度の契約書締結で継続的な取引を効率化できる手段です。ただし、建設業法第19条の趣旨(契約内容の明確化・交付義務)を形骸化させないよう、以下の3点を必ず守る必要があります:
- 基本契約書の明確な締結と相互交付
- 注文書・請書で工事ごとの固有条件を明記
- 基本契約約款の明示(添付または裏面印刷)

工事契約書に貼る印紙税について
1. 印紙税が必要な文書とは?
建設工事の契約においては、以下のような文書が印紙税法の「第2号文書(請負に関する契約書)」として課税対象になります:
- 工事請負契約書(元請・下請を問わず)
- 注文書および請書(請負契約としての性質がある場合)
- 基本契約書(請負契約の内容を含むもの)
※ 「見積書」や「発注確認書」などの形式でも、請負契約の成立を証明する内容であれば課税対象になります。
2. 課税文書に該当する要件
以下の3要件をすべて満たすと、印紙税が課されます:
- 契約当事者間の請負関係が成立している
- 契約金額が明記されている
- 契約の成立を証明するために作成される文書である
→ よって、「契約の成立前に交わす単なる参考資料」や、「契約金額が記載されていない打合せメモ」は非課税となることもあります。
3. 印紙税額の早見表(令和6年11月18日以降)
| 請負金額(税抜) | 印紙税額(1通) |
| 1万円未満 | 非課税(印紙不要) |
| 1万円以上~100万円以下 | 200円 |
| 100万円超~200万円以下 | 400円 |
| 200万円超~300万円以下 | 1,000円 |
| 300万円超~500万円以下 | 2,000円 |
| 500万円超~1,000万円以下 | 10,000円 |
| 1,000万円超~5,000万円以下 | 20,000円 |
| 5,000万円超~1億円以下 | 60,000円 |
| 1億円超~5億円以下 | 100,000円 |
| 5億円超~10億円以下 | 200,000円 |
| 10億円超~50億以下 | 400,000円 |
| 50億超 | 600,000円 |
※ 税抜金額で判断します。税込表示の場合、消費税相当額を差し引いてもよいとされています。
4. 実務上の注意点
| ポイント | 解説 |
| 両者で1通ずつ交付 | 収入印紙は、原則として契約書原本1通ごとに必要です。双方で1通ずつ保有する場合は、それぞれに印紙が必要です。 |
| コピーには不要 | 印紙税がかかるのは「原本」だけです。写し(コピー)には不要。 |
| 電子契約は印紙不要 | 電子契約(クラウド署名など)で契約した場合は、印紙税非課税です(紙の「課税文書」に該当しないため)。※ただし電子契約の要件に注意 |
| 印紙の貼付忘れは過怠税 | 所轄税務署に発見されると、印紙税額の3倍の過怠税(最大)が課されることもあります。 |
5. 印紙の貼付と消印の方法
- 印紙は契約書の空白スペースに貼る
- 契約当事者のいずれかが印紙の上に「消印」(会社名+日付または代表者印)
- 収入印紙は郵便局や法務局などで購入可能
まとめ
- 建設工事の請負契約書は、印紙税法上の「第2号文書」に該当する
- 契約金額に応じた収入印紙を貼り、消印が必要
- 電子契約なら印紙は不要(導入を検討する価値あり)

FAXでの注文書請書のやり取りは実は違法
建設業法第19条第3項では、契約書面の代替として「電磁的な方法(=電子契約等)」による契約が一定の条件下で認められています。しかし、ファックスによる契約はこの「電磁的方式」に該当しません。
以下に詳しく解説します。
【結論】
ファックス(FAX)での契約は、建設業法第19条第3項の「電磁的方式による交付」とは認められません。
【理由と根拠】
● 建設業法第19条第3項の規定:
請負契約の当事者は、紙による書面の交付に代えて「政令で定めるところにより」「相手方の承諾を得て」「電子情報処理組織を使用する方法その他情報通信の技術を利用する方法」で交付できる。
● これを受けた政令・省令(建設業法施行規則等)では、次のような要件が定められています:
相手方の承諾があること
契約の真正性(改ざんされていないこと)と完全性が確保されること
相手がその内容を保存できること(再表示可能性)
❌【ファックスが該当しない理由】
| 要件 | ファックスでの契約 | 電子契約(例:PDF+電子署名) |
| 相手の承諾 | ○ 条件次第では可能 | ○ 条件次第で可能 |
| 改ざん防止・完全性の保持 | ✕ 改ざんの検知ができない | ○ 電子署名やタイムスタンプあり |
| 保存・再表示性 | ✕ 紙媒体のスキャンのみ | ○ 電子的に保存・再利用可能 |
→ ファックスは単なる画像転送であり、電子署名もタイムスタンプも付せず、文書の真正性や完全性を担保できません。そのため、第19条第3項の「電磁的交付」とは認められません。
✅【実務上の推奨】
電磁的交付を行う場合は、以下のような電子契約システムの利用を検討すべきです:
Adobe Sign、DocuSign、クラウドサイン等
PDFで契約内容を送信し、相手方の同意を明確に取得した上で、電子署名を行う形式
第5章 法定帳簿の不備・未保存~施工体制台帳・注文書・工事経歴書の管理不備

標識の掲示と帳簿管理~「見える化」と「保存」が許可業者の責務
建設業を適正に営むためには、現場の施工管理や技術者の配置だけでなく、「標識の掲示」や「書類の保存」といった地道な管理業務も極めて重要です。これらは見過ごされがちですが、建設業法に明確に規定された義務であり、怠れば監督処分や社会的信用の失墜を招くおそれがあります。
まず、建設業法第40条は「標識の掲示」について定めており、建設業者はその営業所(店舗)および発注者から直接請け負った建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所へ標識(建設業の許可票)を掲げなければなりません。この標識には、許可を受けた業種、一般建設業または特定建設業の別、商号、代表者氏名、許可番号等の情報が表示され、現場では主任技術者または監理技術者の氏名も併記することが求められます。標識の様式や記載事項は建設業法施行規則により定められており、虚偽表示や掲示の欠落は監督処分の対象となります。
一方、帳簿類の保存に関しては、建設業法第40条の3により、元請業者が下請契約を締結した場合に作成が義務づけられている「施工体制台帳」や「再下請通知書」などの帳簿類を、工事完了後5年間保存することが定められています。これは、施工体制の透明性確保と適正な監督責任の履行を目的としています。保存が義務付けられた帳簿が未整備または紛失していた場合、建設業許可の更新や経営事項審査等において不利益を被るだけでなく、立入検査や監査の際に行政指導・処分の対象となり得ます。
なお、建設業法第40条の2は、帳簿とは関係なく、「無許可業者が、許可を受けた建設業者であるかのような表示をすることを禁止する条文」であるため、帳簿保存義務とは別の規制です。誤って表示した場合でも、意図の有無にかかわらず処分の対象となるため、商号や広告物、ホームページ等の表現にも注意が必要です。
帳簿や標識は、外部に対して会社の信頼性や法令順守姿勢を示す「見える化」の象徴でもあります。許可業者としての責任を果たすためには、法定の標識を正しく掲げ、必要な書類を整備・保存する体制を社内で確立することが欠かせません。これらの基本的な管理こそが、安定した受注と持続可能な企業経営の土台となります。

建設業法第40条の3と施行規則による帳簿整備の実務~帳簿の記載事項(施行規則第26条第1項)~
帳簿には、以下の内容を工事ごとに記載しなければなりません:
🔹 1. 営業所代表者に関する情報
氏名および就任年月日
🔹 2. 注文者との契約に関する事項
工事名・現場所在地
契約年月日、注文者の氏名・住所・許可番号(ある場合)
完成検査年月日および引渡年月日
🔹 3. 新築住宅の契約に関する事項(住宅瑕疵担保責任関連)
床面積、負担割合、保険法人名等(対象工事のみ)
🔹 4. 下請契約に関する事項
下請工事名・所在地
契約年月日、下請負人の情報(名称・住所・許可番号)
完成検査日および引渡日
下請代金、支払状況、手形の有無、遅延利息等(※法24条の6に該当する契約の場合)

帳簿への添付が必要な書類(施行規則第26条第2項)
帳簿には、次の書類を添付または写しを保存することが求められます:
- 19条1項・2項の契約書面またはその写し
- 支払関係書類(手形・遅延利息など)
- 施工体制台帳(技術者・下請の内容などが記載された部分)
- その他、関係書類を整合的に保存
※添付が重複する場合、関係を明記すれば記載を省略可能(26条4項)
第6章 違反の結果と再発防止~指導・勧告・取消処分のリスクと経営への影響

~知らなかったでは済まされない
~知らなかったでは済まされない
建設業法違反が発覚した場合、その内容や程度に応じて、行政庁から「指導」「勧告」「業務停止命令」「許可取消処分」などが下されます。さらに、公共工事の指名停止や取引停止など、直接的な経済的打撃も発生します。場合によっては、違反行為が「虚偽申請」「不正取得」「談合・名義貸し」などに該当し、刑事罰の対象となることもあり得ます。重要なのは、こうしたリスクを未然に防ぐための「社内コンプライアンス体制」の整備です。経営者だけでなく、現場責任者・事務職員も含め、法令理解を徹底させ、違反リスクの芽を早期に摘むことが肝要です。建設業における信用は、一度失えば取り戻すのに長い時間がかかります。法令を「守るべき枠組み」としてではなく、「経営の基盤」として理解することが、今後ますます求められる時代です。

建設業法に基づく行政処分の体系(第28条)
【1】指示処分(建設業法第28条第1項)
■ 概要:
- 最も軽度な行政処分
- 違反を是正させるための改善命令
- 原則として書面による指導
■ 処分の対象となる典型的な違反:
- 帳簿の記載漏れや保存不備(第40条の3)
- 下請契約書面の交付忘れ(第19条第1項)
- 標識未掲示(第40条)
- 施工体制台帳の記載不備
- 軽微な工事での主任技術者の資格不備
■ 処分内容:
- 違反内容を是正し、再発防止措置を講じるよう命令
- 是正報告書の提出を求められることもある
■ 実務上の影響:
- 公表はされないことが多い
- 経営事項審査や格付に直接の影響は少ない
- ただし繰り返すと重処分に進む
【2】営業停止処分(建設業法第28条第2項)
■ 概要:
- 一定期間、建設業としての営業活動が全面的または一部停止
- 対象工事の受注・着工・請負契約の締結が禁止される
■ 処分の対象となる典型的な違反:
- 建設業許可業者による名義貸し
- 監理技術者・主任技術者の不配置
- 虚偽記載の施工体制台帳提出
- 下請代金支払い遅延・手形乱用等(第24条の6関連)
■ 処分内容:
- 停止期間は7日〜30日程度が一般的(ただし重度の場合は90日超もあり)
- 工事単位・営業所単位での停止命令もあり得る
■ 実務上の影響:
- 公共工事の指名停止措置と連動
- 処分内容は各自治体や国交省のウェブサイトで公表
- 社会的信用の低下、契約の解除・入札失格など重大な影響
【3】許可取消処分(建設業法第28条第3項)
■ 概要:
- 最も重い処分
- 許可そのものが無効になり、建設業者としての資格を喪失
- 再申請は5年間できないケースが多い(欠格要件該当)
■ 処分の対象となる典型的な違反:
- 無許可営業(第3条違反)
- 欠格要件に該当(第8条違反:暴力団関与、破産、禁固刑等)
- 指示処分・営業停止処分を無視して違反を継続
- 虚偽の内容で許可を受けた場合(第29条違反)
■ 処分内容:
- 許可を自動的に失い、元請・下請問わず建設業として一切の業務が禁止
- 行政庁から取消通知書が送付される
■ 実務上の影響:
- 経営事項審査の失格・公共工事の排除
- 社員の雇用喪失や関連会社への影響も重大
- 許可再取得までに長期間を要し、実質的に廃業に追い込まれるケースが多い

補足:処分の選定基準(国交省の判断指針)
行政庁は以下のような観点で処分の程度を決定します:
| 判断要素 | 内容例 |
| 違反の重大性 | 法令の根幹に関わるか/社会的影響の大きさ |
| 違反の継続性 | 是正せず放置しているか/複数回か |
| 故意・過失の有無 | 故意または重大な注意義務違反があるか |
| 是正努力の有無 | 自主的に改善・報告しているかどうか |
| 事業体制の再発防止措置 | 教育・内部管理の充実があるか |

監督処分を受けた場合の対処法と、再発防止策の構築
処分を受けたらまず何をすべきか?【初動対応】
監督処分通知を受けた場合、企業としては以下のような初動対応が必要です。
1. 内容確認と処分理由の精査
通知書に記載された違反の内容、法的根拠、証拠資料を正確に確認
誤認や事実誤認がある場合、早急に担当窓口(国交省・都道府県)へ意見陳述の準備
2. 社内の関係部署への通達と対応チームの立ち上げ
法務・現場・総務・営業などと連携して事実関係を精査
処分の影響範囲(現場停止、入札資格等)を整理
3. 処分に応じた措置命令の履行
指示処分:是正報告書の提出
停止処分:対象工事・営業所の停止と通知掲示
取消処分:関係先への通知、代替体制の検討(グループ会社等)
処分が企業にもたらす影響と、そのリスク管理
| 項目 | 影響内容 |
| 信用低下 | 官公庁・取引先からの信頼失墜。指名停止リスト入りの可能性 |
| 経審評価低 | 下総合評定値P点やW点の著しい減点 |
| 公共工事の失注 | 営業停止中の契約は解除されることもある |
| 社内士気の低下 | 特に下請業者や従業員に与える影響が大 |
再発防止に向けた社内体制の見直し
- 法令遵守チェックリストの整備
建設業法第19条・第26条・第40条の3・帳簿・技術者配置・契約書面義務などの遵守状況を定期的に点検
- 内部監査制度の導入
年1回以上、外部専門家(行政書士・社会保険労務士等)による法令遵守点検を実施
実務マニュアルの見直し・教育研修を義務化
- 情報共有とリスク感度の向上
「自分ごと」として社員全員に処分内容と再発防止策を周知
実際の違反事例をケーススタディとして全社教育に組み込む