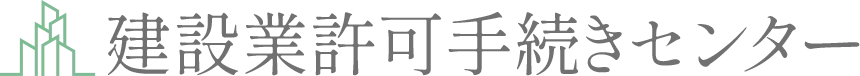建設業許可取得のためのステップバイステップガイド
2025/05/17
建設業許可を取得することは、事業を次のステージに進めるための重要なステップです。本記事では、初めての方でもわかりやすくステップバイステップで解説します。まずは、どのような書類が必要なのか、許可を得るための条件は何かを詳細に確認します。さらに、よくある質問にも答えながら、具体的な手続きの流れを見ていきましょう。建設業界での成功への道筋を共に探っていきます。
目次
建設業許可が必要な理由を知りビジネスの成長を促進する

建設業許可がもたらす信頼性と競争力の向上
建設業許可を取得することは、事業者としての信頼性を大幅に向上させます。許可を持つことは、法的に定められた基準を満たしている証であり、取引先や顧客に対して安心感を提供します。特に、公共工事や大規模プロジェクトにおいては、許可の有無が重要な選定基準となることが多く、競争力の強化に直結します。また、許可を取得することで、経営管理や技術力の向上が図れるため、社内の体制強化にもつながります。これにより、ビジネスの持続可能性が高まり、長期的な成長につながります。許可を持つことで得られる信頼性は、金融機関との取引や新規事業の展開においても大いに役立ちます。

法律遵守とビジネスリスクの軽減について
建設業許可を得ることは、法律を遵守するための第一歩です。無許可での営業は法的リスクを伴い、重大なペナルティや罰金の対象となる可能性があります。許可を取得することで、これらのリスクを回避し、健全な事業運営が可能になります。また、法律に基づいた適切な業務管理が行えるため、ビジネス上のトラブルを未然に防ぐことができます。さらに、許可取得の過程で求められる財務状況や技術者の確保は、企業内部の体制を整える絶好の機会となり、結果的に経営の安定性を高めます。法律遵守は企業の信頼性を高めるだけでなく、企業としての社会的責任を果たすことにもつながります。

許可取得による新たなビジネスチャンスの創出
建設業許可を取得することで、新たなビジネスチャンスが広がります。許可の取得により、公共工事への参入が可能となり、より大規模なプロジェクトの受注が期待できます。さらに、許可を持つ企業としての信頼性が向上するため、取引先の数や質が向上する可能性があります。許可取得は単なる法的要件を超えて、事業拡大のための戦略的ステップとなり得ます。また、許可を持つことで、クライアントからの信頼を得やすくなり、リピートビジネスや紹介案件の獲得にもつながるでしょう。特に競争が激しい市場では、許可の有無が契約獲得の決め手となることも少なくありません。

地域社会への貢献と許可の役割
建設業許可を取得することは、地域社会への貢献にもつながります。許可を持つことで、地域のインフラ整備や公共工事に参加する機会が得られ、地元経済の活性化に寄与します。さらに、適切な管理体制や技術者を確保することで、質の高い工事を提供し、地域住民の生活環境の向上に貢献します。建設業許可は単なる書類上の手続きにとどまらず、社会的責任を果たすための重要な基盤であると言えます。地元との信頼関係を築くことで、長期的なビジネスの安定や発展が期待でき、地域に根付いた企業としての価値が高まります。
建設業許可の必要性について

建設業許可とは何か
「建設業許可」とは、建設業法(昭和24年法律第100号)に基づき、一定規模以上の建設工事を元請・下請を問わず請け負うために、国または都道府県から受ける許可です。この制度の目的は、建設業者の適正な運営を確保し、発注者保護と公共の利益を守ることです。
建設業法第3条により、次のように定められています:
「元請、下請を問わず、1件の請負代金が税込500万円(建築一式工事は1,500万円または延べ面積150㎡を超える木造住宅)以上の工事を請け負う場合には、建設業許可を取得しなければならない」
つまり、許可がなければ一定規模以上の建設工事を請け負うことはできません。

なぜ建設業許可が必要なのか
(1)法的義務
前述のとおり、一定額以上の工事を請け負う場合は許可がなければ違法となります。無許可営業は建設業法違反となり、懲役刑や罰金刑などの処罰を受けるおそれがあります(建設業法第50条、同法第45条)。
(2)発注者の信頼獲得
公共工事はもちろん、民間工事でも大手企業や不動産会社などは「建設業許可を取得していること」を発注条件にしている場合がほとんどです。許可があることで、会社の経営状況・技術力・社会的信頼性などが一定水準にあると認められ、発注者の安心につながります。
(3)公共工事の受注に不可欠
公共工事を請け負うためには、建設業許可が必須であり、さらに経営事項審査(経審)を受けた上で、自治体への指名願い提出が必要になります。つまり、許可がなければ公共工事の市場に参入することすらできません。
(4)会社の成長と信用力向上
許可業者は信用力が高いため、以下のようなメリットがあります:
- 金融機関からの融資が有利になる
- 取引先からの評価が上がる
- 人材採用がしやすくなる
- 長期的な経営基盤の強化
無許可では、500万円未満の小規模工事に限定され、事業の拡大に大きな制約を受けることになります。

無許可営業のリスク
リスク内容詳細
違法行為・・・建設業法第3条違反により、懲役6か月以下または罰金100万円以下の刑罰(法第50条)
民事責任・・・工事に関するトラブルで損害賠償請求を受けた場合、無許可業者の責任が重くなる可能性
社会的信用の失墜・・・元請や発注者からの信用失墜、契約の打ち切りや損害賠償の対象になることも
公共工事の締め出し・・・経営事項審査を受けられないため、自治体への入札資格が得られず市場から締め出される

許可を取得することのメリット
✅ 信用力の獲得
行政庁からの許可を得ることで、一定の経営基盤・技術力・法令遵守体制を備えていると認められ、対外的な信頼度が大きく向上します。
✅ 公共工事・大手案件への参入
公共工事の受注はもちろん、民間の大型案件でも建設業許可を持っているかどうかが選定の基準となります。
✅ 営業範囲の拡大
500万円を超える工事を受注することが可能となり、工事件数や単価の向上によって売上規模の拡大が可能になります。
✅ 経営事項審査や格付け制度への参加
建設業許可を取得していれば、さらに経審を受けて各自治体の「格付け制度」などにも参加可能となり、上位ランクを得れば受注機会が大きく広がります。
ゼロからはじめる建設業
――企業勤めから独立、そして建設業許可へ

ある建設業許可を取得した社長の例
建設の世界に飛び込んで十数年。ふと気づけば、私は「建設業許可業者」として、正式に会社を立ち上げるところまで来ていた。最初は、工具の名前すらろくに知らなかった私が、今や年間数千万円の工事を受注している。今回は、そんな私の「建設業許可取得までのリアルな道のり」を紹介したい。

第一章:建設会社への入社――すべてはここから始まった
20代半ば、未経験で入社したのは、町の小さな建設会社。最初の仕事は、先輩の後ろをついて回って、現場の掃除や資材運搬を手伝うことだった。図面も読めず、現場での掛け声にも戸惑う毎日。けれど、少しずつ経験を重ねるうちに、「できること」が増えていく喜びがあった。
この時期に大切だったのが、「資格取得」だ。会社の方針もあり、2年目で2級建築施工管理技士補を取得。5年目には実務経験を積んで2級建築施工管理技士(国家資格)を取り、現場代理人として小規模な現場を任されるようになった。

第二章:独立の決意――一人親方としての挑戦
会社勤めを10年続けた頃、ふと「独立」という二文字が頭をよぎるようになった。年齢的にも40歳を目前にし、「自分の裁量で仕事を選び、利益も自分の責任で得たい」と思うようになった。
退職後、個人事業主(いわゆる一人親方)として登録し、元請業者から仕事をもらいながら現場をこなす日々が始まった。とはいえ、最初は不安も大きい。税務の知識、保険関係、労災特別加入制度など、経営者としての自覚と責任を自分で背負うことになる。
だがその一方で、「一人でやるからこそ身につく感覚」もあった。工事の原価管理、資材発注、請求書の発行など、これまで事務方が担っていた業務もすべて自分の手でこなすことになる。これは経営業務の管理経験としても、実は非常に重要だった。

第三章:許可を取るか、取らずに済ますか――その壁
数年一人親方として活動していたが、あるとき、大手ハウスメーカーの下請に応募した際にこう言われた。
「建設業許可、持ってないんですね…うちは500万円を超える案件が多いので、無許可では契約できないんです。」
そう、建設業許可は請負金額500万円(税込)以上の工事には必須。つまり、許可がないと大きな案件には手が出せない。
「もっと大きな現場に関わりたい」「売上をさらに伸ばしたい」――その思いが決め手となり、許可取得を決意した。
将来の建設業許可に備えて
――一人親方が今から保管すべき書類と心がけ

建設業許可の取得は、ある日突然「思い立ってすぐ取れる」ものではありません。特に「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」としての要件を証明するには、「過去の実績を裏付ける書類」が非常に重要です。
では、今職人や一人親方として活動している方が、将来の許可取得に向けて、どのような書類を整えておけばよいのでしょうか?以下にそのポイントを具体的に示します。

経営経験の証明のための書類(経営業務の管理責任者に備える)
建設業許可では、「経営業務の管理責任者(いわゆる経管)」となるためには、個人事業主としての経営経験が5年以上必要です。この経験を証明するためには、以下の書類が重要です。
🔹 確定申告書(控)※必須
- 税務署の受付印があるもの、またはe-Taxの送信票付き
- 5年分保管(白色でも青色でも可)
🔹 工事請負契約書または注文書・請書
- 「誰と契約したのか」「いくらで請け負ったのか」「いつ施工したか」が明記されていること
- できれば元請業者の印も押された書類(PDFや写しでも可)
🔹 請求書・領収書
- 請負代金のやり取りを明確にする資料
- 振込明細など支払いの裏付けとセットで保管
🔹 工事写真や工事日報
- 書面だけでなく、実際の施工状況の写真もあると説得力が増す
- 工事場所・工期・工事種別がわかるように整理

技術者としての実務経験の証明(専任技術者に備える)
専任技術者となるには、資格または実務経験の証明が必要です。特に実務経験で申請する場合、客観的な証拠が求められます。
🔹 実務経験証明に使える資料
- 書類名説明
- 工事台帳・施工実績一覧「工事件名、工期、金額、発注者、工事内容」が一覧になっていると良い
- 現場写真・図面担当した現場が分かる証拠。自分がどの工種に関与したかを補足メモとともに保存
元請会社発行の実務証明書将来の申請時に頼めるよう、関係を良好に保っておくとよい

その他心がけたい保管・管理のポイント
✅ 書類は「年別・取引先別」で整理する
→ スキャンしてPDF化+バックアップを取っておくと、紙紛失にも対応できる。
✅ 書類の真正性を意識する
→ 自分だけでなく、相手の署名・押印がある書類の方が信頼性が高く、役所での証明に有利。
✅ 税理士・行政書士に相談できる体制を整える
→ 毎年の確定申告の際に「建設業許可を視野に入れた帳簿のつけ方」を意識しておくと、いざという時にスムーズ。
よくある質問に答える建設業許可取得ガイド

よくある質問トップ10とその回答
建設業許可を取得する際には、多くの方が共通する疑問を抱えます。ここでは、よくある質問トップ10とその回答を紹介します。まず、「建設業許可はどのような種類がありますか?」という質問が多く寄せられます。建設業許可には、特定建設業と一般建設業の2種類があり、それぞれ異なる条件が設定されています。また、「申請にはどのくらいの時間がかかりますか?」という質問も一般的です。申請から許可が下りるまで、通常は4週間から8週間程度かかります。その他、提出書類や手数料についての質問も多く、適切な書類を揃えることが重要です。これらの質問に対する詳細な回答を知ることで、手続きがスムーズに進むことでしょう。

初めての申請者が抱える疑問を解決
初めて建設業許可を申請する際、何から手を付けていいのかわからないという不安が付きものです。例えば、「建設業許可の条件は何ですか?」という疑問を持つ方が多いです。許可を取得するためには、一定の経営経験や技術者の配置が求められます。また、「どのような書類を準備すればよいですか?」という質問もよくあります。必要な書類は、法人の場合は定款や決算書、個人事業主の場合は住民票や所得証明書など、多岐にわたります。さらに、許可取得のための手数料や、更新時の流れについての疑問を持つ方も多く、これらを事前に把握しておくことが重要です。疑問を一つ一つクリアにすることで、安心して申請に臨めるでしょう。

申請手続きに関するFAQと具体的回答
建設業許可の申請手続きに関するFAQは、初めての方にとって非常に重要です。まず多くの方が疑問に思うのが、どのような書類が必要なのかという点です。必要となる書類には、会社の基本情報を記載した法人登記簿謄本や、財務状況を示す財務諸表などがあります。また、申請にはどのくらいの期間がかかるのかもよく尋ねられます。通常、許可取得までには3ヶ月から半年程度かかることが一般的です。申請手続きの流れや必要な書類については、専門家に相談することでスムーズに進めることができます。

許可取得までのタイムラインとプロセス
建設業許可を取得するためのタイムラインは、申請者が準備すべき要素によって異なります。最初のステップとして、申請書類の準備があります。この段階では、必要な書類をしっかりと揃えることが重要です。その後、申請書を提出し、審査が行われます。この審査では、申請者の過去の事業履歴や財務状況が評価されます。最終的に許可が下りるまでには、通常3ヶ月から6ヶ月の期間を要します。この期間中、担当者とのコミュニケーションを重視し、追加書類の要求などに迅速に対応することが、スムーズな許可取得の鍵となります。
「契約書なんていらない」は通用しない
――外注職人が将来の許可取得のために契約書を交わすべき理由

「長年の付き合いだから」「口約束で十分」「元請との信頼関係がある」
――こうした理由で、工事を請け負うたびに契約書を作っていない一人親方や職人の方は少なくありません。
しかし、将来的に建設業許可を取得したいと考えているなら、契約書を交わしておくことは“必須”です。
なぜなら、建設業許可の審査においては、過去の施工実績や経営業務の経験を書面で証明できなければ、一切評価されないからです。

建設業許可に必要な「経験の証明」と契約書の関係
建設業許可の要件には、次のような「経験証明」が求められます:
- 経営業務の管理責任者としての経営経験(5年等)
- 専任技術者としての実務経験(学歴によって3~10年)
このような経験を「客観的に証明」するために必要なのが、契約書や請書、注文書などの工事の証拠書類です。
特に、外注で職人として働いていた場合、次の点が非常に重要になります。
求められる情報契約書で明記されるべき事項
- 工事の種類・・・○○工事、××改修工事などの記載
- 請負者(あなた)の氏名・住所・・・本人確認と個人事業主名義の一致確認
- 発注者の情報・・・元請会社の正式名称・住所
- 請負金額・・・500万円以上かどうかで許可要否が変わる
- 工期・・・実務経験期間の算定に重要
- 契約日・・・実績時期の特定に必要
- 署名・押印・・・双方の合意を証する印(特に発注者の印)

「契約書がない場合の不利な点」
以下のような不利益が発生します:
- 経営・実務経験が証明できず、許可申請が通らない
- 確定申告書だけでは「建設工事を請け負っていた」とまでは判断されない場合がある。
- 口約束で工事した実績は“ゼロ”として扱われる
- 経験年数が不足し、要件を満たさなくなることも。
- 元請が協力してくれないと実績証明が取れない
- 許可申請時に「実務証明書」をお願いしても、会社都合や退職等で対応不可になることもある。

元請との関係を壊さずに契約書を交わすコツ
「契約書をください」と言い出しにくい職人さんも多いと思いますが、実は元請側も契約書を用意する義務がある(建設業法第19条の2、注文者と受注者の間の書面交付義務)ため、法的には当然の行為です。
以下のように伝えると、角が立ちません:
「将来、建設業許可を取ることを目指しているので、実績証明に使えるように、書面をお願いできますか?」
また、テンプレートを自分で用意して「請負契約書」や「注文書・請書」として提出・署名をもらう形でも構いません。
うっかり無許可で500万円以上の工事を請け負ってしまったらどうなる?

「500万円を超える工事を請け負ってから、許可が必要と知った」
「元請から急に大きな案件を振られて、断れずに受けてしまった」
――こうした相談は、現場の一人親方や小規模工務店から実際によくあります。
建設業許可の制度は、請負者の技術力や経営力を一定以上に保ち、発注者を保護するための重要な仕組みですが、知らなかったでは済まされない法的義務があります。

法的な位置づけと違反の重大性
建設業法第3条は、以下のように規定しています:
「請負金額が税込500万円以上(建築一式工事は1,500万円または延床150㎡超の木造住宅)の工事を行う者は、建設業の許可を受けなければならない。」
そして、無許可でこれに違反すると、建設業法第47条により次のような刑事罰が科される可能性があります。
🔹 建設業法第47条第1項第1号:
許可を受けないで第3条第1項の規定に違反して建設業を営んだ者は、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金に処する。
法人が行った場合には、その代表者や従業員も処罰対象
実際に刑事処分が行われた事例もあり、“知らなかった”は免責されない

契約の法的効力はどうなるのか?
工事契約そのものが「無効」になることは通常ありません。民法上は契約自由の原則があるため、許可の有無によって契約自体が無効になるわけではありません。
ただし、以下のような重大なリスクが発生します:
契約トラブルの際に弱い立場になる・・・発注者から「無許可業者だった」として責任追及される可能性がある
発注者との取引停止・・・元請業者がコンプライアンス上、無許可業者との取引を中止するケースがある
許可取得時に不利益な扱い・・・過去に無許可営業の履歴があると、許可申請時に指導・注意・不許可処分になるおそれ
行政処分・公表のリスク・・・悪質と認定された場合、国土交通省または都道府県によって社名が公表されるケースもある

受注してしまった後の対応策
✅ 1. 自主的に行政庁に報告・相談
許可権者(都道府県または国土交通省地方整備局)に事実を報告し、許可取得の意思があることを伝える
自主申告によって、行政処分が軽減される可能性あり
✅ 2. 速やかに建設業許可申請を進める
現在の状況(経営業務の管理責任者・専任技術者・財産要件など)を確認し、最短での許可取得を目指す
行政書士などの専門家に相談し、申請準備を整える
✅ 3. 過去の実績を整理・書面化しておく
万が一、後日発注者や役所から調査が入った場合に備え、契約書・請求書・施工記録などを整備しておく
無許可業者への発注が建設業者に与える影響とは

法的根拠:建設業法第22条の禁止規定
建設業法では、建設業者が無許可業者へ工事を下請けに出すことを明確に禁止しています。
🔹 建設業法 第22条(許可を受けていない者への下請契約の制限)
建設業者は、その請け負った建設工事の全部または一部を、建設業の許可を受けていない者に請け負わせてはならない。
(ただし、軽微な工事はこの限りでない)
🔹 「軽微な工事」とは?
500万円(税込)未満の工事
建築一式工事は1,500万円未満または延床150㎡未満の木造住宅
これを超える金額の工事を、無許可業者に発注した場合は建設業法違反になります。